AIによる情報生成と社会の変容
メディアの信頼性が崩壊する未来
要はですね、AIが記事を書く時代になると、人間がちゃんとした記事を書いているかどうか確認する必要がなくなるわけですよ。でも、それってつまり、AIが勝手に嘘を広めても誰も責任を取らなくなるってことなんですよね。 今までは新聞社やテレビ局が情報の正確性をある程度保証していたわけです。でも、これからはAIが記事を書くとなると、「これ、本当に正しいの?」って誰も確かめなくなる可能性があるんですよ。 で、そうなるとどうなるかというと、ネット上の情報がカオスになるんですよね。誰かが適当にAIに記事を書かせて、それが事実として拡散される。間違った情報が当たり前のように受け入れられる社会になっていくんじゃないかと。 結局、メディアが発信する情報に対して、「これ、本当に大丈夫なの?」っていう疑念がどんどん増えていくと思うんですよね。で、人々はどの情報を信じればいいのか分からなくなる。つまり、メディアの信頼性がどんどん崩壊していく未来が来るんじゃないかと。
フェイクニュースがより巧妙になり、見破れなくなる
AIが記事を作ると、当然フェイクニュースもAIが作るわけですよね。で、問題なのは、AIが作るフェイクニュースって、めちゃくちゃ精巧にできるんですよ。 人間がフェイクニュースを作る場合って、どこかしらでボロが出るんですよね。でも、AIは過去の膨大なデータを学習して、それっぽい記事を作ることができる。だから、人間が読んでも「これ、どこかおかしいぞ?」って気づけなくなる可能性があるんですよね。 で、AIが作ったフェイクニュースが一度広まると、訂正するのがすごく難しくなるんですよ。今の時代でも、ネットでデマが広まると、それを打ち消すのに時間がかかるじゃないですか。これがAIによって加速すると、嘘が真実として定着するスピードが今よりもずっと速くなるんですよね。 結果として、社会全体が「何が本当で、何が嘘なのか」を判断できなくなっていくと思うんですよ。で、人々が「どうせ何も信じられないし、全部フェイクでしょ」みたいな感じになって、社会全体の情報リテラシーが崩壊するんじゃないかと。
AIが情報の管理者となる社会
誰が情報をコントロールするのか
AIが記事を書いて、それがメディアに掲載される時代になると、じゃあ「誰がAIをコントロールするのか?」って話になるんですよね。 例えば、政府がAIを運用すると、都合の悪い情報をAIに書かせないようにできるわけですよ。で、逆に都合のいい情報をたくさん出させることもできる。 企業がAIを使う場合も同じで、自社に有利な記事ばかりをAIに書かせることができるわけです。で、ユーザーはAIが書いた記事だからって「まあ、AIなら中立でしょ?」って思っちゃう可能性があるんですよね。でも実際は、AIの出す情報は運営者次第でいくらでも操作できるんですよ。 これが何を意味するかというと、情報の発信源が一部の権力者に握られて、一般の人が本当のことを知る機会が減るってことなんですよね。で、気づいた頃には「気づいた人だけが気づいている」みたいな状況になって、ほとんどの人は知らない間に操作された情報を信じるようになってるんじゃないかと。
「情報弱者」がさらに増える未来
結局、こういう時代になると、情報の真偽を見抜く力がない人がどんどん増えるんですよね。 例えば、今の時代でもネットのデマに騙される人っていますよね? AIが作った記事が当たり前になったら、それがもっとひどくなると思うんですよ。 AIの記事って、基本的に「それっぽいこと」を書くのは得意なんですけど、「本当に正しいかどうか」までは分かってないんですよね。でも、AIが作った記事が当たり前になったら、それを疑わずに信じる人が増える。で、情報弱者と情報リテラシーの高い人の間で、知識の格差がどんどん広がっていくと思うんですよ。 これが進むと、「AIが言ってるから正しい」とか「ニュースになってるから本当」っていう思考停止した人が増えていくわけですよ。で、結果として、世の中の判断力がどんどん低下していくんじゃないかと。 で、こういう時代になったらどうなるかっていうと、結局「声の大きい人が正義」みたいな世界になるんですよね。つまり、AIが出した情報を都合よく利用する人が得をする時代になって、普通の人は騙されやすくなるって話です。
AI時代の情報リテラシーと対策
情報リテラシーの格差が社会を分断する
要はですね、AIが作る記事のクオリティがどんどん上がって、見分けがつかなくなると、情報を見極められる人とそうでない人の間に大きな差が生まれるんですよ。 これまでも、ネットリテラシーが高い人と低い人の間には認識のズレがあったわけですけど、AIが普及することでその差がさらに拡大すると思うんですよね。 例えば、陰謀論とかデマを信じる人っていますよね? 今でもある程度はそういう人がいるんですけど、AIが自動で記事を書いて、それがもっと「それっぽく」なると、そういう情報に騙される人が増えるんですよ。 で、そうなると何が起こるかというと、社会の中で「AIの記事を鵜呑みにする層」と「AIの記事を疑う層」に分かれるんですよね。で、お互いに「お前らは騙されてる!」みたいな感じで対立が激しくなるんじゃないかと。 つまり、AIが普及することで、社会の分断が加速するってことなんですよね。
「真実を知る人」だけが得をする社会
で、こういう状況になると、結局「情報を見極める力がある人」だけが正しい情報を得て、より有利な立場になるんですよ。 例えば、投資とかビジネスの世界でも、AIが自動でニュースを作る時代になると、どの情報が本物かを見極められる人だけが成功するわけですよね。で、見極められない人は、AIが作った適当な情報に振り回されて損をするわけです。 結局、今の時代でも「情報強者」と「情報弱者」の差はあるんですけど、AIの進化によってこの差がもっと大きくなると思うんですよね。で、情報弱者はどんどん騙されて、情報強者はどんどん有利になっていく。 こういう未来になると、社会の格差がさらに広がるわけですよ。つまり、「情報を正しく扱える人」が勝ち組になって、「AIの言うことをそのまま信じる人」は負け組になるってことですね。
未来の働き方とAIの影響
AIによる「知的労働の自動化」
で、もうひとつ問題なのは、AIが記事を書けるようになるってことは、知的労働がどんどんAIに奪われるって話なんですよ。 今まで「クリエイティブな仕事だからAIにはできない」とか言われていた職業も、実はAIの方がうまくやれるようになる可能性があるんですよね。例えば、ライターとかジャーナリストとか、あるいはマーケティングの仕事とか。 要は、「情報を処理して、新しいものを作る」みたいな仕事は、AIの方が得意になってくるわけですよ。で、そうなると、今まで人間がやっていた仕事がどんどん不要になっていく。 で、最終的には「AIを使える人」だけが仕事を得られるようになって、「AIに仕事を奪われる人」はどんどん厳しくなるって未来が見えてくるんですよね。
「人間らしい仕事」しか残らない時代
で、じゃあどんな仕事が生き残るのかっていうと、「人間にしかできない仕事」なんですよね。 例えば、接客業とかカウンセリングとか、感情が絡む仕事ですよね。あと、創造性が求められる仕事もある程度は残ると思うんですけど、問題は「AIがどこまで進化するか」なんですよ。 結局、今のAIってまだまだ発展途上なんですけど、今後さらに進化すれば、もっとクリエイティブなことができるようになるわけです。で、そうなると、「人間にしかできない仕事」ってどんどん減っていくんですよね。 で、「じゃあ人間は何をすればいいの?」って話になるわけですけど、結局は「AIと共存するしかない」っていう未来になるんですよ。
AI社会で生き残るために必要なこと
情報を疑う力をつける
で、こういう未来になったときに、生き残るために必要なのは「情報を疑う力」なんですよね。 要は、「AIが言ってるから正しい」って思わずに、「本当にこれって正しいの?」って常に考える習慣を持つことが大事なんですよ。 今でも、ネットに書かれていることをそのまま信じる人っていますけど、AIが普及するともっとひどくなるんですよね。で、そうならないためには、「情報をそのまま信じない」っていう意識を持つことが重要になってくるわけです。
AIを使いこなす側に回る
あと、もうひとつ大事なのは、「AIに仕事を奪われるんじゃなくて、AIを使いこなす側に回る」ってことですね。 結局、AIが普及すると、「AIをどう使うか」が重要になってくるんですよ。で、AIを上手く使える人は仕事を増やせるし、そうじゃない人はどんどん仕事がなくなっていく。 だから、「AIが怖い」とか言ってる場合じゃなくて、「どうやってAIを活用するか」って考えるのが大事なんですよね。
まとめ:AI社会で生き残るには
結局のところ、AIが普及することで情報の信頼性が崩壊して、社会が混乱する未来が見えてくるんですよね。で、その中で生き残るためには、情報を疑う力をつけることと、AIを上手く使いこなすことが重要になってくる。 つまり、「AIに騙される側」じゃなくて、「AIを使いこなす側」に回ることが、生き残るためのカギになるんじゃないかと。 で、そうしないと、「AIが作った情報に騙されるだけの人生」になるわけですよ。で、それって結局、誰かにコントロールされる人生と一緒なんですよね。 だから、「AIの進化で何が変わるのか?」をしっかり考えて、自分がどう動くべきかを決めるのが大事ってことですね。
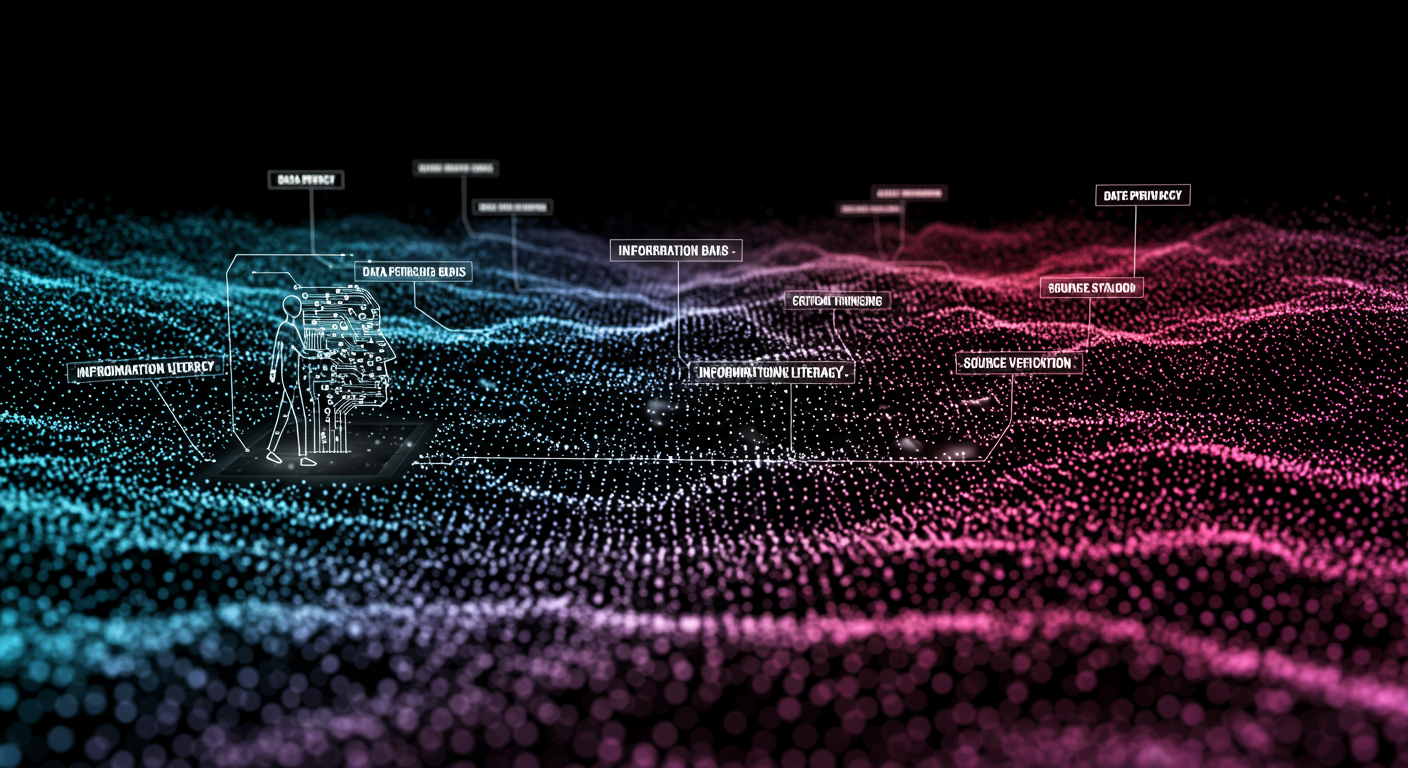


コメント