AI規制と国際競争の行方
アメリカとイギリスが署名を拒否した理由
要は、AIの規制っていうのは「安全性」と「競争力」のバランスをどう取るかって話なんですよね。今回のAIサミットでは、日本とかフランス、中国なんかも含めて60カ国以上が「AIを安全かつ倫理的に発展させよう」っていう宣言に署名したわけですけど、アメリカとイギリスはそれに乗らなかったと。理由はシンプルで、規制を強めるとイノベーションが遅れるからですね。 特にアメリカはGAFAみたいな巨大IT企業があるし、イギリスもAI開発で遅れを取りたくないわけです。ヨーロッパは「安全性重視」でガチガチに規制を作りたがるんですけど、それやっちゃうと「じゃあ中国が勝つよね」って話になる。要するに、規制を強めるとルールを気にしない国が有利になっちゃうんですよね。
中国がAI覇権を握る可能性
で、今の流れだと中国がAIの覇権を握る可能性はけっこう高いです。なぜかっていうと、中国は「とにかく先に作れ」っていうスタンスなんですよね。倫理とか安全性よりも、とにかくAIを強化して、社会にどんどん組み込んでいく。実際、中国ではすでに監視カメラにAIが組み込まれて、顔認識で市民の行動をトラッキングするシステムが動いてますよね。 これがどんどん進むと、AIが政治にも影響を与えるようになる。選挙のない国だからこそ、AIによる「最適な統治」が実現する可能性もある。AIが国民の行動を分析して、政府がそのデータを使って政策を決めるようになれば、独裁がより強化される。でも一方で、それが「効率的な政治」として機能しちゃう可能性もあるんですよね。 そうなると、民主主義の国々はどうするか。ルールを守りながらAI開発を進めようとしても、スピード感で負ける。で、「規制を強めた結果、中国に主導権を握られました」ってことになったら、本末転倒なわけです。
AI格差が広がる未来
先進国と発展途上国の格差
AIが進化すると、今の経済格差よりもさらに大きな「AI格差」が生まれるんですよね。アメリカとか中国みたいにAI開発を主導できる国は、どんどん経済成長していく。でも、AI技術を持ってない国はどうなるかっていうと、完全にAIの「消費者」になっちゃう。 例えば、AIを活用した金融システムや物流システムを持ってる国と、持ってない国があったら、当然ながら持ってる国が経済的に圧倒的に有利になる。今までは「労働力の安さ」で勝負できた国も、AIが労働の代わりをするようになれば、その強みすらなくなるんですよね。 要は、「人間が働くよりも、AIが働いた方がコストが安い」って状況になったら、発展途上国はどうやって生き残るのかって話になる。
個人レベルのAI格差
で、この格差って国レベルだけじゃなくて、個人レベルでも起こるんですよね。AIをうまく使える人と、使えない人で、収入の差がどんどん開く。 例えば、今でもプログラミングができる人とできない人では、給料の差がめちゃくちゃありますよね。それがAI時代になると、「AIを活用して仕事を効率化できる人」と「AIに仕事を奪われる人」に分かれる。で、後者の人はどんどん淘汰されていく。 例えば、AIを使って文章を書く人と、手作業で文章を書く人だったら、明らかにAIを使う方が速いしコストも安い。ってことは、ライターの仕事なんかはどんどん減っていくし、残るのは「AIを使ってより高度なアウトプットを出せる人」だけになる。 こういう流れが、ほぼ全ての職業で起こるわけです。だから、AI時代に「自分の仕事をどうAIに適応させるか」っていうのが、生き残るためのカギになるんですよね。
AI時代の社会と人間の変化
労働の価値が変わる
で、AIが普及すると何が起こるかっていうと、「人間が働く意味」がどんどんなくなるんですよね。今までは、「仕事をしてお金を稼ぐ」のが当たり前だったわけですけど、AIがほとんどの仕事をこなせるようになったら、「じゃあ、人間って何するの?」って話になる。 特に、単純労働とか事務作業みたいな仕事はAIが全部やるようになる。で、クリエイティブな仕事も「AIの補助がないとできない」みたいな状況になるわけです。例えば、デザイナーとかライターも「AIを使わないと勝負にならない」って時代が来る。 そうなると、仕事の価値自体が変わってくるんですよね。例えば、「AIにできない仕事」って何かっていうと、人間同士のコミュニケーションとか、感情を扱う仕事。心理カウンセラーとか、コーチングとか、そういう「人間だからこそできる」領域が重要になってくる。 でも、現実的にはAIがあらゆる仕事を効率化して、労働時間がどんどん減るはずなんですよね。問題は、「労働時間が減るのに給料はどうなるのか?」っていうこと。
ベーシックインカムの導入は必然か
AIが仕事を奪うと、当然ながら「仕事がない人」が増えるわけですよ。で、「仕事がない=収入がない」ってなると、社会が崩壊しちゃう。だから、どこかのタイミングで「ベーシックインカム」を導入せざるを得なくなると思うんですよね。 要するに、「みんなが仕事しなくても最低限の生活ができる」っていう仕組みを作らないと、経済が回らない。で、資本主義っていうのは「みんなが働いてお金を稼いで、消費する」っていう流れで成り立ってるわけですけど、AIが仕事を奪うと「みんな働かない=消費もしない」ってことになっちゃう。 だから、国家がある程度のお金を国民に配って、「最低限の消費は保証する」って仕組みが必要になるんですよね。これをやらないと、「仕事がある人」と「仕事がない人」の格差が極端に広がって、社会が不安定になる。
AIが生み出す新しい価値観
「働かなくてもいい時代」の到来
で、ベーシックインカムが導入されると、「じゃあ、人間は何をして生きるのか?」って話になるんですよね。今までは「仕事をして稼ぐ」のが人生の中心だったわけですけど、それが崩れると「生きる意味」みたいなものを考えざるを得なくなる。 要するに、「お金を稼がなくても生きていけるなら、人間は何をするのか?」ってことです。これまでの価値観だと、「仕事をしない=怠け者」みたいな考え方があったわけですけど、それが完全に崩れる可能性がある。 例えば、「好きなことをやって生きていく」っていうのが普通になるかもしれない。ゲームをしたり、絵を描いたり、音楽を作ったり。AIが労働を代替することで、人間は「創造的な活動」に集中できるようになるかもしれない。 ただ、ここで問題なのは、「何もすることがない人」はどうなるのかってこと。人間って、やることがなくなると退屈して、逆に不幸になるんですよね。だから、「自由に時間を使えるけど、何をしたらいいのかわからない」っていう新しい問題が出てくる。
AIと共生する社会の可能性
結局、AIが発展することで、社会のあり方が根本から変わるわけですよね。労働の価値が変わり、経済システムも変わる。で、「AIをうまく活用できる人」と「AIに振り回される人」で格差が生まれる。 でも、これって逆に言えば、「AIをうまく使える人が自由を手に入れる時代になる」ってことでもあるんですよね。例えば、今までは「お金を稼ぐために嫌な仕事をする」っていうのが当たり前だったわけですけど、AIを活用すれば、「好きなことをしながら収入を得る」みたいな生き方もできるかもしれない。 要するに、「AIを敵に回すんじゃなくて、どう味方につけるか」が、これからの時代のポイントになるんですよね。
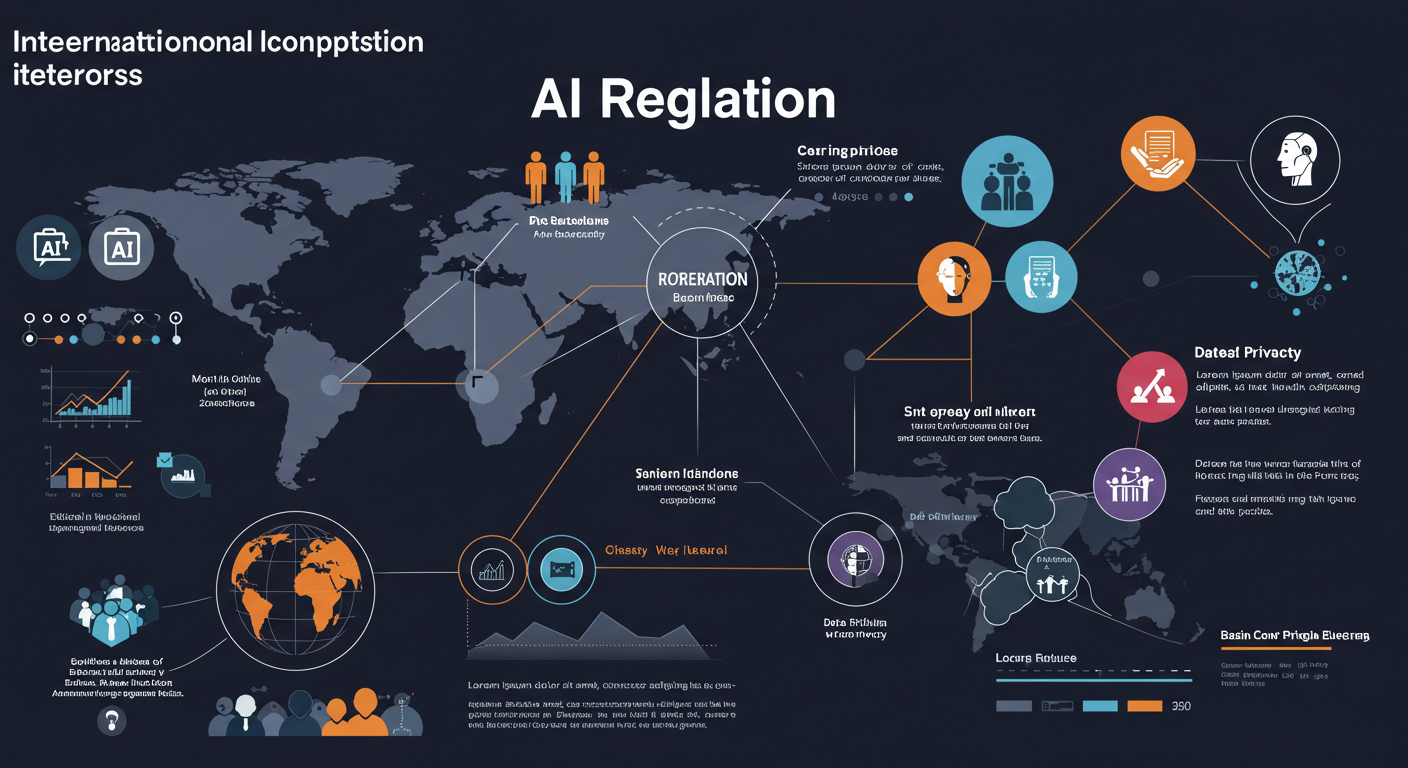


コメント