AIの透明性は結局「ほどほど」が正解なのか?
レッドハットの「現実路線」とは何か
要は、レッドハットが「AIの訓練データを完全公開しません」と言ってるわけですけど、これは結局のところ企業の生存戦略なんですよね。オープンソース文化の企業が「完全公開しない」というのは矛盾しているように見えるかもしれないですけど、現実問題として、AIの学習データを全部見せるのは無理なんですよ。個人情報とか企業の機密情報とか、開示するとまずいデータがゴロゴロしてるんで。 なので、「オープンソースの精神は守るけど、データの中身は見せませんよ」という中途半端な路線に落ち着いたわけです。これ、要するに「透明性をある程度確保しつつ、都合の悪い部分は見せない」という、企業にとって都合のいいバランスなんですよね。
未来は「見えない部分に依存する社会」に
で、こういう流れが進むと、社会全体の透明性はどんどん下がるんじゃないかと思うんですよ。AIがどんなデータを元にしているのか分からないまま、それを前提にした意思決定が増えていくと、「実際のデータはどうなってるの?」って誰も気にしなくなる。 例えば、企業の採用でも「AIが最適な人材を選びます!」みたいなことを言うけど、そのAIが何を基準に判断しているのかはブラックボックス。どんなデータを使ってるのか分からないけど、「AIが言うなら正しいだろう」と思考停止する人が増えるわけです。 これって、「都合よく作られたルールに従う社会」になるってことですよね。要は、「何となく信じる」みたいな状態が当たり前になって、誰もAIの裏側を気にしなくなるんですよ。
「AIの中立性」という幻想
人間はAIに都合よく踊らされる
今のところ「AIは公平で客観的だ」って思ってる人が結構いるんですけど、それって単なる幻想なんですよね。だって、AIって結局、人間が用意したデータを元に動いてるんで。 例えば、企業がAIを使って「優秀な社員」を選別するとして、その基準が過去のデータを元に作られたものだとしますよね。でも、その過去のデータ自体が「偏った評価基準」で作られてたら、AIが出す結果も偏るわけですよ。 だから「AIが決めたから正しい」っていう発想は危険で、むしろ「AIを使う人間が、どういう基準で結果を操作できるのか」を考えたほうがいいんじゃないですかね。
オープンソースの理念が薄れていく
で、レッドハットがこういう「現実的な路線」を取るってことは、今後オープンソース全体の流れも「ある程度の透明性があればOK」みたいな方向に行くと思うんですよね。 オープンソースって元々「誰でも中身を見られるし、改良できる」っていうのが強みだったんですけど、AIの場合は「中身を見せると問題がある」っていう言い訳が成立するんですよ。 これが当たり前になると、オープンソースの名のもとに「実質的にクローズドなAI」が増えていくんじゃないですかね。結局、ユーザーは「オープンソースっぽいもの」を使ってるだけで、実際にはブラックボックスの中身を信じるしかなくなると。
社会はどう変わるのか?
情報の非対称性が加速する
AIがどんどん普及していくと、「情報を持ってる人」と「持ってない人」の差がさらに広がるんですよね。 例えば、企業が自社のAIを使って市場分析をするとしますよね。でも、そのAIがどんなデータを使ってどんなロジックで動いているのかは、企業側しか知らないわけです。 で、ユーザーは「AIの分析結果だから正しい」と思い込む。結果として、AIを使っている側が意図的に情報を操作しても、それに気づかない人が増えていくんじゃないですかね。 これが進むと、AIを開発・運用できる企業や政府が圧倒的に有利な立場になって、一般の人は「AIの結果をただ受け入れるだけ」みたいな社会になる可能性が高いと。
AIの偏見が社会のルールを決める
もうひとつ問題なのが、「AIの偏見がそのまま社会のルールになる」ってことですね。 例えば、AIが「成功する起業家の特徴」を分析して、「○○大学出身の人が成功しやすい」とか「特定の経歴の人がリーダー向き」とかいう結果を出すとしますよね。 で、それが「科学的に証明されたデータ」みたいな扱いになって、企業や学校がそれを基準に意思決定をするようになる。でも、そのデータ自体が偏ってる可能性を誰も考えなくなるんですよ。 これ、要は「過去の偏見をそのまま未来に引き継ぐ仕組み」になるわけです。で、問題なのは、その偏見が「AIが決めたから仕方ないよね」という形で受け入れられるようになることなんですよね。
AIが作る未来の社会構造
「データを持つ側」と「持たない側」の格差
今後、AIがさらに進化すると、結局「データを持つ側」と「持たない側」の格差がもっと広がるんですよね。 例えば、企業がAIを活用して顧客の行動を予測するとしますよね。でも、そのデータは企業だけが持っていて、ユーザー側は自分がどう分析されているのか知らないわけです。 これが進むと、「情報を持っている企業や政府」が圧倒的に強くなって、「一般の人はただのデータ供給者」になる可能性が高いんですよ。で、AIが分析した結果を基に、価格設定やサービスの提供が最適化されるわけですけど、それって企業にとって都合がいい方向に最適化されるだけなんですよね。
「人間がAIに合わせる時代」が来る
で、今まではAIが人間の生活を便利にするために作られてたんですけど、これからは「人間のほうがAIに合わせる」みたいな時代になるんじゃないかと。 例えば、AIが「この時間にこの行動を取るのが最も効率的」と判断すると、それに従うのが当たり前になる。企業も「AIの分析ではこうだから」と従業員の働き方を決めるようになると。 要は、「AIの効率」を基準にして人間の行動を決める社会になるんですよね。で、それが進むと、「人間の自由な選択肢」みたいなものがどんどんなくなっていく可能性があると。
透明性のないAIが生み出す問題
誰が責任を取るのか?
AIが社会のルールを決めるようになると、「何か問題が起きたときに誰が責任を取るのか?」っていう問題が出てくるんですよね。 例えば、AIが判断した結果、誰かが不当に評価されたり、差別的な扱いを受けたりしたとしても、「AIが決めたから仕方ない」で済まされる可能性があると。 で、そのAIのアルゴリズムを作ったのは企業や開発者なんですけど、「AIの判断はブラックボックスなので、責任の所在は不明です」みたいな話になると。 つまり、「透明性がないAI」っていうのは、問題が起きたときに責任の所在を曖昧にする仕組みとしても機能しちゃうんですよね。
人間の価値がAIによって決まる
もうひとつ大きな問題は、「AIが人間の価値を決める社会」になる可能性があるってことです。 例えば、AIが「この人は成功する可能性が低い」と判断したら、企業はその人を雇わないかもしれないし、金融機関はローンを通さないかもしれない。 で、その判断基準は企業や開発者が決めたアルゴリズムによるもので、本人がどんな努力をしても覆せないわけです。これ、結局「AIによる身分制度」みたいなものができるって話なんですよね。
未来はどうなるのか?
「AIと共存する人」と「AIに従う人」の二極化
最終的に、社会は「AIを使いこなす人」と「AIの指示に従うだけの人」に分かれるんじゃないかと思うんですよ。 AIを使いこなす人は、自分でデータを分析して、AIの判断の裏側を理解しようとする。でも、大多数の人は「AIが言うならそうなんだろう」と思考停止する方向に行く。 で、この格差が広がると、「AIを支配する側」と「AIに支配される側」が固定化される可能性があると。これは、単純な経済格差よりも深刻な問題になるんじゃないですかね。
「透明性」を求める動きが出るかどうか
で、こういう状況が続くと、さすがに「AIの透明性を高めるべきだ」っていう動きが出るかもしれないですよね。 ただ、それが実現するには「AIの透明性が低いことによって実害を受けた人」が増えないといけないんですよ。でも、企業や政府は「AIの透明性を高めることで自分たちが不利になる」って分かってるんで、よほどのことがない限り動かないと。 つまり、「透明性がないAI」が当たり前になった時点で、それを覆すのはかなり難しくなるってことですね。
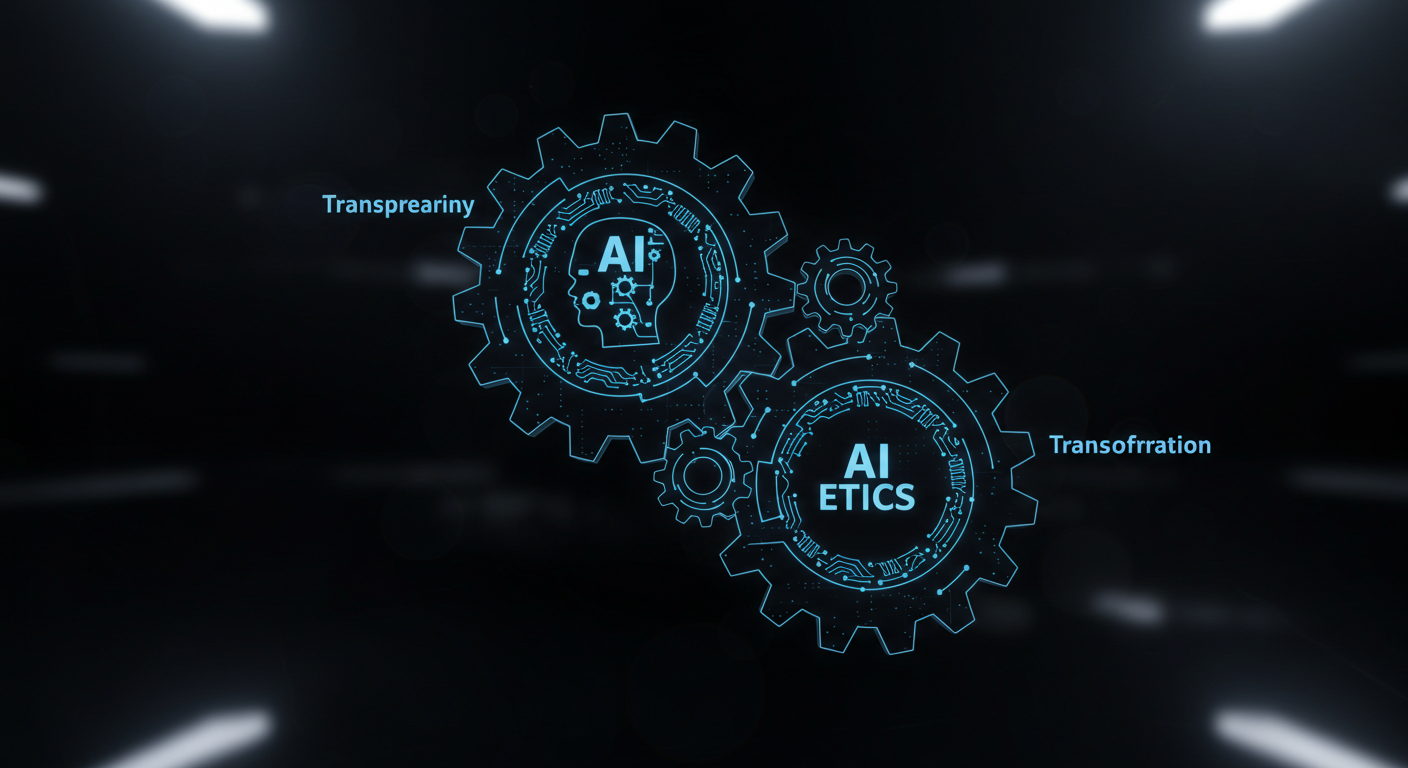


コメント