AIがホワイトカラー業務を自動化するとどうなるのか
AIで単純業務はどんどんなくなる
ホワイトカラーの業務って、結局のところ、決められたルールに沿って処理するものが多いんですよね。例えば、経理の帳簿付けとか、契約書の確認とか、データ分析とか、こういうのってAIがやったほうが正確で速いんすよ。で、こういう仕事って企業からすると「人件費がかかる」ってだけなんで、AIで自動化しちゃえばいいよねって話になるわけです。
で、AIの進化って思ったより速いんで、数年後には「人間がやる必要ある?」って仕事がどんどんなくなると思うんすよね。今は「AIはまだ完璧じゃない」とか言ってる人がいますけど、まぁそれってAIの学習データが増えれば解決する話なんで、企業としては「いずれAIのほうが優秀になる」って見越して、どんどん導入していくと思います。
仕事がなくなる人、スキルアップを求められる人
で、そうなると「仕事がなくなる人」ってのが出てくるんすよね。例えば、企業がAI導入して経理や事務の仕事を削減しましたってなったときに、その仕事をしてた人たちは「新しい仕事を探すか、スキルを身につけるか」みたいな選択肢を迫られるわけです。でも、スキルアップって言っても、全員ができるわけじゃないんすよ。
例えば、40代、50代の人に「今からプログラミング覚えろ」って言っても、そんな簡単にできるわけないですよね。で、企業としても「新しいスキルを身につけた人材を育てるより、最初からスキルのある若手を採用したほうがいいよね」ってなるんで、結局、歳を重ねた人ほど厳しい状況になるわけです。
で、こういう状況が進むと「仕事を失う人が増えて、仕事を得られる人が限られる」って構造になって、結果的に格差が広がるんすよね。今の時代って、もともと「一部の高給取りと、それ以外」みたいな格差が広がってるんですけど、AIが進化することで、その差がさらに大きくなる未来しか見えないんですよ。
企業は得をするが、社会全体はどうなるのか
AIを導入する企業は利益を拡大する
企業からすると、AIを導入すれば「人件費を削減できる」「生産性が上がる」「ミスが減る」っていうメリットがあるんで、使わない理由がないんですよ。特に大企業ほど導入が進むと思います。なぜなら、大企業って大量のデータを持ってるんで、AIを学習させやすいんすよね。
例えば、銀行とか保険会社とかって、過去の取引データとか顧客の情報をめちゃくちゃ持ってるんで、これをAIに学習させれば「この顧客はこういうローンを組みそう」とか「この契約はリスクが高い」とか、AIが判断してくれるようになるわけです。で、人間がやるよりも速くて正確なんで、企業としては「人間を雇うよりAIで済ませよう」ってなるんですよ。
こうなると、大企業はどんどんAIを導入してコストを下げていくんで、結果的に利益が増えるんですよね。でも、その一方で、人間の仕事は減るんで、社会全体としては「AIが進化すればするほど、仕事を失う人が増える」って構造になるわけです。
ベーシックインカムの議論が進むかもしれない
で、こういう流れが続くと、「そもそも仕事がない人が増える」って問題が出てくるんすよね。で、そうなると「働かなくても最低限の生活ができる仕組みが必要だよね」って話になって、ベーシックインカムの議論が進む可能性があると思います。
今の日本って、生活保護とか年金とか、いろんな社会保障制度があるんですけど、AIが進化して仕事がなくなると、「そもそも仕事をしたくてもできない人」が増えるわけですよね。そうなると、「この人たちをどうやって支えるのか」って議論が出てきて、最終的に「働かなくても最低限の収入を保証する仕組みを作るしかないよね」って流れになるかもしれないんすよ。
ただ、日本って「働かざる者食うべからず」みたいな価値観が根強いんで、ベーシックインカム導入にはめちゃくちゃ時間がかかると思います。でも、AIの進化が進んで「マジで仕事がない人が増えた」って状況になれば、政府としても何かしら対応せざるを得なくなるんじゃないかと。
AIによって変わる社会の価値観と人間の役割
「働くこと=価値がある」の考え方が変わる
今の社会って、「働いてお金を稼ぐことが正しい」みたいな価値観があるんすよね。でも、AIがどんどん進化して仕事を奪っていくと、「働かなくてもいい人」が増えるわけですよ。そうなると、「じゃあ、何のために生きるの?」って話になってくると思うんすよね。
例えば、今の日本では「会社員として働くことが安定した人生」みたいな考え方が強いですけど、AIが主流になると、「会社に所属して働く」というモデル自体が崩れてくる可能性があるんですよ。で、そうなると「人間は何をするべきなのか?」みたいな哲学的な問いが生まれると思うんすよね。
仕事を失った人が向かう先は「趣味」か「創造性」
で、AIが仕事を奪うと、仕事を失った人たちは何をするのか?って話になるわけです。で、多分なんですけど、人間がやるべきことって「AIができないこと」になると思うんですよね。で、それって何かっていうと、創造的な仕事とか、芸術とか、人と関わる仕事なんですよ。
例えば、AIがどんなに優秀になっても「人間の感情を100%理解する」ってのは難しいと思うんすよね。だから、カウンセリングとか、教育とか、芸術とか、そういう仕事は残る可能性が高いと思います。ただ、それって全員ができるわけじゃないんで、「AIが奪う仕事」と「人間にしかできない仕事」の格差はさらに広がると思います。
で、それ以外の人はどうなるかっていうと、「趣味で生きる」って方向に行く可能性があるんですよ。例えば、今の時代でも「ゲーム実況で稼ぐ」とか「YouTubeで趣味を仕事にする」とか、そういう流れがあるじゃないですか。AI時代になると、こういう「好きなことをやって生きる」ってスタイルがさらに広がるかもしれないです。
国家の役割と社会の再設計
税制が変わる可能性がある
で、ここまでの話をまとめると、「AIが仕事を奪う→人間の仕事が減る→働かない人が増える→格差が広がる」って流れになるんすよね。で、この問題を解決するために、政府はどうするのか?って話になると思います。
で、多分なんですけど、税制が変わると思うんですよね。今の税制って、基本的に「人が働いて得た所得に税金をかける」仕組みなんですけど、AIが主流になると、「そもそも人が働かなくなる」わけです。そうなると、所得税じゃなくて、「AIを使って稼ぐ企業に高い税金を課す」とか、「AIによる生産の一部を社会保障に回す」とか、そういう仕組みが必要になると思います。
例えば、AIを使って莫大な利益を上げる企業が増えたら、その企業から特別な税を取って、それを国民に配るみたいな仕組みが出てくるかもしれません。そうしないと、「一部のAI企業だけが富を独占して、その他の人は貧しくなる」って構造になっちゃうんで、政府としても何かしら対策を取らざるを得なくなると思うんすよね。
教育のあり方が根本的に変わる
で、もう一つ重要なのが、教育の問題なんですよ。今の教育って、基本的に「決められたことを覚えて、正解を出す」って仕組みじゃないですか。でも、AIがいると、こういう「正解を出す仕事」は全部AIがやることになるんで、人間がやる意味がなくなるんですよね。
そうなると、「じゃあ、これからの教育って何を教えるべきなの?」って話になると思うんすよ。で、多分なんですけど、「創造力」とか「問題解決力」とか、そういう「AIにはできない能力」を伸ばす方向に行くと思います。
例えば、プログラミングを学ぶとか、デザインを学ぶとか、起業のスキルを学ぶとか、そういう「個人で価値を生み出せる能力」が重要になるんすよね。で、こういう教育ができる国と、できない国で、将来的に大きな差がつくと思います。
未来の社会はどう変わるのか
AIに支配される社会になるのか
で、最終的な話として、「AIが進化しすぎると、人間はどうなるのか?」って問題があるんですよね。で、これって結構怖い話で、「AIが社会のすべてを管理する未来」もあり得るんですよ。
例えば、AIが経済の仕組みを完全に管理すると、「誰がどれくらいの収入を得るべきか」とか、「どの企業が成長するべきか」とか、そういうことをAIが決める社会になるかもしれないんですよね。で、そうなると、人間が自分で考える余地がどんどん減って、「AIに管理される社会」になっていく可能性があるんですよ。
で、こうなると、極端な話、「AIが支配するディストピア」みたいな世界もあり得るんですけど、それを防ぐには、「AIを使う側のルール作り」がめちゃくちゃ重要になると思うんすよね。
人間はAIと共存する道を選ぶしかない
で、結論としては、「AIをどう使うかを決めるのは人間」ってことなんですよ。AIが進化して仕事がなくなるのは避けられないんで、「その未来をどうやって活用するか」って考え方が大事なんすよね。
例えば、「AIを使って新しい仕事を生み出す」とか、「AIを活用して人間がより創造的なことに集中できるようにする」とか、そういう方向に持っていくのがベストだと思います。ただ、それができるかどうかは、国の政策とか、企業の動きとか、人々の意識次第なんで、うまくいくかどうかはわからないんすよね。
でも、少なくとも「AIが進化するから、全部任せればいい」って考え方は危険で、「どうやって共存するか」を考えないと、気づいたら「AIに支配される社会」になってる可能性があるんで、そこは注意が必要かなと思います。
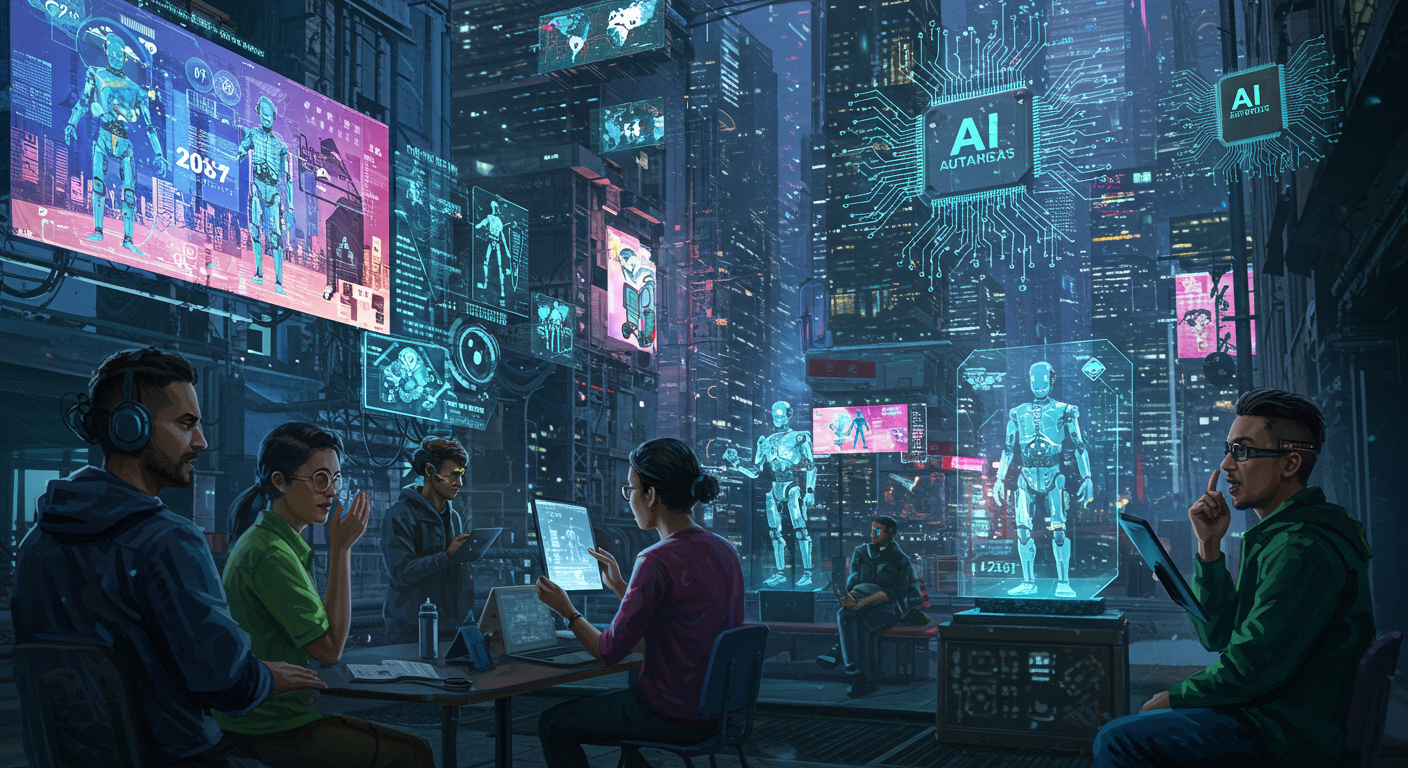


コメント