AI適応格差がもたらす未来
AIを使えない人は淘汰されるのか
要は、KDDIの髙橋社長が「AIを使えない人は放っておけ」と言ったわけですけど、これは別に冷たい話じゃなくて、単純に効率の問題なんですよね。で、これからの社会ではAIを使いこなせる人と使えない人で格差が広がるのは確実です。だから、AIを活用できない人は仕事の生産性が低くなって、給料も上がらずに苦しくなっていくと。結局、企業としては生産性の低い人よりもAIをうまく使える人を優遇するのは当然なので、そういう人が淘汰される未来になるわけです。 で、これを「差別だ」とか言う人が出てくるかもしれないんですけど、資本主義の世界では生産性が低い人は評価されないのが当たり前なんですよね。例えば、昔はソロバンで計算してた人が電卓に負けたし、電卓を使ってた人はエクセルに負けた。で、今度はエクセルを使ってた人がAIに負けるっていうだけの話です。つまり、技術の進歩で適応できない人が淘汰されるのは歴史的に見ても自然な流れなんですよね。
企業の採用基準が大きく変わる
今までの採用って、学歴とか資格とかで判断されることが多かったんですけど、これからは「AIをどれだけ使いこなせるか」で決まる時代になると思うんですよ。要は、学歴が高くてもAIを使えない人よりも、高卒でもAIを駆使して仕事を効率化できる人のほうが評価されると。 例えば、今までは資料作りが上手いとか、データ分析が得意とかが評価されてたんですけど、これからは「AIを使って5分で済ませる能力」のほうが重要になるわけです。だから、「仕事が速い=優秀」っていう評価基準になって、時間をかけて頑張る人ほど評価されにくくなる未来が来ると思うんですよね。 で、これに適応できない人は「仕事が取れない」「昇進できない」「給料が上がらない」っていう悪循環に陥ると。結局、「AIができることを自分でやるのは無駄」っていう意識がないと、どんどん取り残されるんですよね。
AIを使う人と使わない人の収入格差
今後は、AIをうまく活用する人とそうでない人の収入格差がどんどん広がると思うんですよ。例えば、AIを駆使すれば1日8時間働かなくても、2時間くらいで同じ仕事ができるようになる。で、余った時間で別の仕事をしたり、副業をしたりして収入を増やせるわけです。 でも、AIを使わない人は今まで通りのやり方で仕事をするので、時間がかかるし、結果的に生産性も低くなる。だから、同じ仕事をしてても、AIを活用する人としない人で年収の差がどんどん開いていく未来になるんですよね。 特にフリーランスとか個人事業主は、AIをどれだけ使えるかで収入が大きく変わると思うんですよ。例えば、ライターならAIで文章を作成して時短できるし、デザイナーならAIで画像を生成して作業を効率化できる。でも、それをやらない人は「時間をかけて丁寧に作ったのに報酬が低い」とか文句を言う未来が見えるんですよね。
労働時間が減る未来は来るのか
で、「AIが仕事を効率化してくれるなら、労働時間が減るんじゃないか?」って思う人もいると思うんですけど、実際は逆で「成果を出せる人はもっと働いて収入を増やす」っていう流れになると思うんですよね。要は、AIを活用すればするほど、短時間で稼げるので、労働時間が減るというより「もっと稼ぐために働く人が増える」っていう未来になると。 で、問題なのは「AIを使わない人だけが今までと同じ時間働いて、しかも給料が増えない」っていう状況になることですよね。つまり、「AIを使う人はどんどん収入を増やすけど、AIを使わない人は労働時間は同じで、収入も増えない」っていう格差社会が加速すると。 これが進むと、「もうAIなしで生きるのは無理」っていう社会になるわけですよ。例えば、昔はスマホがなくても生きていけたけど、今はスマホがないと仕事もプライベートも不便すぎるじゃないですか。それと同じで、AIを使わないと仕事にならない時代が来ると。
AIが人間の仕事を奪う未来
で、ここからさらに未来を考えると、AIが人間の仕事を奪うのは確実なんですよね。例えば、今まで「人間にしかできない」と言われてた仕事も、AIがどんどんこなせるようになってる。 例えば、接客業とかもAIチャットボットが対応するようになって、問い合わせ対応は全部AIに任せるとか、データ分析もAIがやるとか、どんどん自動化されると。で、人間の仕事が減ると、当然「じゃあ働かなくてもいい社会になるのか?」っていう話になるんですけど、実際は「仕事がなくなる人と、AIを使いこなして仕事を増やす人」に分かれる未来になると思うんですよ。 要は、AIを使える人は仕事を効率化してどんどん稼ぐけど、AIを使えない人は「仕事がない」って嘆く未来になると。で、こういう人たちは「AIのせいで仕事を失った」とか文句を言うかもしれないんですけど、結局それって「技術の進歩に適応できなかっただけ」なんですよね。 だから、AIが発展すればするほど、「AIを活用できる人」と「AIに仕事を奪われる人」の格差がどんどん広がる未来になると。
AIが変える社会構造と人間の価値
「仕事を失った人」の受け皿はあるのか
で、AIが仕事を奪うのが確実だとして、「じゃあ仕事を失った人はどうするの?」って話なんですけど、結局、受け皿は限られると思うんですよね。要は、新しい仕事が生まれるとしても、AIを使いこなせる人しか雇われないわけで、AIを使えない人は「簡単な単純作業」か「人手が足りない分野」くらいしか仕事がなくなると。 例えば、介護とか清掃とかの仕事はまだ人間が必要かもしれないですけど、これもロボットやAIで徐々に置き換わっていく未来が見えてるわけですよ。で、そうなると、仕事を失った人は「AIにできない仕事をやる」か「低賃金の仕事に流れる」しかなくなると。 で、「それって社会的に問題なんじゃない?」っていう話になるかもしれないですけど、要は「適応できない人のために社会がどこまで面倒を見るのか」っていう問題になるんですよね。
ベーシックインカムは導入されるのか
で、AIが発展すると、「人間が働かなくてもいい社会を作るべきじゃないか?」っていう話が出てくるわけです。で、その解決策としてベーシックインカムがよく議論されるんですけど、これは国によって対応が分かれると思うんですよね。 要は、社会全体で「働かなくても最低限の生活ができる仕組みを作るかどうか」っていう話なんですけど、例えばフィンランドとかの北欧諸国はそういう方向に進むかもしれないと。でも、日本みたいな国は「とりあえず自己責任でどうにかしてください」ってなる可能性が高いわけです。 で、これがどうなるかっていうと、結局「ベーシックインカムがある国」と「ない国」で、貧困層の格差がさらに広がる未来になると。つまり、AIによって仕事を失った人が多い国ほど、政府が対策を取らないと社会不安が大きくなるっていう話になるんですよね。
人間の価値はどこにあるのか
で、AIがどんどん発展して、仕事を奪われる人が増えたとして、「じゃあ人間の価値って何なの?」っていう話になるわけです。で、結局、AIができることが増えれば増えるほど、「人間にしかできないこと」が求められるようになると。 例えば、クリエイティブな仕事とか、人間関係を作る仕事とかは、AIには完全には置き換えられないと言われてるんですけど、実際にはこれも徐々にAIが進出してくるんですよね。で、最終的には「AIにできない、人間だけが持っている能力とは何か?」っていうのが問われる時代になると。 で、それって何かっていうと、「共感」とか「感情」とか、そういう部分なんですよね。要は、「人間同士のつながり」とか「感情を理解する力」とか、そういうものが価値になる時代が来ると。だから、「AIにはできないことをやる人」が評価される社会になるんじゃないかと思うんですよね。
「人間は暇になる」という未来は来るのか
で、AIが発展して、仕事が減って、労働時間も短くなったら、「人間は暇になるのか?」っていう話なんですけど、これも結局、人によると思うんですよね。 要は、「時間ができたら何をするか?」っていうのが大事で、AIを活用して新しいことをやる人もいれば、何もしないで時間を浪費する人もいると。で、これが進むと、「暇を持て余す人」と「暇を有効活用する人」に分かれる未来になると。 例えば、昔は仕事が忙しくて趣味を楽しむ時間がなかった人が、AIのおかげで時間ができて新しいことを始めるかもしれないと。でも、一方で、「仕事がないから何もやることがない」とか「やることがなくてダラダラする」っていう人も増えるわけですよ。で、こういう人たちは「社会から取り残された」とか「つまらない」とか文句を言う未来が見えるんですよね。
AIが作る「新しい価値観」
で、最終的にAIが発展すると、人間の価値観も変わると思うんですよ。要は、「仕事がすべてじゃない」とか、「生産性だけが重要じゃない」とか、そういう考え方が広がると。 例えば、今までは「長時間働くことが美徳」とか「努力すれば報われる」とか言われてたんですけど、AIの時代になると「いかに効率よく楽をするか」っていうのが重要になると。で、そうなると、今までの「努力」とか「根性」とかの価値観が変わる未来になるんですよね。 だから、「楽をするのが悪いことじゃない」とか、「無駄な努力をしないことが正しい」とか、そういう考え方が主流になっていくと思うんですよ。で、それが社会全体に広がると、「仕事=人生」っていう価値観がなくなって、「人生を楽しむことが大事」っていう風に変わっていくんじゃないかと思うんですよね。
まとめ:AI時代に生き残るために
で、結局、これからの社会で生き残るためには「AIを活用できるかどうか」が鍵になるわけです。だから、「AIに仕事を奪われる」っていう発想じゃなくて、「AIを使ってどうやって生きていくか?」を考えたほうがいいと。 で、そのためには、「AIができること」と「人間にしかできないこと」をちゃんと理解して、自分がどこで価値を出せるかを考えるのが大事なんですよね。だから、「AIがあるからこそ、人間ができることをやる」っていう視点を持つのが重要になると。 結局、AIの進化によって社会は大きく変わるわけですけど、それに適応できるかどうかで、未来が大きく変わるっていう話なんですよね。
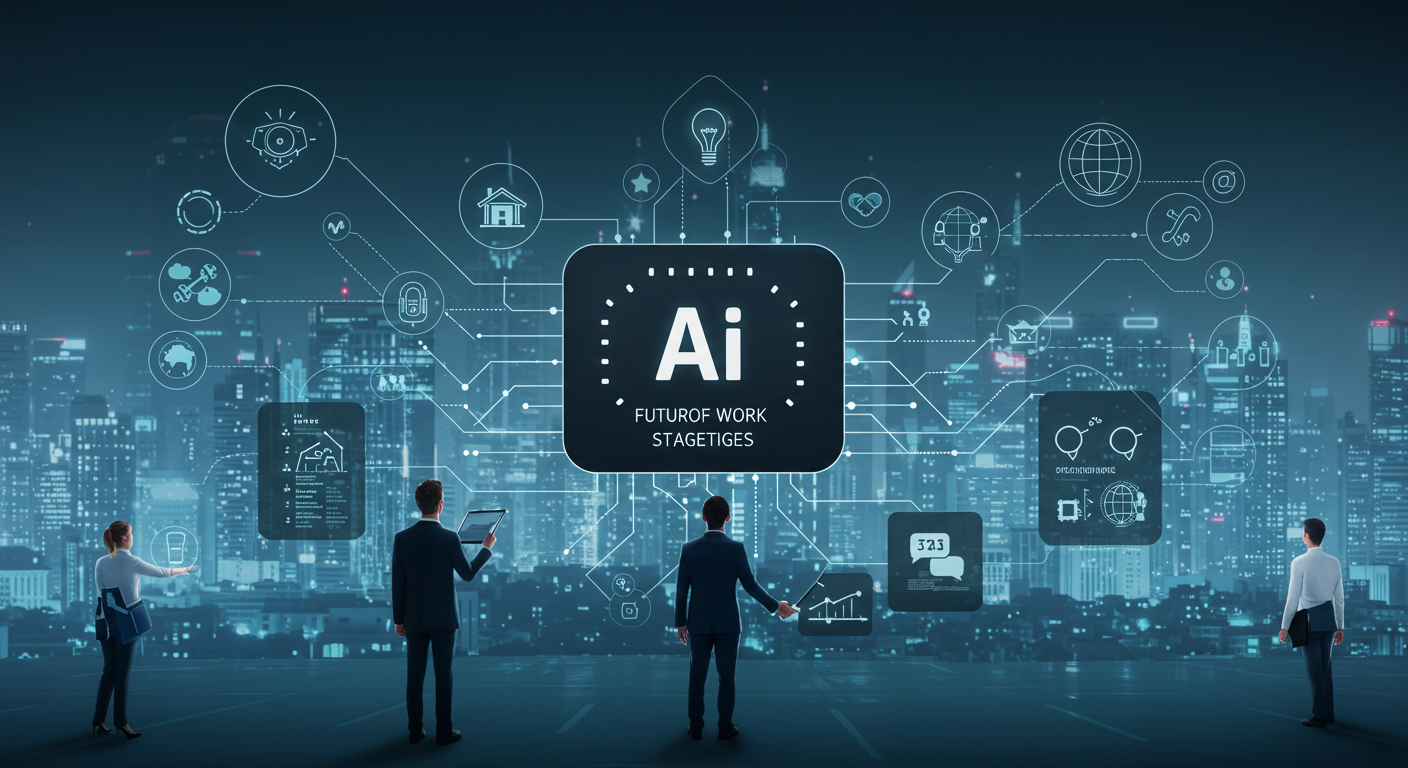


コメント