AI職種の高年収化がもたらす未来
スキル格差による経済の二極化
要は、AI関連の職種が年収1500万円を超えるって話なんですけど、これって結局「学び続ける人」と「学ばない人」の格差がさらに広がるだけなんですよね。 今でもITスキルがある人とない人で収入格差はあるわけですけど、AIが主流になれば、この差がさらに拡大するわけです。 AI関連の職業って、機械学習エンジニアとかデータサイエンティストみたいに、高度な数学やプログラミングスキルが必要なわけです。で、こういう分野って、興味がある人は勝手に学び続けるけど、興味がない人は全く手を出さないんですよね。 つまり、努力する人はどんどん高収入になって、そうじゃない人はAIに仕事を奪われる側になる。だから、将来的には「AIを使いこなして稼ぐ層」と「AIに使われる層」に二極化する未来が来るんじゃないですかね。
AIの普及で「普通の仕事」がなくなる
で、AI技術が発展するとどうなるかっていうと、単純作業とか、ある程度パターン化できる仕事はAIに置き換えられるんですよ。 例えば、今までは「データを集めてまとめる仕事」とか「簡単なプログラムを書く仕事」でもお金をもらえたわけですけど、今後はAIがやるようになるので、人間がやる必要がなくなるわけです。 だから、今の「普通の仕事」っていう概念がなくなる可能性があるんですよね。普通に会社に行って、言われたことをやっていれば給料がもらえる、みたいな働き方がどんどん減っていくわけです。 結果的に、AIをうまく活用できる人や、自分で新しい仕事を生み出せる人しか生き残れない社会になっていくんじゃないですかね。
学ばない人はどこに行くのか
単純労働の価値はさらに下がる
結局、スキルを身につけない人はどうなるかっていうと、単純労働しかできなくなるんですよね。 で、その単純労働の価値はどんどん下がるわけです。例えば、今でもコンビニのレジ打ちとか、工場のライン作業みたいな仕事は自動化が進んでいるわけですけど、AIの進化によってさらに加速する。 そうなると、単純労働しかできない人の仕事がどんどんなくなって、最終的には「AIよりも安く働ける人」しか雇われなくなるんじゃないですかね。 結局、そういう仕事はどんどん低賃金化していって、貧困層の拡大につながる未来が見えてくるわけです。
ベーシックインカムが現実になる?
で、仕事がどんどんAIに奪われると、最終的にどうなるかっていうと、「そもそも働く人がいらなくなる」っていう社会になる可能性があるんですよ。 そうなると、働ける人は限られてくるし、働かなくても生きていける仕組みを作らないと、社会が崩壊するわけです。 で、そうなると出てくるのが「ベーシックインカム」の話ですね。要は、最低限の生活費を政府が保証する仕組みを作らないと、多くの人が食っていけなくなるって話です。 今までは「働かないと食っていけない」っていう社会だったわけですけど、AIが普及すればするほど、「働かなくても生きていける社会」を作らざるを得なくなるわけです。 ただ、ベーシックインカムが導入されたとしても、それで満足する人と、それでも自分で稼ぐ人にまた分かれるわけですよね。 つまり、どっちにしろ「稼ぐ人」と「稼がない人」の格差はなくならないって話です。
AI時代の働き方と価値観の変化
「会社員」という概念が崩れる
要は、AIが発展してくると、会社という組織に属して働く必要がなくなる人が増えるわけです。 今までは「安定した給料をもらうために会社員になる」っていう選択肢が普通だったんですけど、AIが普及すれば、個人で稼ぐハードルがどんどん下がっていくんですよね。 例えば、AIを活用すれば、一人でできる仕事の範囲が広がるので、フリーランスや個人事業主の数が増えていく。 会社に属して同じことをやるよりも、AIを使って効率的に稼げるなら、わざわざ会社に入る必要がないわけです。 そうなると、企業に依存せず、自分のスキルで生きていく人が増えていく未来が見えてくるんじゃないですかね。
雇用の概念が変わる
で、企業側としても、AIを活用することで「そもそも社員を雇う必要があるのか?」っていう話になるわけです。 AIが業務を効率化できるなら、わざわざ人間を正社員として抱えるよりも、プロジェクトごとに必要な人を短期間で雇うほうが合理的ですよね。 つまり、「終身雇用」とか「正社員」みたいな概念がどんどん薄れていって、仕事ごとに契約する「ギグワーカー」の働き方が主流になっていく可能性が高いんじゃないですかね。 結局、企業側も「スキルのある人に必要なときだけ仕事を頼む」っていうスタイルに変わっていくので、「会社にしがみつく」みたいな働き方がどんどん厳しくなる未来が来るわけです。
社会構造の変化とAI格差
「働く意味」が問われる時代
AIが進化していくと、「そもそも人間は何のために働くのか?」っていう根本的な問題に直面するわけです。 今までは「生活のために働く」っていうのが当たり前だったんですけど、AIによって労働の必要性が減ってくると、「じゃあ何のために生きるの?」っていう話になるんですよね。 一部の人は「好きなことを仕事にする」っていう方向に進むかもしれませんけど、多くの人は「仕事がない=自分の価値がない」みたいな状況になって、精神的に病む可能性もあるわけです。 要は、「働くこと=自己肯定感」になってる人が多いので、AIに仕事を奪われると、自分の存在意義を見失う人が増えてくるんじゃないですかね。
「AIエリート」と「その他大勢」の格差
で、AIを活用できる一部のエリート層はどんどん豊かになっていくわけですけど、それ以外の大多数の人はどんどん取り残されていくわけです。 結局、AIを活用して大きな収入を得られる人と、AIに仕事を奪われて何もできなくなる人の二極化が進んで、「持つ者」と「持たざる者」の格差が一層広がる未来が見えてくるわけです。 こういう格差が広がると、社会不安が増えて、治安が悪化したり、政治的な対立が激化したりする可能性もありますよね。
AI社会で生き残るために必要なこと
「使う側」に回らないと生き残れない
結局、AIが発展していく未来で生き残るためには、「AIに使われる側」ではなく、「AIを使う側」に回らないと厳しいわけです。 要は、AIをただの便利なツールとして活用できる人と、AIに仕事を奪われるだけの人に分かれるんですよね。 だから、今後の時代を生き抜くためには、「どうやってAIを活用するか?」っていう視点を持つことがめちゃくちゃ重要になってくるわけです。
「学び続ける力」が鍵になる
で、AI時代の最大の問題は、「今のスキルがずっと通用するわけじゃない」ってことなんですよ。 AI技術はどんどん進化していくので、一度学んだスキルがすぐに陳腐化する可能性があるんですよね。 だから、これからの時代に求められるのは、「学び続ける力」なんですよ。 要は、「今持ってるスキルで食っていく」んじゃなくて、「常に新しいスキルを身につけ続ける」ことが生き残るために必要になるわけです。 結局、「学び続ける人」と「学ばない人」で、収入や生き方の差がどんどん広がっていく未来になるんじゃないですかね。
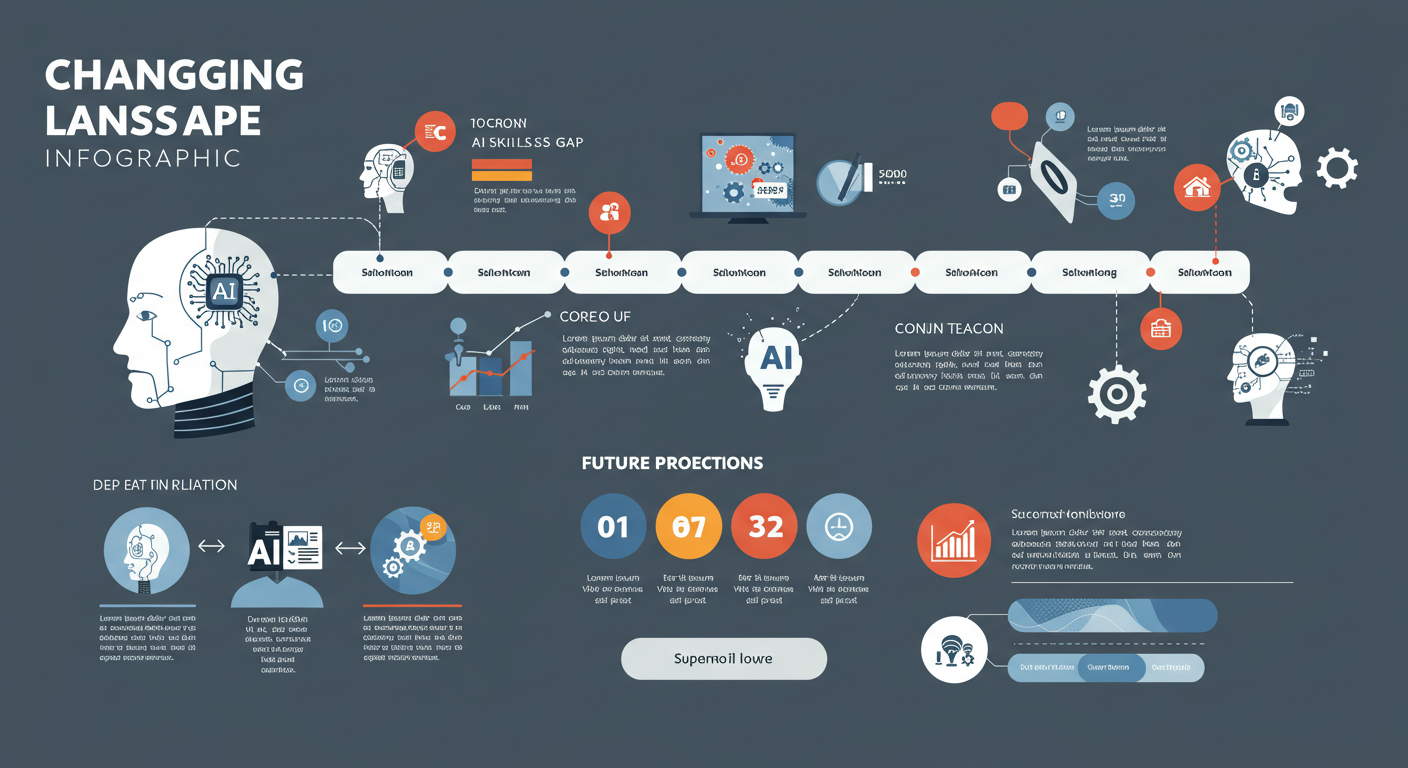


コメント