紙と監視のAI化がもたらす“見えないリストラ”
事務作業がAIで代替されるという現実
要はですね、今回のAI・人工知能EXPOで東芝が出してきたサービスって、結局「人間がやってた面倒な作業を、AIでやっちゃおうぜ」っていう話なんですよね。請求書とか伝票のOCR、映像の解析、文章の要約って、昔から人が目で見て確認してた仕事なわけです。それをAIが一瞬でやっちゃう。
つまり、ホワイトカラーの単純作業ってもうAIで十分だよね、っていう流れが止まらなくなってきてるわけで。これって別に未来の話じゃなくて、今まさに起きてることなんですよ。
で、「便利になったね」って喜ぶ人もいるかもしれないんですけど、裏を返すと、その作業をしてた人の仕事がなくなるってことでもあるんですよね。だから、気づかないうちに人間の仕事がどんどん削られていって、「なんか最近仕事減ったな」って言ってる人は、実はAIに職を奪われてる可能性があるっていう。
“見えない失業”が始まっている
で、こういう変化ってニュースになりにくいんですよ。リストラみたいに「〇人削減しました」とかじゃないから。新しいシステムを導入して、誰かがやってた作業が「自動化された」ってだけ。でも、その裏では「あれ、あの人がやってた業務、もう要らなくね?」ってなって、異動とか退職促されたりするわけです。
これって、僕が勝手に「見えない失業」って呼んでる現象で、要はAIが静かに人間の仕事を奪っていく。でも、その実態が表に出にくい。だから社会全体として「失業率は安定してる」みたいな見せかけが続くわけですよ。でも、実際は人間が仕事で得ていた価値が、AIにスライドしていってるっていう。
この流れ、けっこう怖いですよ。だって、見えないから対策もしづらいし、「自分は関係ない」って思ってるうちに、自分の仕事も対象になってるかもしれないんですよね。
映像解析AIが監視社会を強化する
“見るAI”が社会の目になる
次に、映像解析AIの話なんですけど、これって要は「人間が監視カメラの映像をずっと見るの、非効率だよね」っていう発想なんですよ。で、AIが代わりに見張って、変な動きとか、人数のカウントとか、顔認証までやってくれると。
これ、技術的にはすごいんですけど、冷静に考えると「常に誰かに見られてる社会」になっていくってことでもあるんですよ。つまり、昔は人が数人でやってた警備やモニタリングが、今はAIが24時間365日見てる。
で、そういう環境って、安心感はあるかもしれないけど、同時に自由が制限されていく方向にもつながるわけで。「変な動きをしたら即座に検出される社会」って、ちょっと息苦しくないですか?
“行動のデータ化”が始まる
映像解析AIって、「誰が」「どこで」「何をしたか」っていう行動ログを、全部データにしちゃうんですよ。これってつまり、人の行動履歴がどんどん積み上がっていく世界になる。
で、それが何に使われるかというと、防犯だったり、店舗の導線改善だったり、広告ターゲティングだったりするわけですが、要は「人の行動を商品化する時代」になっていく。
これはちょっと前のネットのCookieと似てて、今は街を歩いてるだけで、自分の動きがビッグデータとして蓄積されていく。で、「あなたの行動パターンから、これ買うでしょ?」って提案が来るようになるわけです。
自然言語処理AIによる“知的作業の外注化”
文章の要約や検索もAI任せに
で、もうひとつ注目したいのが「コメンドリwith生成AI」ってやつなんですけど、これがまた厄介でして。要は、「大量のドキュメントから情報を引っ張って、自然な日本語で要約してくれる」っていうサービスです。
一見、便利そうに見えるんですけど、これもまた“知的作業の外注化”なんですよね。今までは、誰かが資料を読み込んで、要点をまとめて、上司に説明するみたいな仕事があったわけですが、それもAIがやってくれる。
つまり、資料を読んで理解する力とか、要点を抽出する能力って、今後必要なくなる可能性があるわけです。で、それを「便利だな〜」って思ってるうちに、自分の“考える力”が鈍っていくっていう。
プロンプト設計の格差が生まれる
ただし、ここでひとつ重要なのが「プロンプトの設計力」です。要するに、AIに何をどう聞くかっていう能力なんですけど、これって地味に格差を生む要素になると思うんですよ。
同じAIを使ってても、うまく使いこなせる人と、うまく質問できなくて変な回答しか得られない人って、今後どんどん差がついていく。つまり、「AIを使う力」が、これからの“新しい読み書きそろばん”になるわけです。
で、その格差って、学歴とか職種よりも、もっと深刻かもしれないんですよ。だって、「何を聞けば、欲しい情報が出てくるか」って、本質的には“思考力”の問題ですから。
労働の意味が再定義される社会
“働く”が生活のためじゃなくなる?
で、ここからちょっと大きな話になるんですけど、こういうAIの進化って、最終的には「労働の意味って何だっけ?」って話にたどり着くと思うんですよ。つまり、仕事がAIに置き換えられていくなら、人間は何のために働くのか?って話です。
たとえば、AIが請求書も読んでくれるし、監視カメラも見てくれるし、資料も要約してくれるなら、定時でオフィス行って、書類作って、報告して、っていう“普通の仕事”って、どんどん要らなくなるんですよね。
で、そうなると、生活費を稼ぐための労働って、あんまり意味なくなるんですよ。ベーシックインカムみたいな制度が現実になれば、「食っていくために働く」っていう構造自体が崩れるかもしれない。そうなると、人間は「何のために働くか?」っていう問いに直面する。
要は、好きなことを仕事にする時代が来る、って言うと聞こえはいいんですけど、それって同時に「意味のない仕事は淘汰される」って話でもあるので、「何が好きかすらわからない人」は、社会からどんどん取り残されていくんじゃないかなと思うんですよ。
“やりたいことがない人”が一番困る時代
AIが仕事をどんどん奪っていくと、最後に残るのは「人間にしかできないこと」なんですけど、それって、けっきょく“創造性”とか“感情”とか、そういう曖昧な部分になってくるんですよね。
で、「自分には特別なスキルもないし、やりたいこともない」って人が一番困る時代になる。なぜなら、そういう人たちが今までは“普通の仕事”で食えてたのに、その“普通の仕事”が消えていくから。
しかも、自分で考えることが減って、AIが全部やってくれるってことは、余計に「自分は何がしたいのか?」って問いに向き合わざるを得ない。で、そこで空虚さを感じる人って、たぶん増えると思うんですよね。
だから、AIの進化って、「人間の自由を広げる」一方で、「自分で何も決められない人には厳しい時代」を作ってるっていう、ある意味、皮肉な状況でもあるんです。
教育と育成の価値が変わる
“詰め込み型”の教育は役に立たなくなる
あと、教育の分野もけっこう大きく変わると思ってて、これまでの「暗記して知識を詰め込む」っていうスタイルの教育は、ほぼ意味を失っていくと思うんですよ。
だって、AIに聞けば何でも出てくる時代に、「歴史の年号を覚えましょう」とか「英単語100個覚えましょう」って、無駄じゃないですか。むしろ、「その情報をどう使うか」とか、「AIにどう聞けばいいか」っていう“問いの立て方”のほうが、100倍重要になる。
つまり、教育の価値って、「知識を教えること」から「思考を鍛えること」に完全にシフトすると思うんですよ。で、そうなると、先生の役割も変わってくるし、学歴社会の価値も揺らいでくる。
“正解のない問い”に向き合える力が必要
今後必要になるのは、「この問いにはまだ正解がないけど、どう考えればいいかを導ける人」なんですよ。要するに、AIが出せない答えを出せる人。たとえば、「今後の社会はどうなるか」とか、「人間らしさとは何か」とか、そういう漠然とした問いに、自分の視点で向き合える人が評価される時代になる。
で、それって学校で習うことじゃなくて、自分で考えて、自分で仮説立てて、自分で検証して、っていうプロセスなんですよね。だから、今後の教育って、もっと「問いを立てる力」を育てる方向に進まないと、本当に使えない大人ばかり量産しちゃうと思います。
未来に備えて個人がやるべきこと
AIを敵にしない、むしろ“味方にする”
最後に、じゃあ僕ら個人がこの流れにどう向き合えばいいかって話なんですけど、基本的に「AIに仕事を奪われる」とか「AIが怖い」とか言ってる人って、たぶん負ける側の人なんですよ。
要は、AIを敵視するんじゃなくて、味方にする。つまり、AIに何を任せて、自分は何に集中するかっていう、“役割分担”を考えられる人が、これからの社会では強いと思うんですよね。
で、具体的には、AIを使って自分の時間を作るとか、AIと一緒にコンテンツを作るとか、そういう“ハイブリッド人間”になったほうがいい。全部自分でやろうとする人は、どんどん効率で負けるし、全部AIに任せる人は、考える力を失う。だから、その中間を取れる人が生き残る。
“思考力”と“感性”が武器になる
で、結局最後に残るのは「人間らしさ」なんですよね。要するに、論理的に考える力と、共感や感性っていう、人間だけが持ってるスキル。AIがどれだけ進化しても、「人間がどう感じるか」とか、「その表現が心を動かすか」っていう部分は、まだまだ人間の領域です。
だから、「答えがないことに向き合える力」とか、「他人に伝える力」っていうのが、今後めちゃくちゃ重要になる。で、それって、今の教育や会社ではあんまり評価されてこなかった部分だから、逆にチャンスでもあるんですよ。
要は、AIの進化で“思考停止してる人”は淘汰されるけど、“自分で考えて行動できる人”にとっては、むしろチャンスが広がる時代になるんじゃないかなと、僕は思ってます。
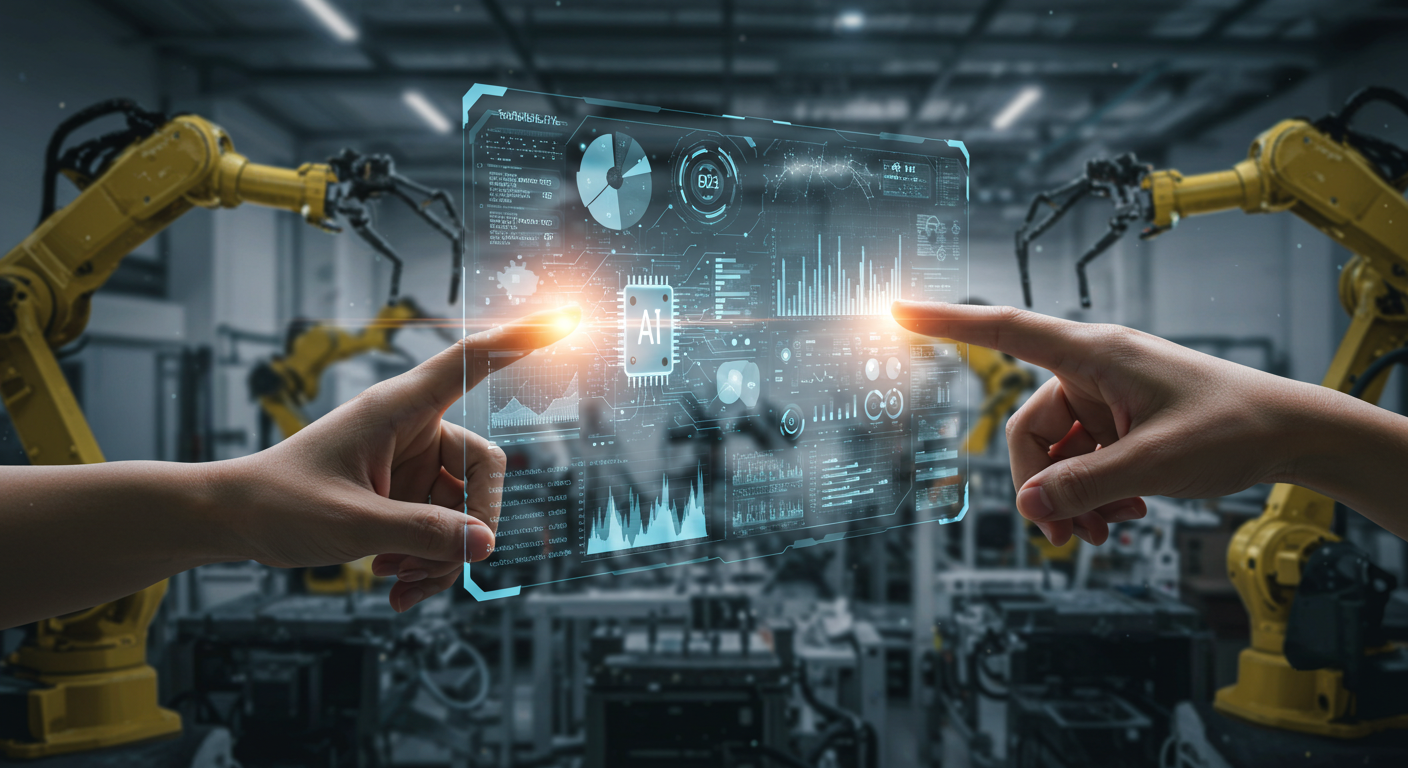


コメント