中国のロボット産業競争が示す未来の生活像
家事をしない時代がやってくる
中国の都市が人型ロボットとエンボディドAIに本気出し始めてるんですよ。特に上海のスタートアップ「Agibot」が開発してる家庭用ロボットなんですけど、これがベッドメイキングしたり、テーブルの掃除したり、洗濯までやってくれると。で、これが本格的に普及し始めたらどうなるかっていうと、「家事をする人」っていう職業や役割自体がなくなる可能性があるんですよね。
今までは「家事は人がやるもんだ」っていう前提で社会が成り立ってたわけですけど、それが根本から変わっちゃう。つまり、専業主婦やパートタイマーの仕事の多くが機械に置き換わってくる。すると「家庭内の役割」っていう概念が変化するので、家族の形や夫婦間の関係にも影響出ますよね。
「誰の役にも立たない人」が増える可能性
で、要は人型ロボットが社会に浸透すると、「役に立つ人」と「役に立たない人」の線引きが今よりも明確になっちゃうんですよ。例えば、今までは「料理上手だから重宝される」とか「掃除が得意だから必要とされる」みたいな人がいたんですけど、それが全部ロボットで代替できるようになったら、そういう人たちの価値が相対的に下がる。
すると「自分が社会の中でどうやって生き残るか」っていう問いに直面する人が増えるんです。だから「何ができるか」より「どんな存在であるか」っていう人格面や創造性、発想力がより重要になってくると思うんですよね。AIとロボットは知識や手作業を代替できますけど、人間にしかできないのは「偶然の発想」や「非合理な判断」だったりするので。
都市の未来はロボット前提で設計される
中国って国として「上からの強制」が効くから、都市設計もロボット前提でどんどん変わっていくと思うんですよ。例えば「エレベーターはロボットがボタン押しやすいように設計する」とか、「キッチンやベッドの高さはロボット基準に合わせる」とか。今の住宅って人間の使いやすさを基準にしてるけど、今後はロボットが活動しやすいように作られるんじゃないかなと。
で、これって結構本質的な話で、「人間が中心の社会」から「ロボットやAIも含めた社会」への移行なんですよね。人間以外の存在が社会のインフラや設計の前提になるっていうのは、今までの文明の歴史においても大きな転換点なわけです。
働く意味が根本から変わる未来
「稼ぐこと」より「存在価値」が問われる
結局、ロボットやAIが労働を代替すると、僕らは「何のために働くのか?」っていう根本的な問いに直面することになるんですよね。今までは「お金を稼ぐために働く」ってのが当たり前だったんですけど、そのモデルが崩れる。なぜかというと、AIとロボットは「24時間働いても疲れない」し、「文句言わない」し、「給料もいらない」わけで、コスパが圧倒的に良い。
なので企業もどんどん人を減らして、ロボットやAIを導入するようになる。すると「人間を雇う理由」が薄れてくるわけです。つまり、会社が人を雇うのは「労働力として使えるから」じゃなくて、「何かしらの創造的価値があるから」とか、「ブランドやファンを持ってるから」みたいな特殊な理由になってくる。
要は、「ただ真面目に働く人」っていうのは、AIとロボットに置き換えられてしまう可能性が高い。逆に「人として面白い」とか、「人に影響を与えられる存在」っていうのが重視されるようになる。これは芸能人やインフルエンサーだけの話じゃなくて、普通の会社員やフリーランスにも関わってくる問題ですね。
教育の中身がガラッと変わる
で、教育も変わらざるを得ないんですよ。今の学校教育って「知識を詰め込む」ことに重きを置いてるんですけど、それってAIに一番得意な分野なんですよね。知識を覚えて、正確に出力するっていうのは、むしろ人間よりAIの方が向いてる。
だからこれからの教育で重要なのは、「何を知ってるか」じゃなくて「どう考えるか」「どう問題を定義するか」っていう部分。あと、「他人とどう協力するか」とか、「相手の感情をどう読み取るか」とか、そういう“人間にしかできない能力”がカリキュラムの中心になると思うんですよ。
さらに言うと、「やりたいことを見つける力」っていうのもすごく重要になってくる。何でもできる世の中になったときに、「自分が何をしたいか」っていう指針がないと、ただの漂流者になっちゃうんで。
社会的インフラの再設計が必要になる
そして、もう一つ大きな変化としては、「インフラの再設計」が求められるってことですね。今の社会制度って、人間が労働してお金を得るっていうモデルがベースになってる。例えば、年金制度もそうだし、健康保険や雇用保険もそう。でも、もし人が働かなくてもよくなる社会が来たら、これらの制度も全部見直さなきゃいけなくなる。
じゃあベーシックインカム導入するのかって話になるんですけど、これも簡単じゃない。財源の問題もあるし、「働かない人に金を配るのか?」っていう反発もある。でも、ロボットやAIが生み出した価値をどう分配するかっていう仕組みを作らないと、不平等がどんどん拡大していくわけですよね。
なので、政治的にも「誰に富を再分配するのか?」っていう論点が今まで以上にシビアになっていくと思います。
ロボットとAIがもたらす新たな社会構造
ロボット中心社会がもたらす格差の再定義
ロボットやAIが生活の多くを担う社会になった場合、「格差」っていう概念自体が変わる可能性があるんですよ。今までは収入とか資産とか、いわゆる「持ってる・持ってない」で上下関係が決まってましたけど、ロボット中心の社会では「人間としての魅力」や「他人に与える影響力」みたいな、より抽象的な価値で格差が生まれるようになると思うんです。
つまり、お金持ちだけど退屈な人よりも、発信力があって周囲を楽しませる人の方が評価される世界。これはSNSでインフルエンサーが活躍してる今の流れと似てますよね。結局、「誰かの時間を奪えるか」「誰かの注意を引きつけられるか」が、新しい格差の軸になる。
で、そうなると「能力のある人」が有利になるというより、「面白い人」「共感される人」「信頼される人」が得をする。つまり、生きづらい人がより生きづらくなる社会にもなりかねないわけで、そこをどうケアしていくかが今後の課題になるんですよ。
「働く意味」が文化に変わる可能性
AIとロボットが労働を代替するって話をすると、「じゃあ人間は何すんの?」って疑問が当然出てくると思うんですけど、僕は「働くこと自体が趣味になる」んじゃないかなと思ってるんですよ。
要は、働くことが「生活のため」じゃなくて「自己表現」とか「楽しみ」の一部になる。今でも、定年後にNPOとかやってるおじいちゃんとかいますよね。あれってお金のためにやってるわけじゃなくて、「何かしら社会と関わっていたい」っていう動機なんです。
だから今後は、「やらなくていいけど、やりたいからやる」っていう働き方が増えると思います。それって文化活動に近いんですよ。芸術とか、趣味の延長線上で「仕事」と「遊び」の境界がどんどんなくなる。そうなると、「働いてる=偉い」って価値観も崩れて、「好きなことをやってる=カッコいい」みたいな方向に変わっていくかもしれないですね。
未来の家族と人間関係の変化
人間同士の関係がより曖昧になる
家事ロボットが普及すると、家の中の“役割”っていう概念が薄れてくるんですよ。これまでの家庭は「夫が稼いで妻が家事をする」みたいな役割分担が暗黙の前提としてありました。でもロボットが家事を全部やってくれるようになると、じゃあ夫婦で何を共有するの?って話になる。
つまり、家事という“協働作業”がなくなることで、人間関係の接着剤みたいなものが一つ消えるわけです。すると、もっと精神的なつながりとか、お互いの価値観への共感みたいな、抽象度の高い関係性が求められる。だから、今よりも「人間同士の相性」がめちゃくちゃ重要になってくると思うんですよ。
要は、便利になった分だけ、感情とか価値観のズレが表面化しやすくなる。なので今後の家族って、「生活の共同体」から「感情の共感体」に変わっていくんじゃないかなと。
子育てにもロボットが関与する時代
で、もう一歩踏み込むと、子育てにもロボットやAIが関わるようになると思うんですよ。既に一部の国では、子どもに絵本を読み聞かせるAIや、発達のサポートをするアプリが普及し始めてますけど、これがさらに進化して、24時間子どもの質問に答えるロボットとか、感情の変化を読み取って適切に対応するAI保育士みたいなものが出てくる可能性は高い。
で、それが便利なのは確かなんですけど、同時に「人間の親が果たしていた役割」ってのも再定義されるわけです。つまり、「子どもの話を聞く」とか「悩みに共感する」っていう行為が、もはや人間である必要がなくなる可能性もある。
そうなると、親が親である理由って何?って話になる。単に「生んだから親」っていう時代は終わって、「どう関わったか」で親としての価値が決まるようになるんじゃないかなと。
人型ロボット時代の倫理と社会的責任
ロボットに権利を与えるか問題
あと、ちょっと先の話になりますけど、AIやロボットがあまりにも人間に似てくると、「これ、モノとして扱っていいの?」って議論が出てくると思うんですよ。特に感情表現が豊かで、人間のように反応するロボットを、単なる道具として使うのは倫理的に問題じゃないの?って話になる。
これってペットの扱いに近いんですよね。昔は犬や猫も道具として扱われてたけど、今は家族の一員として扱われる。それと同じように、人型ロボットも「人格のようなもの」を持ってると認識された時点で、権利や保護が議論されるようになる。
じゃあそのロボットが壊れたときに「殺した」っていう表現になるのか?とか、感情を持つロボットを長時間労働させるのは“虐待”なのか?とか、法的にも倫理的にも新しい領域に突入することになるんですよね。
技術が先行して倫理が追いつかない未来
で、今の技術の進化スピードに対して、倫理や法制度が全然追いついてないってのが現実なんですよ。これまでも、インターネットの匿名性とかSNSの情報拡散でいろいろ問題が起きましたけど、ロボットやAIの進化はそれ以上に複雑で、かつ社会への影響がでかい。
でも、法整備って基本的に「問題が起きてから」じゃないと動かないんですよ。つまり、実際に人型ロボットが虐待された動画が拡散されたり、AIに関する人権訴訟みたいな事件が起きない限り、なかなか社会が本気で議論しようとしない。
だから、これからの社会は「技術に人間が追いつく」っていうより、「人間がどう遅れずに付いていくか」っていう課題に直面するんじゃないかなと。で、その過程で失敗もたくさん起きると思うけど、最終的には「どうすれば人が幸せに生きられるか」って視点で技術を使える社会になればいいなと思ってます。
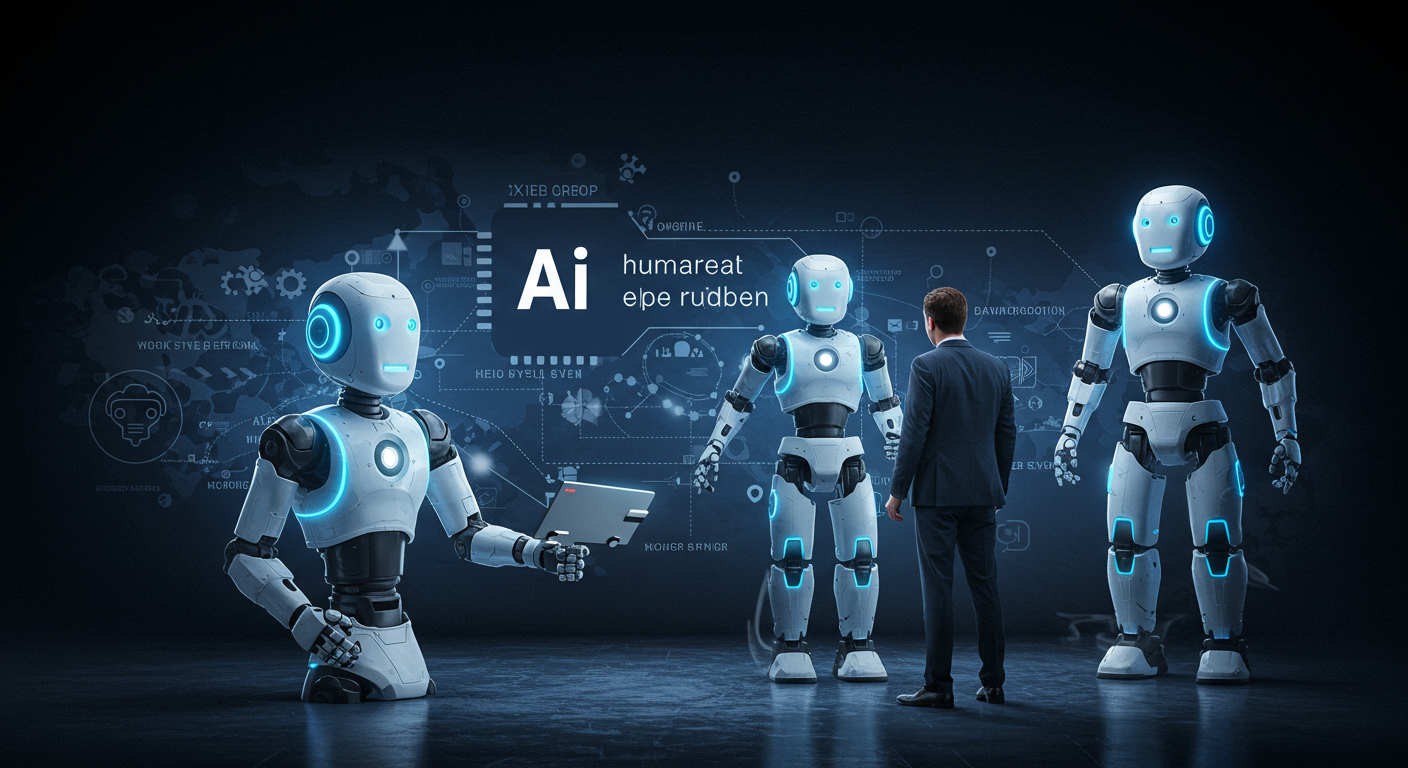


コメント