AIインフラの進化がもたらす社会構造の変化
AIが当たり前のインフラになる未来
要は、AIって昔は一部の企業とか研究者しか触れなかったものだったんですけど、今はクラウドとAPIで誰でも簡単に使える時代になってきてるんですよね。で、これからはその「当たり前に使える」って状態が、さらに強化されていくわけです。
F5のような企業が提供するAIインフラって、裏側でAIの処理を高速化したり、セキュリティを確保したりするためのものなんですけど、それがちゃんと整備されると、ユーザーがAIを使ってることすら意識しない社会になると思うんですよ。
たとえば、スマホで写真を撮ると自動で画像が補正されたり、翻訳されたり、音声がテキストになったりっていうのが、全部AIのおかげなんですけど、誰も「AI使ってる」って意識してないじゃないですか。そういうのがもっと進んで、日常のすべてにAIが入り込んでくると、人の暮らしってかなり変わると思うんです。
中小企業と個人がAIの恩恵を受けられる時代
で、ここからが大事なんですけど、大企業だけがAIを使える時代じゃなくなるんですよ。要は、AIファクトリーみたいな大規模な処理基盤は大企業が持つんだけど、それをAPI経由で中小企業や個人が使えるようになると、格差が縮まるわけです。
昔だったら「資本がないとテクノロジーを使えない」ってのが当たり前だったんですけど、クラウドやAIサービスのおかげで、資本が少ない人でもレベルの高い技術を利用できるようになると。これって社会的にめちゃくちゃ大きな変化なんですよ。
たとえば、地方の農家がAIを使って作物の収穫時期を予測したり、観光業者が多言語AIチャットボットで海外客の対応したりするのが、特別なことじゃなくなる。こういうのが全国レベルで当たり前になると、地方と都市の情報格差も縮まっていくんですよね。
AIとセキュリティが統合される未来の働き方
セキュリティと自動化が人間のミスを補完する
AIって便利なんですけど、便利なものほどセキュリティの穴も大きくなるんですよ。で、F5みたいな会社がAIとセキュリティを一体化させて提供するってのは、要は「AIを使っても安全ですよ」って状態を作るってことなんです。
この「安全なAIの利用」ができるようになると、企業も個人ももっと大胆にAIを使えるようになります。たとえば、社内の業務を全部AIに任せるような会社が出てきても、情報漏えいの心配が減るから経営者の心理的ハードルが下がるんですよ。
で、そういう状態になると何が起きるかっていうと、「人間の役割が変わる」んですよね。いままでは人がルールを作って、それを従業員が守るって形だったんですけど、これからはAIがルールを判断して、人はそれを管理する側になると。
つまり、働き方そのものが「作業する人間」から「判断しないで管理する人間」になっていく。要は、感情や判断に頼らずに、AIの示す最適解を見守るって仕事が増えるんですよ。
AIゲートウェイが業務を標準化し、属人性を排除する
F5が出してる「AI Gateway」ってサービスも面白くて、これってAIを通じた業務フローを管理する仕組みなんですけど、要はどのAIが何をやったのか全部見える化されるんですよ。
そうなると、「誰がどの判断をしたか分からない」みたいな属人的な問題がなくなる。逆に言うと、「誰がやっても同じ結果が出る」って状態が作れるから、会社としての安定性が増すんですよ。
で、こうなると何が起きるかっていうと、「人を採用する理由が変わる」んですよね。いままではスキルとか経験が評価されてたけど、これからは「AIをうまく使えるか」「標準フローに従えるか」ってのが重要になる。要は、優秀な人じゃなくて、素直にシステムに乗れる人の方が重宝される社会になるんです。
そうなると、過去の経歴とか学歴よりも、「この人はAIと共存できるかどうか」ってことが問われるようになる。そういう意味で、教育のあり方も変わってくるんじゃないかなと。
AIがもたらす社会構造の再編
職業の意味が再定義される未来
で、AIが社会に深く浸透すると、「そもそも仕事ってなんのためにあるの?」って話になると思うんですよね。つまり、AIが大抵のことをやってくれるようになると、人がやるべき仕事ってすごく限られてくるんです。クリエイティブとか、人間関係に基づいた交渉とか、直感的な判断が求められる領域以外は、どんどんAIに置き換えられていく。
だから、将来的には「仕事ができる人」が偉いんじゃなくて、「AIがやらない仕事を見つけられる人」が重宝される時代になるんですよ。要は、みんなが「自分にしかできない仕事」を探し始めるってことです。
たとえば、感情を扱う介護職とか、創造性が要求されるアート系の仕事とか、そういう領域の価値が見直されるようになるんですよね。逆に、事務作業とか経理とか、ルールに従ってやる仕事はどんどんAIに吸収されていく。で、そこに人を割くのは非効率だから、企業もそういう人材を採用しなくなる。
組織の形も変わる
AIの普及によって「組織」そのものの形も変わっていくと思うんですよ。今って会社ってのは人の集合体として存在してるんですけど、将来的には「AI+人」って構成になって、むしろAIが中核になって人が補助的な役割を担うって構図になる。
たとえば、AIが指示を出して人がその通りに動くみたいな逆転現象が普通になってくると思います。で、それに適応できる人だけが組織の中で価値を持つようになる。つまり、AIの出した指示に対して「これは違う」って言う人より、「じゃあ、どう実行するか?」を考えられる人の方が評価される。
で、そういう社会になると、「上司が正しいとは限らない」ってのが前提になる。AIの方が正しい判断をするケースが多いなら、上司の役割も変わってくるわけで。つまり、組織内のヒエラルキーが「年功序列」から「AIとどう向き合えるか」で決まるようになる。
個人の生き方に及ぼすインパクト
働かない選択肢が現実になる
で、個人レベルの話をすると、AIが多くの仕事を代替するようになると、「働かなくてもいい人」が出てくるんですよね。ベーシックインカムみたいな制度も現実味を帯びてくるし、副業とか趣味をベースにした生活も増える。
要は、「何のために働くか?」って問いが、いまよりももっと個人に突きつけられるようになる。で、それに対して「生きがいのため」とか「社会参加のため」って答える人が増えると思うんですよ。金のために働くって時代が終わって、「やりたいことに時間を使う」って価値観が主流になる。
これは人によってはすごく楽になると思うし、逆に「何をしていいかわからない」って人には辛いかもしれない。でも、それってある意味で「人間の本質」に近づくことでもあるんですよね。
教育の方向性も変わる
で、この流れにあわせて教育も変わるはずなんですよ。これまでの学校教育って「決まった正解を速く正確に出す」ことを重視してきたわけですけど、それってAIが最も得意なことなんですよね。つまり、人間がやる必要ない。
だから、これからの教育ってのは「AIにはできないことをどう育てるか」って方向にシフトしていくはずです。たとえば、自分の意見を持つ力とか、他人との共感力とか、未知の問題に対処する柔軟性とか、そういう部分が評価されるようになる。
で、これって本当に根本から教育の形を変える話で、要は「テストで点を取る人」じゃなくて、「変化に適応できる人」を育てる方向に舵を切ることになる。今の受験制度や評価システムが崩れていくのは、時間の問題だと思います。
結局、AIに使われる人になるか、使う人になるか
結局のところ、AIが普及した未来で人間が問われるのは「AIを使う側に回れるかどうか」なんですよね。AIに使われる側、つまり指示を受けて動くだけの人になると、仕事はどんどん奪われていく。でも、AIをうまく使って新しい価値を作る側に回れれば、むしろチャンスは増える。
要は、AIが奪うのは「頭を使わない仕事」であって、「頭を使って創造する仕事」は増えるって話なんです。で、その変化に適応できるかどうかが、これからの分かれ道になる。
今までの常識に縛られて「AIは危ない」とか「信用できない」って言ってる人たちは、多分そのまま取り残される。でも、うまく取り込んで「面倒なことはAIに任せて、自分は好きなことやる」ってスタンスになれれば、未来は案外楽しくなると思うんですよね。
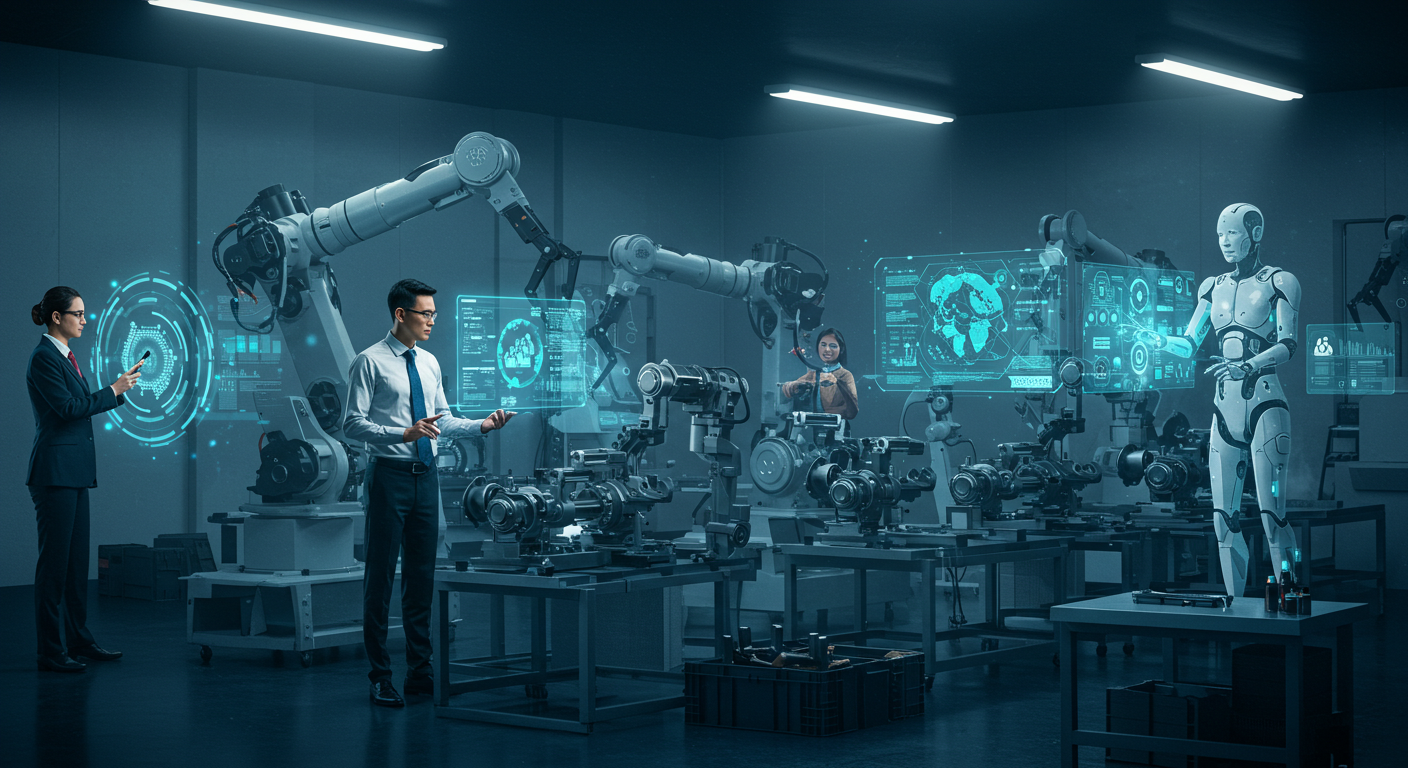


コメント