マグロの脂をAIが判定する時代に突入した話
職人の「勘」がいらなくなる未来
要は、富士通が開発したAIでマグロの脂のりを判定できるようになったらしいんですけど、これ、結局、今まで職人さんが長年の経験で培ってきた「目利き」みたいなのが、いらなくなるって話なんですよね。 つまり、何十年も修行して培ってきたスキルが、機械一つでポンと再現できちゃうわけです。
これ、単なるマグロの話じゃなくて、あらゆる業界に波及すると思うんですよ。 例えば、野菜とか果物の品質も、職人の目じゃなくてAIで見ればいいし、ワインの熟成具合も人間じゃなくてセンサーとAIで管理できるようになる。 だから、結局「経験が必要な仕事」ってのが、どんどん機械に置き換わっていく未来になるんですよね。
熟練工が不要になると、社会はどう変わるのか
うん、で、ここからが本題なんですけど、職人とか熟練工が不要になるって、実は社会全体にものすごい影響を与えるんですよ。
要は、若い人が「修行しなくていい社会」になるってことです。 これ、聞こえはいいんですけど、裏を返すと「誰でもできる仕事」ばかりになるってことでもあるんですよね。
たとえば、今までは30年修行しないとマグロの目利きができなかったのが、ボタン一つで誰でもできるようになる。 そうすると、技術職っていうカテゴリ自体がどんどん縮小して、単純労働か、あるいはAIを作る側にまわるか、どっちかしかなくなる。
つまり、中間層がごっそり消えて、めちゃくちゃ格差が広がる社会になると思うんですよ。 「高度なスキルを持った人」と「機械に使われる人」っていう、二極化がもっと加速するんじゃないかと。
「伝統」って本当に必要だったのか問題
伝統の重みは幻想だった説
日本って、やたら「伝統」とか「職人技」とか持ち上げる文化あるじゃないですか。 でも、それって本当に必要だったの?って話なんですよね。
要は、「長年修行してスキルを得る」って、単に効率が悪かっただけなんじゃないかと。 もし最初からAIがあったら、そんな無駄な努力しなくてもよかったわけで。
つまり、伝統っていうのは「技術が未熟だった時代の言い訳」みたいなもので、これからの時代にはどんどん意味が薄れていくと思うんですよ。 もちろん、伝統工芸とか文化としての保存は必要かもしれないですけど、それは趣味の世界にとどめるべきで、生活や経済活動にガチで組み込むものじゃない。
結局、効率的じゃないものは淘汰されるってだけの話なんですよね。
消える職人文化と生き残るもの
とはいえ、全部が消えるわけでもないと思ってます。
たとえば、寿司職人とか、ワインソムリエとか、ある種の「ブランド価値」がある職人技は、しぶとく生き残ると思うんですよ。 なぜなら、人間って「ストーリーに金を払う生き物」だから。
要は、「このマグロは30年修行した職人が選んだんですよ!」っていう物語が付加価値になって、機械で判別したマグロより高く売れる。 つまり、モノの本質じゃなくて、背景にある物語で差別化する方向に行くんじゃないかと。
だから、「機械より劣ってても生き残れる職人」っていうのは、「ストーリーを語れる職人」だと思うんですよね。
人間の感覚と機械の判断、どっちが正しいのか
人間のバイアスがどれだけ不正確だったかが露呈する
これも面白い話で、AIがマグロの脂のりを判定できるようになると、「今まで人間がやってた判定って、けっこういい加減だったんじゃないの?」ってバレるんですよね。
つまり、職人さんが「これは上モノだ!」って言ってたマグロが、実はそれほど脂が乗ってなかったり、逆に見た目が悪いけど脂のってるマグロを見逃してたり。 要は、今まで感覚でやってたものの精度が、データで可視化されちゃうってことなんですよ。
これって、医療の世界でもすでに起きてるんですよね。 レントゲン写真の診断で、人間の医者よりAIのほうが精度高いとか普通にある話で。 結局、経験と勘ってのはバイアスだらけだったって話なんです。
「人間らしさ」をどう定義するか問題
で、こうなると「じゃあ人間の役割って何なの?」って話になるんですけど、 僕は「人間らしさ」っていうのは、効率の悪さとか、曖昧さにこそあると思ってるんですよ。
たとえば、AIは「脂がのってるか」っていう明確な基準では勝てるけど、「このマグロを食べたときに幸せな気分になるかどうか」とか、そういう曖昧な感情には弱い。 だから、これからは「感情に訴えかける力」が人間の武器になるんじゃないかなと。
効率だけを突き詰めたら、どんどん無感情な社会になるけど、 「なんかこのマグロ、食べたら涙出たわ」みたいな、説明できない体験が、逆に貴重になる未来が来ると思うんですよね。
技術革新がもたらす新しい社会構造
「AIに使われる人」と「AIを使う人」の格差
要は、マグロの脂判定みたいな話って、表面だけ見ると「便利になったねー」で終わりがちなんですけど、 もうちょっと深く考えると、社会構造そのものが変わるきっかけなんですよね。
つまり、単純労働だけじゃなく、今まで専門性が高いとされていた仕事も、どんどんAIが代替できるようになる。 すると何が起きるかというと、「AIに使われるだけの人」と「AIを使いこなして成果を出す人」の二極化です。
たとえば、マグロの判定をボタン一つでできるようになったら、それを大量に効率よくさばける人間は重宝される。 逆に、「俺はマグロの目利きができるんだ」と自負してた人たちは、仕事を失うだけ。
結局、テクノロジーを受け入れて自分の武器にできるかどうかが、これからの生き残りに直結するんですよね。
教育の在り方も根本から変わる
さらに言うと、教育のあり方も変わると思うんですよ。
今までは、「知識を覚えること」とか「技術を身につけること」が教育の中心だったけど、 AIが正確にかつ高速で判断できる世界では、記憶力とか技術習得ってあんまり意味ないんですよね。
じゃあ、何を教えるべきかというと、「どうやってAIを使うか」とか、「どうやって新しい価値を生み出すか」という発想力。 要は、正解を知ってる人間じゃなくて、正解を自分で作れる人間を育てる方向にシフトするしかない。
つまり、「与えられた問題を解く力」よりも、「問題そのものを作れる力」が問われる時代になるって話です。
テクノロジーの進化と人間の幸福
便利になっても幸福度は上がらない説
ここでひとつ冷静に考えたいんですけど、テクノロジーが進化すれば人間は幸せになるかっていうと、たぶんならないんですよね。
だって、マグロの脂のりが正確に判定できるようになったからって、 別にみんなの生活が劇的に豊かになるわけじゃないし、むしろ仕事を失う人のほうが多くなる。
つまり、技術が進化しても、社会全体の幸福度ってあんまり変わらない。 一部の成功者だけがどんどん豊かになって、大多数は現状維持かむしろ悪化する。 これ、歴史見てもずっとそうなんですよね。
だから、AIによる効率化っていうのも、冷静に見れば「格差を広げるだけ」っていう側面のほうが強いと思ってます。
「無駄」があるから人間は楽しい
それでも、僕はあんまり悲観してないんですよね。
要は、人間って「無駄なこと」にこそ楽しさを感じる生き物だと思ってるんで。 マグロの脂のりをいちいち人間が判定しなくても、 「やっぱ俺は自分の目を信じる!」とか言いながら、機械に頼らずやるバカな人たちがいるほうが、世界は面白い。
結局、完璧で効率的な世界って、すごく息苦しいし退屈なんですよ。 多少ヘタクソでも、時間がかかっても、みんなでワイワイやってるほうが楽しいっていう価値観は絶対に残る。
だから、AIが進化しても、一定数の人間は「わざわざ非効率な道を選ぶ」という、超人間らしい生き方をするんじゃないかと思ってます。
まとめ:マグロAI判定が示す未来
効率化の波は止まらないけど、それが全てじゃない
結局、マグロの脂判定をAIがやるって話は、効率化社会の象徴みたいなもので。 これからどんどん、人間がやってた仕事が機械に置き換わっていくのは間違いない。
でも、だからといって人間が不要になるかというと、そんな単純な話でもない。
むしろ、機械ができない「無駄」とか「感情」とか「ストーリー」を作れる人間が、より一層価値を持つ時代になるんじゃないかなと。 要は、技術に飲み込まれるんじゃなくて、技術の上に乗っかって、 なおかつ人間らしさを忘れない人たちが、最後には勝つんだろうなって思ってます。
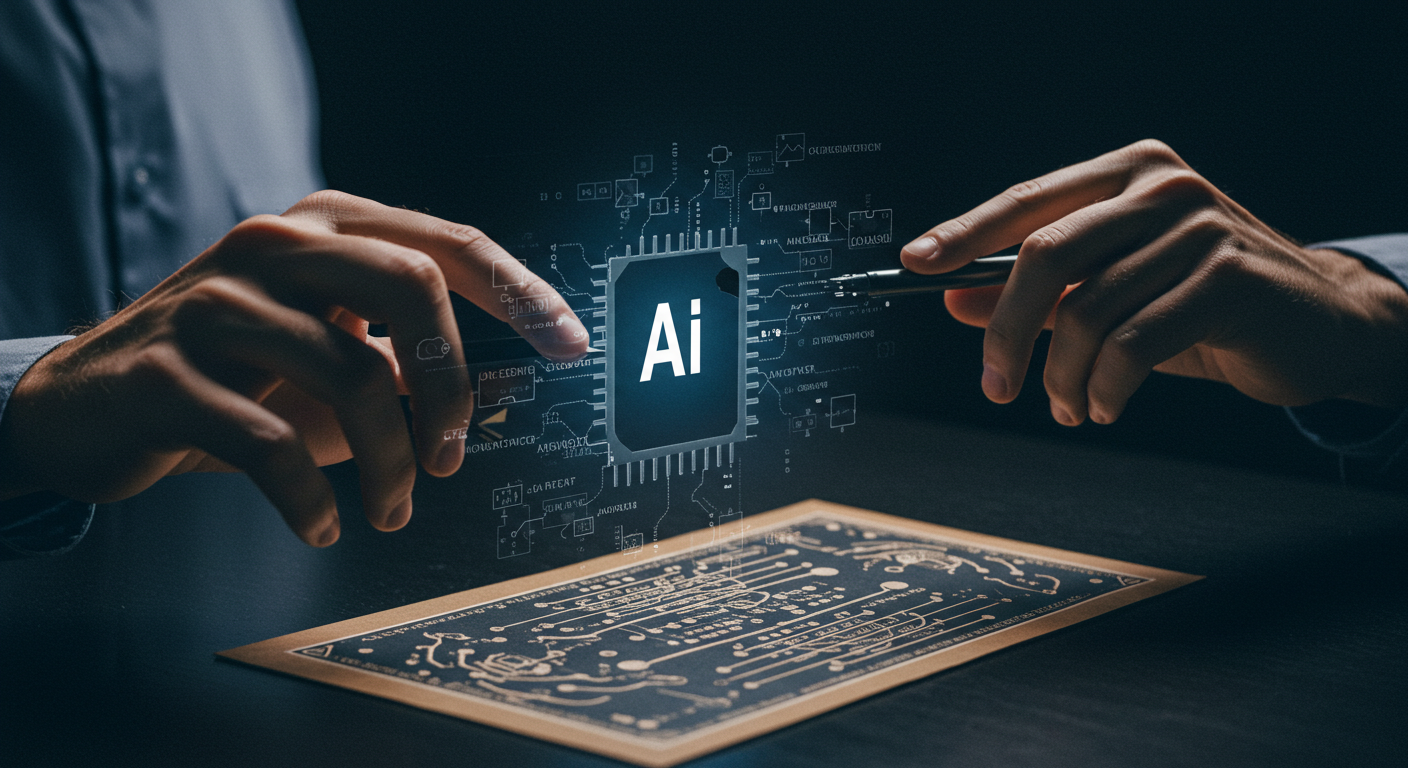


コメント