生成AIが起業の「初期コスト」を壊す
要は、技術の敷居が一気に下がるって話なんですよね
AWSが提供する「Technical Founder Sprint」って、まあ要するに起業家向けの集中講座なわけですけど、それが生成AIに特化してきたというのは、けっこう時代の象徴だと思うんですよね。 昔って起業するには、それなりに技術力が必要だったり、エンジニアを雇うお金が必要だったりしたわけですよ。で、プロダクト作るにもサーバー立てたりインフラ構築したり、かなり面倒くさい部分が多かった。
でも、今は違う。ChatGPTとかClaudeとか、あとはオープンソースの生成AIモデルを組み合わせて、アイデアさえあれば形にできちゃう。で、そのインフラもAWSが安く提供してくれる。 つまり「アイデア × プロンプト力」だけで起業できる時代が始まってるわけです。
エンジニアの価値、下がると思いません?
昔はコード書ける人が重宝されてましたけど、今ってGitHub Copilotとかにコード書かせるのが当たり前になりつつあるんですよね。 で、今回のAWSのイベントって「生成AIを活用してどう構築するか」ってテーマになってるので、要するに「人間が書くコードの価値」より「AIに何をさせるかを考える能力」の方が重要になるってことです。
つまり、今後の社会では「エンジニア」っていうより「AIハンドラー」が求められるんですよ。AIをいかに正しく使って、効率的にアウトプットさせるか。で、そのトレーニングやサポートをAWSが提供するっていう構造ができあがってる。
結局、コード書けるだけの人って、どんどんコモディティ化していくと思うんですよね。
プロダクトが「量産」される未来
誰でも作れるなら、何が残るのか?
プロダクトが簡単に作れるってことは、「プロダクトそのものに価値がなくなる」っていう皮肉な現象も起きるんですよね。 昔は「こんなアプリ作りました!」って言えば、それだけで称賛された時代もありましたけど、今は「で、それがどう便利なの?」って突っ込まれるのが当たり前。
技術的ハードルが下がった分、「問題解決力」や「ビジネスモデル設計力」が重要になる。AIで作れるんだったら、誰でも作れるからこそ、何を作るかより「なぜそれを作るのか」「どうやって売るのか」ってとこに価値が移動してる。
要は、ツールとしての生成AIはもう前提条件で、そこから先の話ができない人は、生き残れない時代に突入してるんですよね。
「個人開発者」と「大企業」の差が縮まる
これは面白い現象なんですけど、生成AIを使った開発って、むしろ大企業よりも個人の方が有利だったりするんですよ。 なぜかというと、意思決定の速さとか、プロトタイプの爆速リリースができるから。大企業は、稟議が必要だったり、社内調整に時間がかかったり、いろいろ縛りが多いんですよね。
でも個人とか小規模スタートアップなら、「あ、これ作ってみよう」で一晩でアプリ作って公開、ユーザーの反応見てすぐ改良、みたいなことができる。で、それを可能にしてるのが、生成AIとAWSの低コスト構築環境ってわけです。
だから、今後は「1人スタートアップ」みたいなのがもっと増えると思いますよ。で、そういう人たちが企業レベルのサービスをポンポン作るから、競争も激しくなるし、淘汰も速くなる。 結局、スピードと柔軟性が正義になるんです。
職業の変化と「無職の価値」
AI時代における「仕事」とは?
生成AIが台頭すると、いろんな職業が自動化されるって言われてますけど、それって要するに「意味のない作業をしてた人がバレる」ってことでもあるんですよね。 報告書作るだけの仕事とか、定型業務を回すだけの仕事って、全部AIに取って代わられるわけで。
で、「仕事がなくなる!」って叫ぶ人もいるけど、じゃあその仕事、そもそも価値あったんですか?って話なんですよ。 実際、フランスとかでは週35時間労働で「人生の豊かさ」が議論されてるけど、日本では「働くこと自体に意味がある」みたいな宗教になっちゃってるんですよね。
だから、AIが仕事を奪うんじゃなくて、「無意味な仕事を炙り出す」だけ。で、それによって、人間はもっと創造的な活動に時間を使えるようになるはずなんですよ。 趣味を極めるとか、地域で活動するとか、あるいはただのんびりするっていう選択肢も含めて。
無職でも価値がある社会へ
今までは「働いてないと人として終わってる」みたいな風潮ありましたけど、AIが当たり前に仕事する社会になったら、「無職でも価値がある」っていう考え方が出てくると思うんですよね。 要は、金稼いでなくても、面白いことやってる人の方が注目される時代。
例えば、X(旧Twitter)でバズる人って、別にサラリーマンとか社長とか関係なくて、単純に面白いこと言う人が支持されるじゃないですか。 それと同じで、職業がアイデンティティじゃなくなるんですよ。
で、そういう社会になると、教育とかも変わってくる。「何になりたいか」じゃなくて、「何を面白がれるか」が重視される。 結局、生成AIがもたらすのって、「能力の平準化」なんですよ。で、その中で目立つのは「人間性」とか「発想力」になってくる。
教育とキャリアの「設計思想」が変わる
AI時代に必要なスキルって何?
結局、AIができることが増えれば増えるほど、人間にしかできないことが浮き彫りになるんですよね。で、それが「正解を出す力」じゃなくて、「問いを立てる力」になってくる。
日本の教育って、いまだに「正解をいかに速く出すか」にフォーカスしてますけど、AIはその部分を完全に代替できちゃうわけです。 だからこれからの教育は、「そもそもその問題って必要?」「なんでそれをやるの?」っていう、メタ認知的な視点が重要になる。
それともうひとつ、「自分の機嫌を自分で取る力」も大事になってくる。 AIがどれだけ便利になっても、他人に感情任せてる人って、不満だらけの人生になっちゃうと思うんですよね。 要は、自分が楽しく生きるための設計を自分でできる人が、これからの時代の勝者になるんです。
キャリアのゴールは「肩書き」じゃない
昔って、「大企業に入る」「役職を得る」みたいなのがキャリアのゴールだったと思うんですけど、今はもうそういうのが無意味になってきてる。 むしろ、フリーランスで好きなプロジェクトに関わって、年に数ヶ月だけ働いて残りは海外で過ごす、みたいなライフスタイルの方が羨ましがられる時代なんですよ。
で、生成AIの普及によって、こういうライフスタイルが実現可能になる。 つまり、労働の「密度」と「時間」の関係が崩れるんですよね。1日8時間働くことに価値はなくて、1時間で価値出せばそれでOK、っていう話になる。
そうなると、「どう生きるか」に主軸を置いたキャリア設計になるわけで、これはもう働き方というより「生き方のアップデート」なんですよ。
企業と社会構造の変化
企業の「規模」が価値じゃなくなる
これまでって、大企業が資本と人材を集めて、巨大なシステムを動かして…みたいな構造だったんですけど、生成AIがあれば、10人未満のチームでもそれ以上の生産性を出せるんですよね。
となると、企業の「規模」自体にあまり意味がなくなる。 むしろ、スピードと柔軟性を持った小規模チームの方が市場に対応できるし、ユーザーとの距離も近い。結果的に「顧客体験」で勝負する企業が強くなる。
要は、これからは「組織の力」よりも「個人の能力」と「ツールの使い方」が勝負になるんです。で、その中心に生成AIがあるという話。
社会の「中間管理職」不要論
生成AIが普及すると、情報共有や報告、意思決定が効率化されるんですよね。そうなると、中間管理職の「調整役」ってかなり役割を失う。
SlackとかTeamsにAI入れて、議事録やタスク管理を自動化すれば、部下からの進捗報告も上司への説明も全部不要になる。 そうなると、「じゃあ中間管理職って何のためにいるの?」って話になる。
もちろん人材育成とかもあるけど、それもAIがコーチングできるようになってきてるんで、ますます人間がやるべき部分って絞られてくるんですよね。
AIと共存する人間の姿
結局、人間は「遊び」に回帰する
AIに仕事を任せて、人間は何をするかって言ったら、僕は「遊ぶこと」に戻っていくと思うんですよ。 仕事っていうより「面白いことを追いかける」っていうスタイル。
それが創作活動でもいいし、ゲーム配信でもいいし、農業でもいい。 今までは「収入につながること」しか価値がないとされてましたけど、これからは「人生を豊かにすること」が重視されるようになる。
で、それを支えるのがベーシックインカムだったり、AIで自動化された社会インフラだったりするわけで、人類全体が「働かなくても生きていける」って状態に少しずつ近づいていく。
それでもAIに使われる人は出てくる
ただし、誰もが幸せになるかというと、そうでもないんですよ。 生成AIをツールとして使いこなす人もいれば、逆にAIに使われる人も出てくる。
例えば、TikTokでアルゴリズムに依存してコンテンツを作る人たち。アルゴリズムの顔色を伺って、数字だけを追いかける人生になると、結局それって「AIの奴隷」なんですよね。
つまり、AIの時代をどう生きるかって、単に技術の話じゃなくて「価値観の話」になってくる。 自由に遊べる社会なのに、自分で考えることを放棄して、楽な方に流れてAIに操作される人も出てくる。
だからこそ、「考える力」「自分で決める力」って、より重要になってくると思うんですよね。

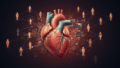
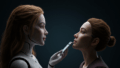
コメント