囲碁AIの進化が示す未来
人間の「思考力」の価値が変わる
要はですね、囲碁AIが進化したことで何が起きてるかっていうと、人間の思考の「上限」がテクノロジーによってあっさり超えられた、ってことなんですよ。で、昔だったら、何十年も修行してようやく到達する境地ってのがあったわけですけど、今はAIに数日教えたらそれを超えちゃうと。
で、これって囲碁だけの話じゃなくて、要するに人間の「考える力」が今後どんどん代替されていくんですよね。つまり、「考えなくてもいい人」が増えて、「考えられる人」しか価値がなくなる社会になる可能性があるんです。
例えば、将棋でもAIがプロ棋士より強くなったことで、若手がAIを使って研究するのが当たり前になったんですけど、それって「自分の頭で考える」っていう訓練の時間がごっそり削られるってことなんですよ。囲碁も同じで、AIが最適解を見つけてくれるなら、人間はそれを真似すればいい。
でも、それって長期的に見ると「考える力」が退化してく方向に行くと思うんですよね。
社会の中で「凡人」が減っていく
結局ですね、囲碁AIがすごい進化したっていうのは、社会全体が「平均」じゃなくて「トップ」の再現性を機械で可能にする方向に進んでるってことなんです。で、これまでだったら、普通の人でも努力して経験積めばなんとか一流に近づけたんですけど、AIが「最適化された知識と経験」を即座に提供してくると、そういうプロセス自体が無意味になる。
つまり「努力の過程」が評価されない時代になるんですよ。だから、凡人が成長して活躍するという物語が、社会からどんどん消えていく。AIを上手に使えるやつだけが価値を持つ。で、それ以外の人たちは「再生産されない凡人」になるだけです。
例えば、囲碁の世界では若手棋士がAIを使って研究して強くなるケースも多いんですけど、それって「AIを使ってるから強い」ってだけなんですよね。で、AIがなかったら強くなれたかっていうと、たぶんなれない。
そうすると、人間が持ってた「成長性」とか「ポテンシャル」っていう評価軸が意味を持たなくなる。じゃあ、社会はどうなるかっていうと、「今すぐ結果を出せる人間」だけが評価されるようになる。長い目で育てるとか、ポテンシャルを信じるとか、そういう余裕がなくなる社会になります。
AIと共存する社会のズレ
教育の目的が変わる
あと、AIの進化で大きく変わるのは「教育」ですね。今の学校教育って、基本的に「知識を覚えること」に時間を使ってるんですけど、AIがその役割を担えるなら、それ全部意味なくなるんですよ。
囲碁AIが出てきたことで、子供がプロ棋士になるために必要なステップも変わったわけです。昔なら地道な修行と実戦経験が必要だったのが、今はAIから学ぶのが最短ルートになった。で、これは他の分野でも一緒なんですよ。
たとえば、歴史や数学、語学でもAIが答えを出してくれるなら、人間がそれを覚える意味って何なんですか?って話になるんです。じゃあ、教育で何を教えるべきなのか?っていうと、「AIにどう質問するか」「どう使うか」っていう能力になる。
つまり、知識を得る力じゃなくて、「使いこなす力」が教育のゴールになるわけです。で、それを子供たちに教える教育者が、果たして今の日本にどれくらいいるのかっていうと…まあ、ほぼいないですよね。
「AIに勝てない仕事」の価値が上がる
もう一つの未来予測として、逆に「AIに勝てない仕事」の価値が上がるって話があります。つまり、AIが得意なのは論理とデータの処理なんで、そこに頼ってる職業はどんどん淘汰されるんですけど、逆に人間にしかできない領域ってのもあるんですよ。
例えば、人間の感情に寄り添う仕事。介護、教育、育児とか、そういう「非効率」を前提にした仕事は、AIに完全には任せられない。
囲碁の例で言うと、いくらAIが強くても、それを「教える」ことができるかというと難しいんですよ。結局、子供や初心者に囲碁を教えるのは人間の役目になる。で、そこには「人間らしさ」とか「共感」とか、論理では測れない要素が必要になってくる。
だから、未来の社会では「論理的に正しいこと」よりも「感情的に納得できること」のほうが価値を持つ可能性がある。つまり、論理で勝てる仕事はAIに任せて、人間は「感情」にシフトするっていう構造ですね。
AI社会で問われる「人間らしさ」
感情と偶然性の重要性
で、AIが囲碁のような論理性の高いゲームで圧倒的な成果を出すと、人間が勝てる部分ってどこなの?って話になるんですけど、結局それは「非合理性」だったり「偶然性」だったりするんですよね。
囲碁でいうと、プロ棋士の一手がAI的には「悪手」でも、人間的には「美しい」とか「粋だ」とか感じることがあるわけです。で、それを見て感動する観客がいる。つまり、AIが完全に合理性を追求する一方で、人間の価値は「非合理な魅力」にシフトしていくんです。
たとえば、芸術やエンタメ、創作系の分野なんかはまさにそうで、「なぜこれが心に響くのか」をAIが完全に説明することはできない。そこに人間の余地が残ってるんですよ。
だから今後は、合理的に説明できないけど「なんかいい」とか「感覚的に好き」とか、そういう要素が重視されてくる社会になる可能性があります。逆に言えば、すべてを数値化して説明しようとする人間の価値はどんどん薄れていく。
偶然を生む「余白」がなくなる世界
ただ、ここで一つ問題なのが、AIが社会に浸透しすぎると「偶然」が減ってくるんですよね。要するに、AIは最適解しか選ばないので、そこに「ミス」や「気まぐれ」ってものが存在しない。
囲碁でいえば、人間が偶然打った一手が奇跡的な大逆転を生むとか、そういうドラマが起きにくくなる。で、これって社会全体でも同じで、「非効率な選択」が許されない空気になるんです。
人間の歴史って、偶然から生まれた発明や、思いがけない失敗から得られた教訓とか、そういうのが山ほどあるわけで。AI社会になると、そういう「余白」がどんどん失われていく。つまり、「偶然を楽しめる文化」が廃れていくんですよ。
だから、未来の社会で本当に価値があるのは、「偶然を意図的に起こせる人間」だと思うんですよね。効率性だけを追求するのではなくて、あえて無駄を選べる勇気とか、偶然を受け入れる感性とか。そういう部分が、ますます重要になるんじゃないですかね。
未来の囲碁、未来の社会
「勝負」の意味が変わる
で、囲碁AIの進化って、結局「勝負の意味」を変えたと思うんですよ。勝つことが目的じゃなくて、「どれだけ美しく負けるか」みたいな、価値の再定義が始まってる。
これは社会にもそのまま当てはまって、今後の世界では「成果を出すこと」が目的じゃなくなって、「どんなプロセスでやったか」「どんな意味があったか」が評価されるようになる。
たとえば、AIが最適解を出してくれるなら、人間がやるべきことは「その選択にどんな意味を込めるか」になるわけです。囲碁でも、AIの打ち筋にあえて逆らう一手を打つことで「自分らしさ」を表現する、みたいな。
これからは「勝つこと」よりも「意味を生むこと」が重視される。つまり、定量的な成果じゃなくて、定性的な価値の時代になる。で、それがわかってる人と、わかってない人で、ものすごい格差が生まれると思います。
AIが導く「人間の再定義」
結局ですね、囲碁AIが人間を超えたことで、人間の役割って何?って話になるわけです。で、これは囲碁に限らず、社会全体の話にもつながる。
AIが「考えること」を代替し、「決断すること」も代替し、「最適な選択」を提案してくる時代に、人間がやるべきことって、「生き方」なんですよね。どう生きたいか、どんな風に時間を使いたいか。それを自分で決めること。
でも、そういう「自己決定」って、実はすごく難しい。今まで人間って、社会の価値観とか枠組みに従って生きてきたわけで、それが壊れると「自由だけど不安定」な世界になる。
囲碁の世界でも、AIが正解を教えてくれる時代に、「自分はなぜこの一手を選ぶのか」って問いが必要になる。それと同じように、AIが正解を示す世界では、人間が「自分なりの間違い」をどう選ぶかが問われるようになるんです。
つまり、囲碁AIの進化って、「人間とは何か」をもう一度問い直すための材料になるんですよね。で、その問いにちゃんと向き合える人だけが、これからの時代をうまく生きていけるんじゃないかと思います。

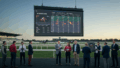

コメント