AIで教育格差は縮まるのか?
学び方の民主化が起きる
要は、Fujitsuとマッコーリー大学がやってる「AutoMLを学べる講座」って、AI技術を一部のエリート層じゃなくて、一般人に開放しようっていう流れなんですよね。で、こういうのが増えると何が起きるかっていうと、教育の民主化が進むわけです。つまり「学歴」よりも「スキル」や「実績」が重視される社会になっていく。
例えば、今までは東京大学とかMITとか、名門大学の肩書があるだけで企業が採用してた。でもこれからは、「あ、この人、FujitsuのAutoML講座を修了して、実際にモデル作って運用できるんだ」って人のほうが重宝される可能性が高い。
で、そうなってくると、わざわざ高額な学費を払って大学に行かなくても、オンラインで専門スキルを獲得して、ちゃんと食っていけるようになる。学歴よりも実力。これって結構、世界の構造を変える話だと思うんですよね。
地方と都市の格差も縮まる
今までだったら、最先端のAI技術を学ぼうとしたら、東京とかシドニーとか、都市部に出ないと難しかった。でも、オンラインで高品質な講座が受けられるってなると、地方にいても関係ないんですよ。
要は、インターネットとPCさえあれば、誰でも「最先端の知識」にアクセスできる社会になる。で、これって日本みたいに地方と都市の格差が問題になってる国にとっては、かなりデカい変化です。田舎に住んでても、AIエンジニアとして東京の企業にリモートで仕事できるみたいな流れになるわけですから。
そうすると、人口が都市に集中する理由も薄れるし、地方活性化にも繋がる可能性がある。もちろん、そこに至るまでにはインフラ整備とか色々あるけど、「選択肢がある」ってだけで人の人生の幅が変わるんですよね。
企業の採用基準が変わる未来
ポートフォリオ採用が主流に
昔は「どの大学を出たか」「どこの会社にいたか」が重視されてたんですけど、これからは「何ができるか」「どんなプロジェクトをやってきたか」が大事になります。要は、ポートフォリオが採用の基準になる。
で、Fujitsuの講座みたいに実践ベースでAIモデルを作る訓練があると、「はい、これ僕が作ったモデルです」って提示できるわけです。そうすると、企業側も「この人、即戦力じゃん」って判断しやすくなる。
だから、採用活動がかなり効率化されますよね。今までは新卒を取って、一から教育してたのが、最初から一定のスキル持った人をプロジェクトベースで雇うみたいな流れになる。働き方もどんどん「プロジェクトベース」「成果ベース」に変わっていくと思います。
転職や副業の自由度が上がる
AutoMLみたいなスキルが身につくと、転職も副業もしやすくなるんですよね。例えば、今までは「会社辞めたら次の職見つかるまで不安」って人が多かった。でも、スキルがあって、しかも証明できる資格や作品があると、「じゃあ次、別のとこで働こうかな」って判断がしやすくなる。
で、そういう人が増えると、企業側も社員を大事にしないとすぐ辞められるから、待遇改善せざるを得ない。つまり、労働者側の交渉力が上がるって話です。これは働く側にとってはかなりポジティブな変化。
副業もそうで、AutoMLスキルがあると「週3で企業のAI分析の仕事して、残りはフリーで別案件やってます」みたいな働き方も可能になる。これまでの「9時から5時まで会社にいなきゃダメ」みたいな昭和的働き方は、ますます時代遅れになっていくでしょうね。
教育機関と企業の関係も変わる
大学の存在意義が問われる
正直なところ、オンラインで実用的なスキルが学べるようになると、「じゃあ大学って何のために行くの?」って話になるんですよね。もちろん、研究職とかアカデミックな職業を目指す人には大学が必要なんですけど、一般的なビジネスパーソンにとっては、もっと効率的な学び方があるってことになる。
で、そうなると大学側も「座学だけじゃ意味ないよね」「実務スキルも教えないと学生来ないよね」ってなる。つまり、大学教育も変わらざるを得なくなる。企業と連携して即戦力を育てるとか、プロジェクトベースの教育を増やすとか、そういう方向にシフトしていくはずです。
企業主導の教育が加速する
逆に言うと、企業が自前で教育リソースを持ち始めるんですよ。Fujitsuみたいに、「自社で使ってるAI技術を教える講座を作る」っていうのが、どんどん一般的になる。
つまり、「教育=学校」っていう発想が崩れて、「教育=企業×オンライン」になるわけです。で、こういう構造が当たり前になってくると、「企業が社会に対してどう教育を提供するか」ってのが、新しい社会的責任の一つになる。
そうすると、企業は単にモノを売るだけじゃなく、「人を育てる」こともビジネスモデルに組み込んでいく。人材育成そのものが新しい収益源になる可能性もある。これって結構すごい話で、教育の在り方が根本から変わる流れです。
グローバル人材とローカルスキルの逆転現象
「英語ができるだけの人」の価値が下がる
昔は「英語ができる」ってだけで価値があったんですよね。海外と取引できるとか、グローバルな視点を持ってるとか。でもこれからの時代って、AIの技術とかデータ分析とか、そういう「具体的なスキル」がないと英語だけじゃ食えない。
で、今は自動翻訳とか音声認識も進化してるから、正直、英語が多少できなくても技術さえあれば仕事になる。つまり、「グローバル人材」の定義が変わっていくんですよね。「言葉」じゃなくて「技術」を持ってる人が、国境を越えて仕事をする時代になる。
なので、これまで「グローバル企業で英語使ってます!」ってだけで威張ってた人たちは、ちょっと立場が危うくなるかもしれないですね。
「地元で世界とつながる」働き方が増える
逆に言えば、地方に住んでる人でも、AutoMLとかAIスキルを持っていれば、世界中の企業と仕事できる時代になるわけです。田舎の小さな家から、アメリカのスタートアップのプロジェクトに参加してるみたいな働き方が普通になる。
で、そうなると「引っ越す理由がない」って人が増える。地方移住とかも促進されて、都市一極集中の流れが逆転する可能性もあるんですよ。都会の高い家賃払わなくても、同じ仕事ができるなら、みんな地方に住みたがるのは当たり前。
これ、結構デカい社会変化で、インフラや不動産の在り方も変わってくると思うんですよね。
教育の評価基準が変わる社会
資格よりも「できること」が問われる
今の社会って、まだまだ「資格があるかどうか」で評価されがちなんですけど、これからは「それで何ができるの?」って問いがメインになります。例えば、「AI検定1級持ってます」って言っても、実際にモデル組めなかったら意味ないわけです。
で、Fujitsuの講座みたいに「実際に手を動かして、プロジェクト単位で学ぶ」って形式が主流になると、履歴書じゃなくてポートフォリオの時代になります。GitHubのアカウント見せて、「これ僕が作ったAIです」って言える人の方が強い。
だから、学びの評価が「資格」から「成果物」にシフトする。これは学生だけじゃなくて、社会人にとっても大きな変化ですね。
学び直しが当たり前になる時代
一回大学を卒業して就職したら、もう勉強しなくていいって時代は終わりです。むしろ「今の仕事に飽きたら、オンラインで新しいスキル学んで次に行く」ってのが普通になる。
で、特にAIとかテクノロジー系の分野って変化が早いから、常に学び直さないといけない。そうすると、年齢関係なく勉強するのが当たり前になるし、「勉強してる=意識高い」って風潮もなくなると思うんですよね。
実際、今でも40代とか50代でプログラミング勉強して転職成功する人もいるわけで、年齢よりも「今、何を学んでるか」が重視される時代になります。
国家と教育の役割の再定義
国家による教育支援の重要性
ただ、こういう教育の個別最適化が進むと、「全部自分で学べばいいじゃん」って話になりがちなんですけど、それはそれで問題もあるんですよね。要は、自己管理ができる人とできない人の格差が広がっちゃう。
だからこそ、国家レベルで「誰でもアクセスできる教育リソース」を整備する必要がある。つまり、無料で受けられるオンライン講座とか、補助金でスキル講座を受講できる制度とか、そういう支援が重要になってくる。
で、それをやらないと、結局「学べる人」と「学べない人」の格差が固定化されて、社会全体の生産性が上がらない。なので、教育ってのは個人の問題であると同時に、社会全体の未来に関わるインフラなんですよね。
企業と国家の協業が鍵になる
Fujitsuみたいな企業が教育に乗り出すのはすごくいいことなんですけど、最終的には国家と企業が協力しないと効果が最大化されないんですよ。例えば、企業が作った講座に公的な認定を与えるとか、講座の受講に助成金を出すとか。
そういう仕組みがあれば、企業が作った教育資源が「公教育の一部」として機能するようになる。で、これは結果的に「教育の質」を底上げするし、「実社会で役に立つ教育」を全国民が受けられるようになるわけです。
だから今後は、「文科省と民間企業が協業して、教育を再設計する」みたいな流れが絶対必要になると思います。で、それがうまくいく国が、将来的に技術大国として生き残っていくんじゃないですかね。
結局、何が変わるのか?
「自分で選ぶ」時代の到来
最終的に、こういう変化って何を意味してるかっていうと、「人生の主導権を自分で握る時代になった」ってことなんですよね。今までは、「いい大学入って、いい会社に就職して、定年まで働く」っていうテンプレートがあったけど、それが崩れてきた。
だから、これからは「自分は何ができて、何をしたいか」をちゃんと考えて行動する必要がある。でも逆に言えば、誰にでもチャンスがあるってことです。スキルを身につければ、どこに住んでても、どんな経歴でも、仕事ができる。
で、こういう社会って、自由である反面、自己責任の時代でもある。「やらない人」はどんどん置いていかれる。だから、自分で考えて動ける人が強い時代になるわけです。
結局のところ、学歴や年齢に関係なく、「学び続ける人」が生き残る。そんな社会に、もうすでに突入してるんじゃないかと思ってます。
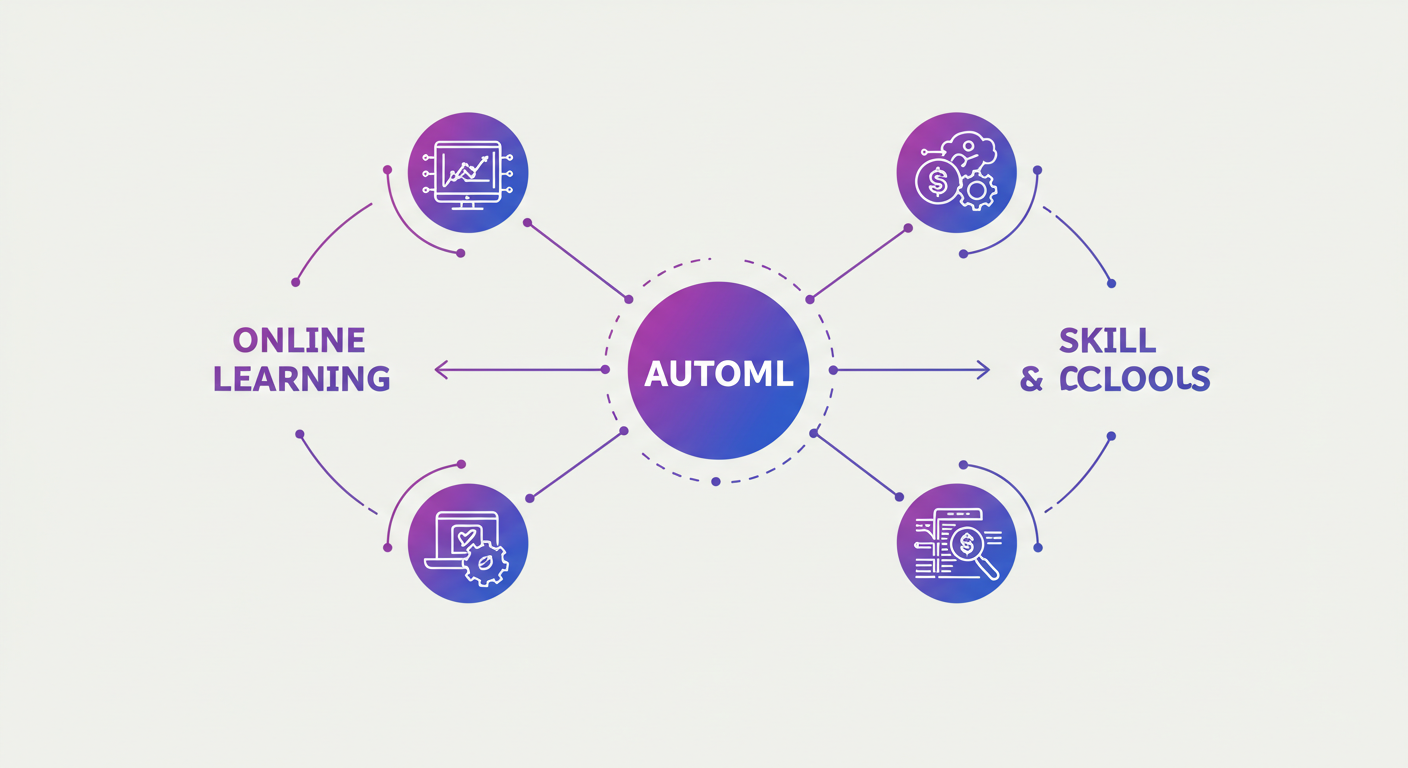


コメント