ソフトバンクの6兆円投資が意味するもの
金の力で未来をねじ曲げようとする話
ソフトバンクがOpenAIに6兆円投資するって話、普通に考えたら「すごいね」って話になると思うんですよ。でも、要はそれって、金の力で未来をねじ曲げようとしてるってことなんですよね。AIっていうのは、本来は徐々に発展していく技術だったはずなんですけど、大量の資本が流れ込むことで、数年先に起こるはずだった変化が、一気に数ヶ月とかで現実化しちゃうわけです。
で、OpenAIって元々は「人類にとって有益なAIを作る」っていう理想で始まったんですけど、最近は普通に商業ベースの企業になってるんですよね。だから、ソフトバンクみたいな資本を入れるってことは、利益重視の方向にさらに舵を切ることになる。つまり、僕らが使うAIのサービスも「便利かどうか」じゃなくて「金になるかどうか」で進化していくわけです。
AIによって職がなくなる未来
よくある話ですけど、AIに仕事が奪われるってやつですね。で、今回みたいに6兆円レベルの投資がされると、要は「人間がやってる仕事をAIに置き換えた方がコスパいいよね」って流れが、もう止まらなくなるわけです。たとえばカスタマーサポートとか、文章の作成、翻訳、会計、マーケティングのデータ分析。こういう仕事って、別に人間じゃなくてもいいんですよ。
僕が思うに、今後10年でホワイトカラーの仕事の3割くらいは、AIによって消滅するんじゃないかと思ってます。で、その失業者がどうなるかっていうと、結局は「AIを使いこなせる側」か「それに使われる側」に分かれるわけです。
で、問題なのは、日本ってITリテラシーが極端に低い国なんですよね。未だにFAX使ってる役所とか、手書きの書類が大好きな企業とかが普通に存在する。そういうところに勤めてる人たちは、AIに仕事を奪われるっていうより「気づいたら職場ごとなくなってた」みたいな未来を迎える可能性が高いです。
教育と再学習のシステムが追いつかない
で、失業者が出るのはしょうがないにしても、じゃあその人たちをどうするのかって話になるわけですけど、日本の教育って基本的に再学習とか、社会人がスキルをアップデートするための仕組みがほとんどないんですよね。大学に戻るにも金がかかるし、企業も再教育に投資しない。
結局、何が起きるかというと、「技術的には人類が前に進んでるのに、社会全体としては格差が広がって、取り残される人が増える」っていう状態になるわけです。これ、アメリカとかでも起きてる現象ですけど、日本の場合は高齢化もあって、もっと深刻になります。
人々の生活はどう変わるのか?
無人化と監視社会の進行
6兆円の投資が意味するのは、AIの劇的な進化だけじゃなくて、それに対応するインフラの拡充も含まれてるわけです。たとえばデータセンター。これが増えるってことは、より多くの情報がリアルタイムで処理されるようになる。で、それによって何が起きるかっていうと、社会全体の「見える化」が進むんですよね。
つまり、スーパーのレジも無人になるし、交通もAIが管理するし、防犯カメラもAIが顔認識して自動通報するとか、そんな未来です。で、便利にはなるんですけど、同時に監視社会化も進むんですよね。「あ、あの人、週に3回コンビニで酒買ってるな」とか、データとして全部残っちゃう。
「別に悪いことしてないし監視されても平気」って人も多いと思うんですけど、それって要は「支配される側の発想」なんですよね。自由に何かを選ぶっていう感覚が、少しずつ奪われていくんです。
人間関係の形も変わる
AIが発展してくると、当然、人とのコミュニケーションの形も変わってきます。たとえば、すでにChatGPTを使って恋愛相談とかしてる人がいるわけですけど、将来的には「人間よりAIのほうが話しやすい」って感じる人が増えていくと思うんですよ。
で、それって何を意味するかっていうと、家族とか友達とか、リアルな人間関係の価値が相対的に下がっていくってことなんですよね。特に若い世代は、すでにネットの中で完結するコミュニケーションに慣れてるから、「別に会わなくてもよくね?」ってなる。
こうなると、孤独感ってのは一見減るように見えるんですけど、実際は逆に増えていくと思ってます。AIとのやり取りって、リアルな意味での「共感」や「愛情」ではないから、本質的に満たされない。でも、それに気づいたときには、もう人間との関係の作り方を忘れてるってことになるかもしれない。
経済と社会構造の変化
中間層の消滅と格差社会の加速
前半で触れたように、AIの導入でホワイトカラーの仕事が削られていくと、いちばん影響を受けるのは中間層なんですよね。つまり、そこそこ稼げていたサラリーマン層が、AIに取って代わられて収入を維持できなくなる。で、上にいる「AIを作る人たち」や「資本を持ってる人たち」はもっと儲かるようになる。いわゆる“勝ち組”ですね。
つまり、資本主義の構造がさらに強化される方向に進むんです。AIが労働を代替するってことは、労働者が不要になるわけで、人間の時間と労力が価値を持たなくなる。で、労働から得られる対価がどんどん下がっていく。これは「働かなくても生きていける社会」ではなく、「働いても生きられない人が増える社会」になるってことです。
日本の場合、こういった変化に対する政治的な対応が非常に遅れてるので、気づいたら“貧困層が過半数”みたいなことが起きてもおかしくないです。
ベーシックインカムは現実化するのか?
じゃあ、そういう社会でどうやって生活を維持するのかって話になると、やっぱり出てくるのが「ベーシックインカム」なんですよ。でもこれ、日本ではかなり難しいです。財源の問題もあるし、既得権益に守られてる層が多すぎる。
ただ、未来予測として言うなら、AIが本格的に労働を代替するようになると、社会全体が生産性を維持するためには、消費者である国民を生かしておく必要がある。つまり「最低限の金は配ってやらないと経済が回らない」って状況になるんですよね。
要は、ベーシックインカムって「人道的な制度」じゃなくて、「経済を壊さないための制度」として導入される可能性が高い。でも、政治家が「国民のために」なんて理由で動くことはなくて、「もうやらないと回らないから仕方なく」ってタイミングになると思います。
AIと人間の役割の再定義
創造性と感情が唯一の武器になる
AIにできることが増えるってことは、人間がやるべきことが減るわけですけど、それって逆に言うと、「AIにできないこと」がすごく価値を持つようになるってことなんですよね。たとえば芸術とか、感情を扱う仕事、ストーリーテリング、哲学的な思索とか。
つまり、要は「無駄なことをする力」ってのが重要になる。AIってのは効率の塊だから、非効率で意味のないことは基本的にできない。でも人間は、無駄なことに情熱を注げるし、意味のないことに価値を見出すことができる。それって、すごく人間らしいことだと思うんですよ。
これからの社会で生き残るためには、逆に「役に立たないこと」に価値を見出せる人が強いんじゃないかと思ってます。だから、芸術や哲学、娯楽といった分野が、もう一度見直される未来が来るかもしれません。
人間性の回復と「意味」への渇望
AIの発展によって便利になった社会って、最初は「楽でいいね」ってなるんですけど、そのうち「全部やってくれるAIに囲まれて、自分の存在って何なんだろう」って疑問が出てくると思うんですよ。つまり、人間が「生きる意味」みたいなものを求める流れになる。
昔は「働くことに意味がある」って言われてましたけど、仕事がAIに奪われたら、その意味も失われるわけです。で、宗教とか哲学とか、精神的な拠り所に回帰する人が増える可能性が高いです。
僕が思うに、これからの社会では「自分の存在意義を定義できる人」が生きやすくなるし、「他人から与えられる意味」で生きてる人はどんどん辛くなる。要は「自分で物語を作れる人」が強い社会になるわけです。
未来をどう受け入れるか
悲観ではなく選択の問題
AIが発展する未来って、一見するとディストピアっぽく感じるかもしれません。でも、それをどう受け取るかは、結局はその人の「選択」の問題なんですよね。「便利になって楽でいい」と捉えるのか、「自分の価値が下がった」と捉えるのか。
で、前者の人はうまくAIと共存できるし、後者の人はAIを敵視して生きにくくなる。だから、必要なのは「どっち側の視点で生きるか」を早めに選ぶことなんですよね。時代に文句を言っても変わらないし、AIを止めることもできない。だったら、どう利用するかを考える方が合理的です。
知識よりも「態度」が問われる時代へ
昔は「何を知ってるか」が価値になってたんですけど、これからは「どう生きるか」「どう考えるか」っていう態度のほうが大事になる。知識はAIが持ってる。でも、それをどう活用するか、どんな目的で使うかっていうのは人間の側に残る領域です。
つまり、「どう考えるか」ってことに価値が移動していく。論理的に考える力とか、違う視点を持つ力とか、共感する力。そういうのが、今後の社会では「資本」になると思います。要は「人間らしさ」が通貨になるって話ですね。
で、そのためには、日頃から問いを持ち続けることが大事です。「これは何のためにあるのか?」「本当にそうなのか?」っていう態度が、AI時代を生き抜くためのスキルになっていくんじゃないかと思ってます。
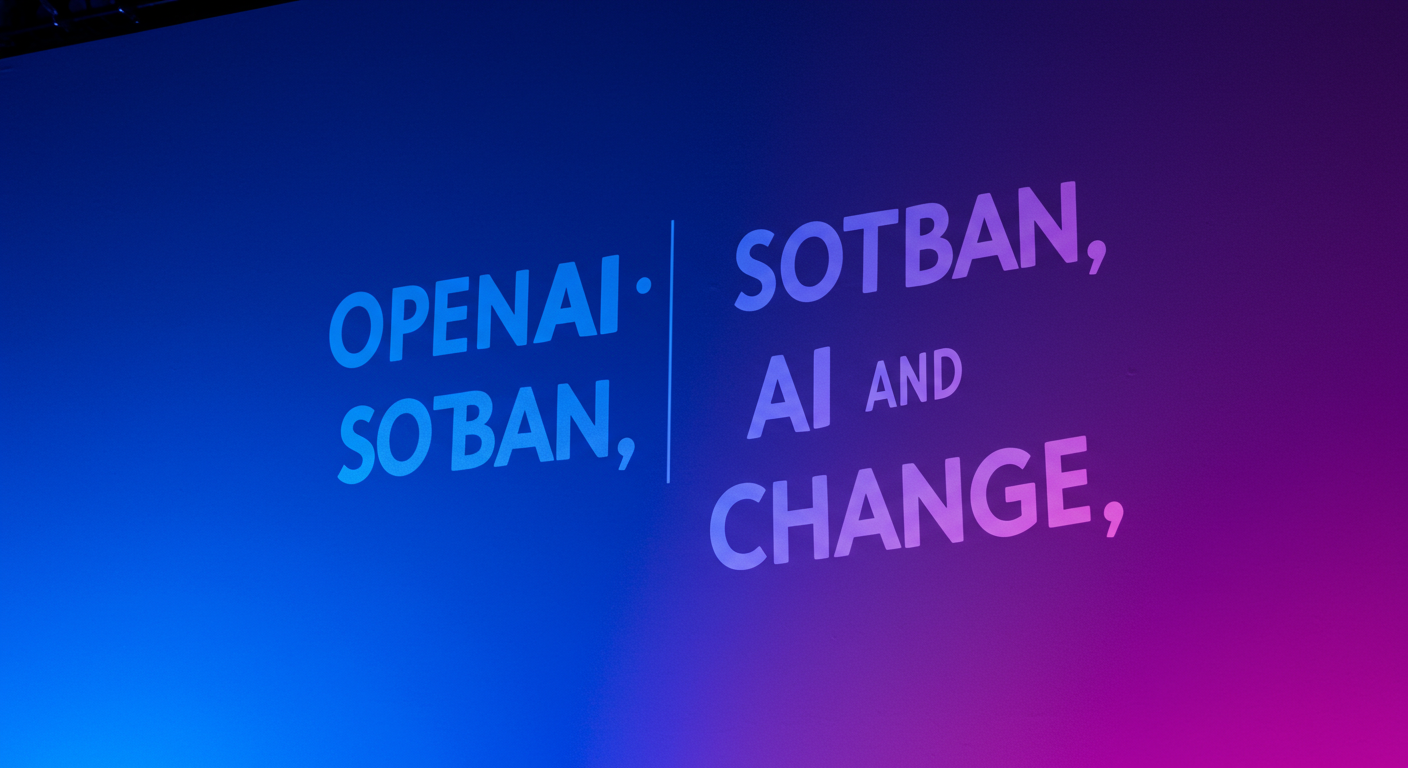


コメント