オープンAIの欧州進出が示す未来
要はAIインフラ戦争が始まるって話
オープンAIのサム・アルトマンさんが「スターゲートの欧州版を作る」とか言ってるわけですけど、これって要するに「AIのインフラ整えた国が勝つ」って話なんですよね。AIをどれだけ活用できるかってのは、結局その国のデータセンターの数とか計算能力に依存するんで、もう「AIの時代」じゃなくて「AIインフラの時代」に入ったわけです。 で、アメリカは当然自国で進めるとして、そこにソフトバンクとオラクルが乗っかってきてる。これ、日本の企業が絡んでるから「日本もAI競争の中心にいる」とか勘違いする人いるかもですけど、ソフトバンクがやってるのは「投資」なのであって、日本国内でAIが発展するわけじゃないんですよね。要するに、お金は出すけど実際の恩恵を受けるのは別の国っていういつものパターン。 で、欧州がここに乗るってことは「データセンター作って計算能力を確保しないとAI競争で負ける」ってことに気づいたってことですよね。アメリカ、中国に遅れを取るわけにはいかないと。
AIが変えるのは「仕事」じゃなくて「生活の前提」
「AIが仕事を奪う」とかよく言われますけど、もうそんなレベルの話じゃなくて、「人間が今までやってたことの意味が変わる」っていう世界になっていくんですよね。 たとえば、今までは「プログラマーがコードを書く」のが普通だったんですけど、もうAIがコードを書いたほうが速くて正確な時代になってる。だから、プログラマーは「コードを書く人」から「AIが作ったコードをチェックする人」になるわけですよ。これ、どんな職業にも当てはまる話で、「医者が診断する」んじゃなくて「AIが診断して、医者はそのチェックをする」とか、「弁護士が契約書を作る」んじゃなくて「AIが契約書を作って、弁護士は問題がないか見る」とか。 で、ここで面白いのが、「チェックする人」になるってことは、実は「AIの言うことを疑う力」が必要になるってことなんですよね。AIがどんなに優秀でも、間違えることはあるわけで、それをちゃんと見抜けるかどうかが重要になる。つまり、これからは「何かを作るスキル」よりも「AIが出した答えが正しいか見極めるスキル」のほうが価値が高くなるわけです。
日本はまた「ルールと議論」で遅れる
で、問題は日本なんですけど、たぶんまた「規制がどうこう」とか「倫理的にどうなのか」とか議論してる間に遅れるんですよね。 これ、いつものパターンで、例えばドローンが流行ったときも日本は「規制が先」で、結局中国に全部持ってかれたわけですよ。でも、アメリカとか中国は「まずやってみる」で、後からルールを作る。AIも同じで、日本は「リスクがある」とか言って足踏みしてる間に、アメリカと欧州がインフラ整えて覇権を取る。 で、日本が「じゃあそろそろAIやろうか」ってなった頃には、もう遅いんですよね。すでにデータセンターは欧米にあって、計算資源も全部そっちが握ってる。だから、日本の企業がAIを使いたくても「欧米のAIを借りる」しかなくなる。そうなると、当然データも全部欧米に渡るわけで、日本独自のAI産業なんて育たないんですよ。
欧州がAIを進めるってことは、ルールも変わる
アルトマンさんが「欧州のルールに従う」って言ってるのもポイントで、これ、AIの規制を欧州が主導するって話なんですよね。 今までは、アメリカの企業がAIのルールを決めてたんですけど、欧州がここに入ってくると、もっと「規制が厳しい世界」になる可能性がある。GDPR(欧州の個人情報保護規則)みたいに、AIの扱いにも厳しいルールができて、それが世界標準になるっていう流れですよね。 で、これ何が問題かっていうと、AIの規制が厳しくなればなるほど、「大手企業しかAIを開発できなくなる」ってことなんですよ。小さいスタートアップが「新しいAIを作ろう」と思っても、「この規制をクリアしないとダメです」とか「このデータは使えません」とか言われたら、もう戦えないわけです。 つまり、「AIを持ってる企業」と「持ってない企業」の格差がどんどん広がる。結局、AIを支配するのはGoogleとかMicrosoftみたいな超巨大企業になって、中小企業や個人がAIを活用するのは難しくなるわけです。
AIが変える社会と日本の未来
人間が「考えない社会」になる可能性
AIの進化が進むと、まず「考える必要がないこと」が増えるんですよね。例えば、今までは「何を食べようか」とか「どのルートで行けば早いか」とか、ちょっとした判断を日常的にしてたわけですけど、それも全部AIが決めてくれる。 で、これが進むと、「そもそも人間が考える機会が減る」っていう問題が出てくるんですよ。昔は「暗算できるのが当たり前」だったのに、電卓が出てから誰も暗算しなくなったように、AIが何でも答えを出してくれるなら、「考える」という行為自体が不要になっていくわけです。 で、これが「便利でいいじゃん」って思う人もいるかもですけど、実はそうじゃなくて、「考える力を持ってる人」と「持ってない人」の格差がめちゃくちゃ広がるんですよね。AIをうまく使える人は、どんどん新しいことを生み出せるけど、AIの言うことをそのまま受け入れるだけの人は、ただの「指示待ち人間」になってしまう。 要は、今後は「AIを使う側」と「AIに使われる側」に社会が分かれて、格差がどんどん固定化されていくんじゃないかって話ですね。
日本の教育はAI時代に対応できるのか
で、これを考えたときに、日本の教育がどうなるかって問題があるんですよね。今の教育って「正解を求める」方向なんですけど、AIが発達すると「正解を出すのはAIの仕事」になるんで、人間がやるべきことは「正解のない問題をどう解決するか」ってことになるわけです。 でも、日本の教育って「間違えないことが大事」っていう考え方なんで、そもそも「答えのない問題に向き合う」っていう訓練をしてないんですよね。これ、かなり致命的で、世界的に見ても「創造性を伸ばす教育」ってのがどんどん進んでる中、日本はまだ「決まった答えを覚える」っていう旧時代的なやり方を続けてるわけです。 だから、このままいくと「AIに仕事を奪われるだけの人材」ばっかりになっちゃう可能性が高い。AIを活用して新しい価値を生み出せる人じゃなくて、AIが出した答えをただ受け入れるだけの人になる。
経済の主役が「データを持ってる企業」に移る
もうひとつの大きな変化として、AIの時代になると「データを持ってる企業」が圧倒的に強くなるんですよね。 例えば、GoogleとかAmazonとかFacebook(今のMeta)みたいな企業は、すでに膨大なデータを持ってるわけです。で、AIの精度って「どれだけデータを学習させるか」で決まるんで、結局「データを持ってる企業」が最強になるんですよ。 これが進むと、中小企業とか個人が「データの壁」にぶち当たるんですよね。例えば、日本の企業が「AIを活用したサービスを作りたい」と思っても、そもそも学習に使うデータがない。で、結局GoogleやAmazonからデータを買うしかなくなる。でも、データを持ってる企業は「自分たちのAIを売るほうが儲かる」んで、わざわざ競争相手にデータを渡したりしないわけです。 つまり、AIの時代って「データを持ってる企業が独占する世界」になりやすいってことですよね。
日本が生き残るには「ニッチ戦略」が必要
じゃあ、日本はどうすればいいのかって話になるんですけど、正直「アメリカや欧州と同じ土俵で戦う」のは無理なんですよね。だって、計算資源もデータもないし、AIの開発競争では完全に遅れてる。 だから、日本が生き残るには「ニッチな分野で戦う」しかないんですよ。例えば、AIって「大量のデータを学習させる」のが基本なんですけど、「めちゃくちゃ専門的な分野のデータ」って、アメリカの企業もそんなに持ってないんですよね。 例えば、日本の伝統技術とか、特殊な製造業のノウハウとか、そういう「他の国が持ってない知識」をAIに学習させて、それを武器にするとか。 あるいは、日本って「アニメ」とか「ゲーム」とか、文化的に強い分野があるんで、そういうクリエイティブな領域にAIを活用するとか。要するに「誰もやってない分野」でAIを活かす戦略を取るべきって話ですね。
未来を決めるのは「AIをどう使うか」
結局、AIの時代になっても「AIを持ってる企業だけが儲かる世界」になるか、「みんながAIを活用できる世界」になるかは、どう使うか次第なんですよね。 今はまだ「AIはすごい!」っていう雰囲気だけで終わってる部分が多いんですけど、これからは「じゃあAIをどう使うのか?」っていう視点が重要になってくる。で、日本の場合、それを決めるのは「規制」じゃなくて「実際にやる人」なんですよね。 だから、本当に日本がAI時代に生き残りたかったら、「議論してる暇があったら、まずやってみる」っていうマインドが必要なんですよ。でも、これが一番難しいんですよね…。
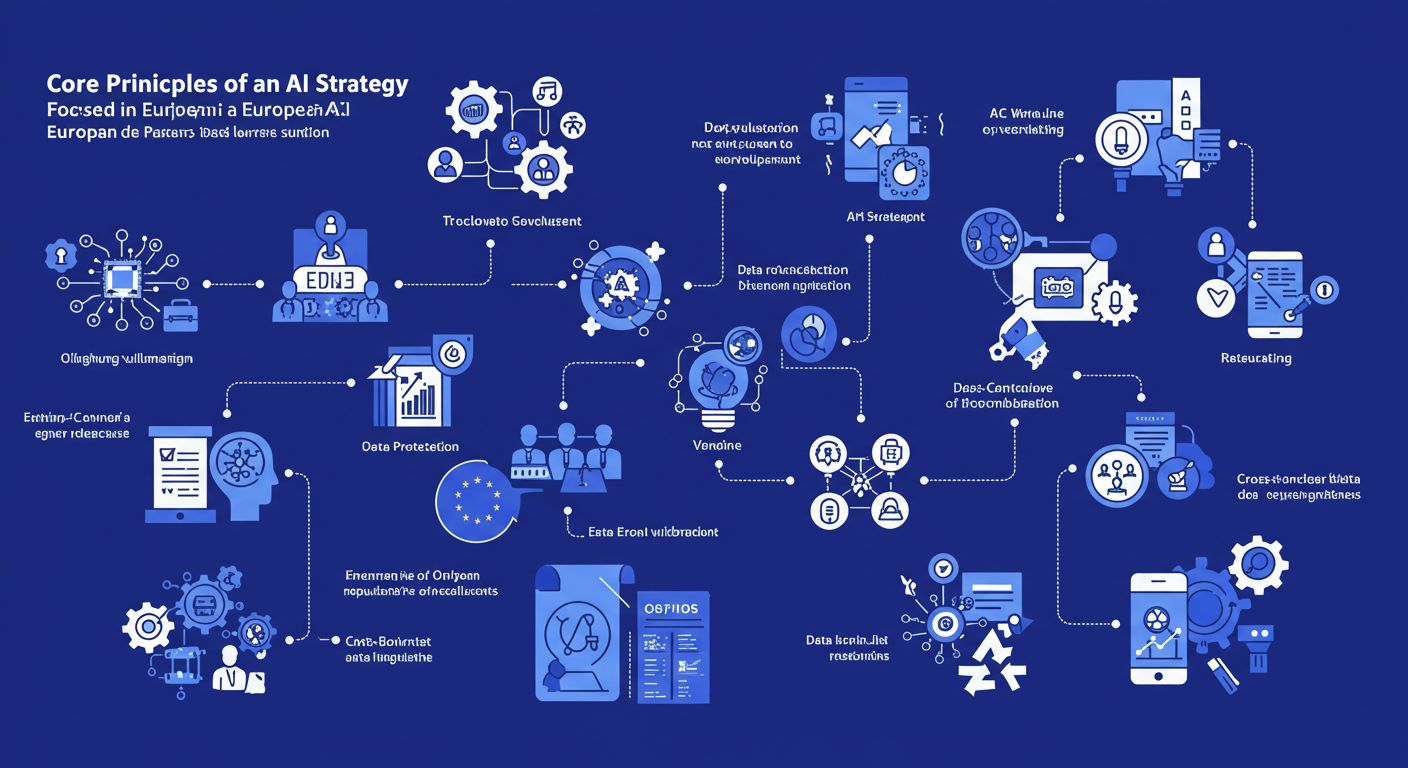


コメント