AIチャットボットによるトラフィック可視化のインパクト
「検索」の時代から「対話」の時代へ
要は、これまでのインターネットって「Googleで検索して、自分で情報を探す」っていうのが当たり前だったんですよね。でも、今ってChatGPTとかのAIチャットボットに「おすすめのレストラン教えて」って聞いたら、それっぽい答えがすぐ返ってくるわけです。人はだんだんと、検索のために複数のサイトをクリックするのが面倒になって、AIに聞く方が楽ってなってくる。
で、Similarwebが出した「AIチャットボットからの流入を可視化する機能」って、つまりは今まで見えなかったAI経由のトラフィックを見えるようにしたってことなんですけど、これって地味にすごく大きな変化なんですよ。なぜかっていうと、企業が「どうすればAIに紹介されるか?」を考え始めるからです。
SEOの終焉とAI最適化(AIO)の時代
今まではSEO、つまりGoogleの検索結果で上位に表示されるために、企業は記事を書いたり、リンクを増やしたりしてたんですよ。でも、ChatGPTとかって「Webページをそのまま表示する」んじゃなくて、「要約された情報」をユーザーに伝えるんですね。
ってことは、AIが「何を学習しているか」とか「どういう情報を重視するか」に最適化する、いわばAIO(AI Optimization)の時代が来るってことなんですよ。企業は「人間に読んでもらう」ためじゃなくて、「AIに読んでもらって、選ばれる」ための文章を作るようになる。
結局、SEOのテクニックってのはGoogleという一社のアルゴリズムをハックするためのものでしたけど、これからは各種AI、それこそOpenAIのGPT、GoogleのGemini、AnthropicのClaudeとか、それぞれに最適化されたコンテンツを作る必要が出てくる。つまり、情報発信者が向き合う相手が「人間」じゃなくて「AI」になるんですね。
社会の中で変わる「情報との接し方」
「調べる能力」が不要になる社会
検索エンジンって、ある意味「情報リテラシー」が試されるツールなんですよ。正しいキーワードを打って、信頼できるサイトを見極めて、情報を取捨選択する能力が必要。でもAIに質問して回答をもらうっていうのは、ユーザーにその力を求めない。
要は「質問力」だけあれば、なんとなくそれっぽい答えが返ってくるから、「調べる能力」とか「情報を比較する力」が必要なくなるわけです。で、これは一見便利なんだけど、裏を返せば「与えられた答えを鵜呑みにする人」が増えるってことでもある。
つまり、AIチャットボットが日常の情報取得の窓口になると、人々の思考力や判断力が鈍ってくる可能性がある。そうすると、どこかでAIが誤った情報を出しても、「それっぽく言ってたから信じちゃった」みたいな人がどんどん出てくるんですよね。
メディアや教育機関の役割の変化
で、そうなった時に大きく変わるのがメディアとか教育機関の役割です。今までメディアは「一次情報を伝える場所」だったけど、AIがニュース記事を要約して伝えるようになると、メディアは「AIに読まれるための文章」を作らないといけなくなる。
教育機関も、これまでは「調べてレポートを書く」っていう学習方法が中心だったけど、「AIが書いてくれる時代」において、それって意味あるの?って話になってくる。要は、学ぶべきは「答えを探す力」じゃなくて「問いを立てる力」に変わってくるわけですね。
で、そういう変化をちゃんと理解して適応できる人と、昔のやり方に固執してる人で、すごい格差が生まれるんですよ。たぶん今の小学生とかは、AIに質問して学ぶのが当たり前の世代になるんで、「Googleで調べて答え探してました」っていう世代は、情報収集の効率で大きく差をつけられるようになると思います。
企業とマーケティングの未来
ブランドの時代から「AIに選ばれる時代」へ
今までって「ブランド力」があると、それだけで人が集まってきたんですよね。トヨタだから安心、ソニーだから品質がいい、みたいな。でもAIにとってブランドって関係ないんですよ。AIが重視するのは「情報の正確性」「文脈」「信頼性」であって、「この会社は有名だからオススメしよう」なんて判断しない。
そうすると企業がやるべきことって、「どれだけAIにとって学習しやすい構造で情報を発信してるか」とか、「定期的に更新してるか」とか、すごく地味な努力になってくる。ブランド広告とかに何億円もかけるより、AI向けに地道な情報設計する方が重要になるかもしれない。
で、これはつまり「企業間の戦いのルールが変わる」ってことです。たとえば地方の小さな会社でも、AIに正しく情報を提供できれば、グローバル企業と同じ土俵で戦えるようになる。逆に言えば、大企業でも情報設計をサボってたら、AIに無視される可能性がある。
マーケターは「AIとの対話者」になる
広告業界やマーケティングの世界でも、大きなパラダイムシフトが起こります。これまでのマーケターは「人間の消費者にどう訴えかけるか」を考えてたけど、これからは「どうやってAIに選んでもらうか」を考えるようになる。
で、その時に重要になるのが「AIにとって意味がある構造のデータを作る能力」なんですね。つまり、マークアップ言語とか、スキーマ構造とか、そういう裏側の設計に詳しい人の価値が上がる。で、表向きのキャッチコピーとかビジュアルとかって、どんどんAIによって最適化されていくから、人間のクリエイティビティが発揮される場所が限定的になってくる。
情報の階層化と「AIに届く声」の偏り
表に出る情報と埋もれる情報の二極化
AIが情報のハブになる社会では、「AIに認識されやすい情報」と「そうでない情報」に分かれていく傾向が強まります。例えば、構造化されたデータや更新頻度の高い信頼性のある情報はAIに拾われやすくなります。一方で、個人のブログやニッチな体験談のような「非構造的で埋もれがちな情報」は、どんなに価値があってもAIの応答に出てこない可能性が高い。
要は、AIの世界観の中では「存在しないことになる情報」が増えてくるんですね。情報はあるのに、AIが認識してないから、一般人の目には触れられない。これは情報の民主化どころか、情報の集中とフィルタリングによる「知の偏り」が起きるってことでもあります。
マイノリティや新興勢力が見えなくなる社会
これって地味にヤバい話で、例えば新興ブランドやスタートアップ、マイノリティの主張みたいなものは、最初はどうしても情報量が少ないんですよ。で、AIはそういう「エビデンスが少ない情報」をあんまり採用しない傾向があるので、「主流の情報」ばかりが再生産される社会になる。
結果として、「まだ知られていないけど、価値あるもの」がいつまでもAIの応答に出てこない。つまり、価値がある情報でも「AIの目に止まらなければ存在しない」と同義になる。こういう偏りが進むと、新しい思想や技術が出にくくなるという弊害があるんですよね。
職業構造の変化と新しいスキルの必要性
「AIに読ませる職人」が求められる時代
で、情報がAIを通じて流通するようになると、新たに必要とされるスキルが出てきます。たとえば「AIに正確に解釈させる文章を書く」スキルとか、「どのフォーマットで出力すればAIが理解しやすいか」を設計する能力。これまでの「キャッチーなコピーを書く」とか「エモーショナルな表現で響かせる」みたいな広告的発想とは逆方向の能力ですね。
要は、文章の美しさや感情的な訴求力よりも、「構文解析されやすいか」「ファクトベースか」「更新されているか」といった要素が評価される。で、そういう技術を持ってる人が「AIとの橋渡し役」になって、情報経済の中で新しいポジションを築くわけです。
中間層のホワイトカラーが危ない
逆に、やばいのが「中間層のホワイトカラー」です。AIが情報の仲介をするようになると、これまで「情報を調べてまとめる」だけで価値があった仕事って、全部AIで代替されちゃうんですよね。たとえば、資料作成とかデータ整理とか、そういう業務ってもはやAIが人間より早くて正確にできる。
結果として、知識労働者の中でも「言われたことを調べてまとめるだけの人」は不要になってくる。じゃあ何が求められるかというと、「AIを活用して何かを生み出す能力」なんですよね。ただ情報を持っているだけじゃなくて、それを元に新しい価値を作れる人だけが生き残れるようになる。
変わる生活習慣と価値観
「自分で考える」時間が減る社会
生活レベルでも変化が出てきます。たとえば、今までは何かを決めるときにいろんなサイトを見比べて、自分で比較して考えるっていう時間があった。でも、AIに聞けば「おすすめ」をすぐ出してくれるので、そのプロセスがどんどん省略される。
で、便利になった反面、「自分の価値観で物事を選ぶ機会」も減るんですよ。AIに選んでもらった選択肢って、要は「他人のロジック」に乗っかってるだけなんで、そこに主体性がなくなっていく。つまり、自分の判断力が衰えるリスクがあるわけです。
「疑う力」が鍵になる時代
だからこそ、今後大事になるのは「AIの答えを疑えるかどうか」っていう力なんですよ。AIは間違えるし、偏ったデータを元に答えることもある。で、それを見抜いて「それって本当に正しいの?」と考えられる人と、そうじゃない人で、情報の信頼度や行動の質に差が出てくる。
つまり、「知識を持つ」よりも「何を信じるかを判断する力」が重要になってくる。今までよりももっと、個人が情報に対して批判的な目を持たないといけない時代になるんですよね。
最終的な未来予測と個人の戦略
AI時代を生き残るために必要なこと
結局、AIが情報流通の中心になると、人間の役割ってどんどん「意思決定」や「創造」の領域に押し出されていくんですよ。で、それができない人は「AIに選ばれない情報を信じて生きる人」になって、どんどんズレた世界に取り残されていく。
だから生き残るには、「AIを使う力」「AIを疑う力」「AIに情報を届ける力」の3つが必要です。要は、AIに頼るのはいいけど、依存しすぎず、常に自分の頭で考えて選び取れる人じゃないとヤバいですって話ですね。
情報発信者の立場が根本的に変わる
あと、個人でも情報発信する人が増えてますけど、「誰に向けて発信するか」を見直したほうがいいです。昔は「人間の読者」に向けて書いてたけど、今後は「AIが読んでくれるか」を考えないと意味がなくなる可能性がある。
つまり、ブログやSNSも「AIに拾われやすい形式」で書く必要が出てくるわけで、それって表現の自由とは逆行してる部分もある。でも、それが現実になるとしたら、僕らが取るべき戦略は「AIに好かれるように設計する」か、「AIのバイアスを逆手に取ってニッチを攻める」か、どっちかです。
で、AIが当たり前のインフラになった未来では、「人間のために情報を書く」っていう価値観そのものが再定義されることになると思ってます。


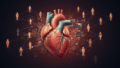
コメント