AIとSNSの融合がもたらす新たな「情報空間」
人間の思考がAIに代替される未来
イーロン・マスク氏が自ら立ち上げたAI企業xAIと、彼が買収したSNS「X(旧Twitter)」を統合するって話なんですけど、これってつまり「AIが人間の情報インフラを直接制御する時代が始まった」ってことなんですよね。
要は、SNSって人間が情報を発信したり受け取ったりするメインの場所なんですけど、そこにAIが直接入り込むことで、どんな情報を誰が見るか、どんなタイミングでどの情報がバズるのか、全部AIが裏でコントロールできちゃうわけです。人間の「思考の入り口」にAIが座る、みたいな。
で、これが本格化するとどうなるかというと、いわゆる「考える人」と「流される人」の差がめちゃくちゃ広がるんですよね。AIが提示してくるニュースや意見をそのまま信じる人たちは、どんどん受け身になっていくし、自分で情報を選んで分析する人たちは逆に武器としてAIを活用できる。
広告と消費行動の進化
AIがSNSと一体化すると、個人の趣味嗜好の分析がリアルタイムで可能になります。要は、「こいつは今ラーメン食いたそうだな」ってAIが判断したら、その瞬間にラーメンの広告が流れてきたりする。これはもう、人間の消費行動を先読みして誘導する「半強制的マーケティング」の時代になると思うんですよ。
今までの広告って一応「見るか見ないかはあなた次第です」っていう体だったんですけど、AIによるパーソナライズが極まると、「気づいたら財布が空になってた」って人が増えてくると思うんですよね。で、そういうのって自己責任の範疇じゃないですか。だから文句を言う前に、AIと付き合う技術が求められるんですよね。
「SNS中毒」の質的変化とAI依存社会
AIとの対話が孤独を埋める?
SNSって「誰かとつながってる感」が魅力だったんですけど、AIがそれを代替するようになると、孤独を感じる人がAIと会話して満たされるって構図になるんですよ。ChatGPTが出てきてから、すでに一部の人はAIと雑談してるだけで満足しちゃってるわけで。
それって便利ではあるんですけど、同時に「人間との関係性が不要になる」ってことでもあるので、社会の人間関係がますます希薄になると思うんですよね。で、そういう孤独をAIが埋めるようになると、「人と話すよりAIと話す方が楽」っていう人が増えてくる。結果として、人間同士のコミュニケーション能力が下がる社会になっていくと。
リアルな会話の価値が上がる
ただ、その逆もあって、AIとの会話に飽きた人たちは「人間と話すってこんなに面白かったんだ」って再評価する動きも出てくると思うんですよね。つまり、リアルな会話の価値が相対的に上がって、「ちゃんと話せる人」が一種のスキルとして重宝される時代になる。
今までは「文章がうまい人」とか「論理的な人」が強かったけど、これからは「人とちゃんと会話できる人」が意外と強くなる。人との対話って予測不能な要素が多いので、AIには完全再現できないんですよ。だから、そこに価値を見出す人が一定数出てきて、「AI疲れ」みたいな現象も出てくると思うんですよね。
教育・就職活動・人間関係の変化
AIが先生になる時代
教育に関しては、もうAIが教師を代替するのは時間の問題だと思っていて、要は「その子に合った教え方をするAI」って、実在する先生より圧倒的に効率いいんですよ。間違えても怒らないし、同じ質問を100回してもちゃんと答える。で、分かるまで付き合ってくれる。
そうなると、「教える側の価値」ってかなり相対的に下がっちゃうんですよね。じゃあ、教育の場で何が残るかっていうと、「人間関係」とか「コミュニケーション」みたいな非言語的な部分だけになる。つまり、学校が「知識を得る場所」じゃなくて「人間関係を学ぶ場所」になるんですよ。
採用の世界がAIと面接官で分断される
就職活動もかなり変わりますよね。企業がAIを使ってエントリーシートを自動選別したり、AI面接で「この人は嘘をついてるか」とか「ロジックに矛盾があるか」を判別するようになる。要は、「人間が見抜けなかったこと」をAIが拾い上げるようになる。
そうなると、今まで「なんとなく印象が良かったから採用」みたいな曖昧な判断がなくなるんですよ。逆にいえば、感情で選ばれることがなくなって、ロジックで評価される世界になる。で、感情的なアピールが得意だった人たちはちょっと不利になるかもなーって思うんですよね。
AI×SNS時代における「格差」の再定義
情報格差から「思考格差」へ
これまで「情報格差」って、インターネットにアクセスできるかどうかとか、英語が読めるかどうかって話だったんですけど、これからは「情報があってもそれを使いこなせるか」っていう「思考格差」に変わっていくと思うんですよね。
要は、AIが大量の情報を目の前に出してくれても、「で、それをどう使うの?」っていう部分が本人に委ねられるわけです。だから、表面上は平等に情報が提供されてるように見えて、実際には「その先で考える力がある人」が有利になる。情報が民主化されたことで、逆に個人の頭の使い方の差が浮き彫りになるって話ですね。
デジタルネイティブの世代にも二極化
デジタルネイティブって「生まれたときからネットがある世代」って言われてますけど、今後はその中でもAIを自分の目的に使える人と、受動的に流される人に分かれていくと思います。
たとえば、「AIで課題を丸投げして終わり」って人と、「AIに質問して自分の考えを深める」って人では、時間が経つにつれてどんどん差が出てくるんですよ。結局、便利なツールがあるからこそ、それをどう使うかのセンスや思考力が求められるわけで。
AI×SNSが生む「新しい社会構造」
分断と同調の強化
AIがSNSのアルゴリズムを強化すると、ユーザーの嗜好に合わせた情報ばかりが届くようになります。つまり、「見たいものしか見えない世界」がさらに加速するわけです。
で、これは一見便利なんですけど、実際は「異なる意見を聞かなくなる社会」をつくるんですよね。結果として、思想の分断が進むし、「同じ意見を持つ者同士だけの閉じた世界」が増えていく。いわゆる「エコーチェンバー現象」がめちゃくちゃ強化される。
その結果、社会全体が「極端な意見」に流れやすくなって、論理やデータよりも「共感できるかどうか」が優先されるようになる。これって、長期的に見ると民主主義の弱体化にもつながるかもしれないっていう懸念もありますよね。
デジタル宗教化の進行
SNSってすでに一種の「信仰」に近い状態になってるんですよ。インフルエンサーの言葉を無条件に信じるとか、「この人が言ってるから正しい」みたいな現象って、完全に宗教的な構造なんですよね。
で、ここにAIが入ってくると、「AIが言ってるから正しい」っていう新しい信仰が生まれる可能性がある。要は、「科学的根拠があるかどうか」じゃなくて、「AIが出した答えかどうか」で物事を判断するようになる。
これって一見合理的に見えて、実は思考停止を助長する構造なんですよね。自分の頭で考える代わりに、AIという「神」に従うような社会になる可能性がある。で、それに対して疑問を持つ人が減っていくと、結局「支配されやすい社会」ができあがるんじゃないかと思うんですよ。
ひろゆき的未来予測:AI時代の「生き残り方」
「無駄なことを考える力」が重要になる
AIが「効率化の権化」みたいな存在になるほど、逆に「非効率なことを考える力」が人間の価値になると思うんですよ。たとえば、AIが最適解を出してくれる時代に、「でも、違う角度から考えたらどうなる?」っていう思考はAIには苦手なんですよね。
結局、人間に残る仕事って「問いを立てる力」とか「常識を疑う力」みたいな、曖昧で非論理的な部分だったりする。で、そういう力って、学校では教えてくれないし、AIも教えてくれない。だからこそ、日常で「意味ないけど面白いこと」に取り組む時間がめちゃくちゃ大事になるんですよ。
「使いこなす側」になるか「使われる側」になるか
最後に一番シンプルな話をすると、AIとSNSが融合した社会で大事なのは、「自分が使う側になるか、使われる側になるか」ってことなんですよね。
SNSをAIが支配して、情報がアルゴリズムに制御されるなら、そこで「見せられる側」にいるより、「見せる側」になった方が強い。つまり、自分で情報を発信したり、分析したり、仕掛けたりする側に回らないと、ただの情報奴隷になっちゃうんですよ。
だから、「何を学ぶべきか」「どう考えるべきか」っていう問いを、自分で持てるかどうかが未来を左右する。AIに使われる人間になるか、AIを使う人間になるか。シンプルだけど、今後の人生が分かれる最大の分岐点はそこなんですよね。
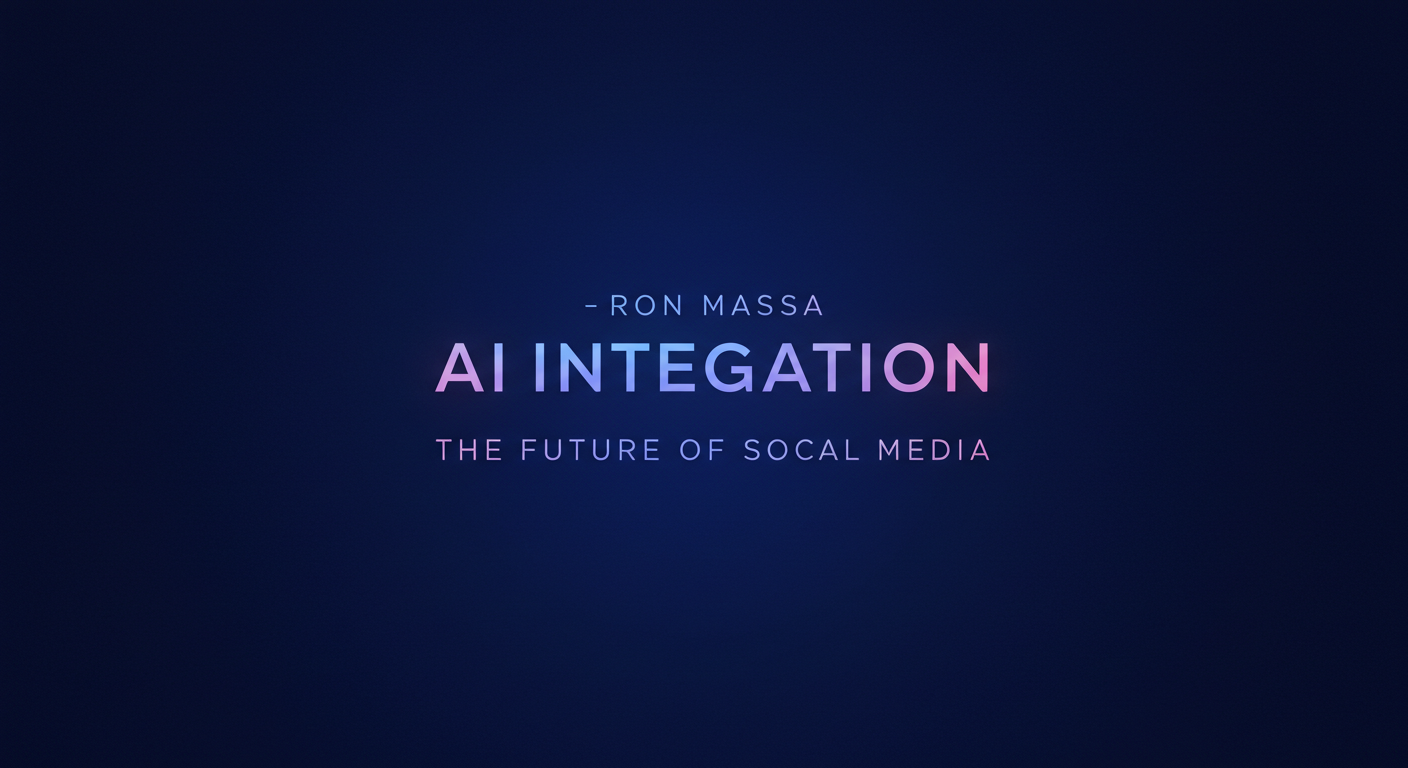


コメント