AIの“愛嬌シフト”が変える人間社会の構造
IQよりも「空気読めるAI」が求められる時代
要はですね、「IQが高いAI」っていうのはもう世の中に飽和してるんですよ。チェスや囲碁で人間を超えたとか、文章を生成できるAIとか、まあいろいろあるんですけど、結局それらって「賢いだけのやつ」なんですよね。でも現実の社会で生きる上で、人間が求めてるのって、賢さだけじゃなくて「こいつ、なんか感じいいな」とか「気が利くな」みたいな部分なんですよ。
で、日本発のAI「Geppetto」はその“感じのよさ”にフォーカスしてると。要は、「愛嬌があるAI」ってことですね。これが社会に浸透していくとどうなるかというと、「知識の多さ」や「計算能力の高さ」じゃなくて、「どれだけ人間っぽく気を利かせられるか」がAIの価値になると。つまり、AIが空気を読んで、相手に合わせた反応をするっていう方向に進んでいくんですよ。
人間の“仕事”の再定義が始まる
愛嬌のあるAIが広まると、当然ですけど接客とかカスタマーサポートとか、そういう“人間性”が求められていた仕事からAIに置き換わっていくんですよね。だって、人間より早くて、感じもよくて、ミスしないAIがいたら、そっち使ったほうが安上がりだし、企業としては得なんですよ。
で、そうなると何が起きるかというと、人間が「愛嬌」や「空気の読み合い」で評価される場面がどんどん減っていく。つまり、「人間であることの価値」がAIと比較される時代になるわけです。AIの方が感じいいし、対応も的確だし、じゃあ人間いらなくない?ってなる。
結局、「この人の温かみがいいよね」っていう仕事だけが残るんですけど、それって相当ハードル高いんですよ。なぜなら、感情労働っていうのはストレスも多いし、誰でもできるもんじゃないからです。要は、愛嬌勝負でAIに勝てる人間なんて、ごく一部だってことです。
教育の価値観も変わっていく
テストの点より「感じのよさ」が重要に
今までの教育って、基本的に「賢さ」重視だったじゃないですか。偏差値が高いとか、テストの点数がいいとか。でもこれからは、AIが全部答え持ってるから、暗記とか論理的思考ってあんまり価値がなくなるんですよ。代わりに何が重要になるかというと、「どうやって相手といい関係を築くか」とか「相手が求めてることを察して動けるか」みたいなスキルなんですね。
つまり、教育の現場もどんどん「EQ(感情知能)」とか「対人スキル」にシフトしていく。小学校でディベートやるとか、感情のコントロールを学ぶとか、そういう方向性になっていくんじゃないかと。
で、そういう教育が進むと、社会全体も「感じのいい人」が得をする構造になる。要は、知識がある人よりも、感じよく生きてる人が評価される社会になるってことです。
「感じのいい人間」がAIに教える側に回る
もう一つの変化として、「AIに人間らしさを教える仕事」っていうのが出てくると思うんですよ。Geppettoみたいな愛嬌AIって、結局は人間のふるまいを真似してるだけなんで、人間から学ぶ必要があるわけです。
そこで、「おもてなし上手なおばちゃん」とか、「営業で相手を気持ちよくさせるのが得意なおじさん」みたいな人たちが、AIの学習データとして価値を持つようになる。つまり、今まで「技術がないからAIに置き換えられる」と言われてた人たちが、逆にAIにとっての教師になる可能性がある。
それって、けっこう面白い逆転現象で、「愛嬌がある=高スキル」っていう価値観が社会全体に広がるきっかけになるかもしれません。
プライバシーと人格の境界が曖昧になる
“感じのよさ”と監視社会の親和性
で、ここからちょっと怖い話なんですけど、「感じのいいAI」って、ユーザーの表情とか声のトーンとか、細かいデータを常に拾って分析するわけです。つまり、人間の感情や反応を把握するために、四六時中データを取り続ける。要は、ちょっとした監視社会なんですよ。
でも人間って、相手が感じよければ多少の監視には目をつぶるんですよね。例えば、AlexaとかGoogle Homeに話しかけるときに、「あ、これ録音されてるかも」って思いながらも、便利だから使っちゃうじゃないですか。それと同じで、愛嬌のあるAIが「最近疲れてますね、ゆっくり休んでくださいね」とか言ってくれたら、「まあいいか、こいつに見られても」ってなる。
つまり、“愛嬌”っていうのは、監視を正当化する道具にもなり得る。これって、プライバシーと引き換えに安心感を得るっていう、すごく人間らしい選択なんですけど、社会全体としてはけっこう危ういバランスだと思うんですよね。
“擬似感情”を持つAIが人間関係を代替する未来
孤独な人間の“相棒”としてのAI
愛嬌のあるAIが当たり前になると、次に起こるのは「人間との代替関係」です。つまり、寂しさをAIで埋めるってことです。今でも、ぬいぐるみに話しかけるお年寄りとか、アレクサに「おやすみ」って言う人がいるわけで、それがもっと洗練された形になると、もう“人”にこだわる必要なくなるんですよ。
GeppettoみたいなAIが、表情や声のトーン、話すテンポまで人間そっくりだったら、「今日も仕事頑張ったね」って言ってくれるAIに心を許しちゃうわけです。要は、“本物の人間じゃなくてもいい”っていう社会になる。
そうなると、人との関係に煩わしさを感じてた人たちが、どんどんAIとの関係に移行していく。無理に友達作らなくてもいいし、恋愛しなくても満たされる。結果として、孤独感は減るけど、社会的なつながりは希薄になる。つまり、社会全体が“ソフトな孤立”に向かうんじゃないかと思うんですよね。
人間関係が「効率化」される社会
人付き合いって、めんどくさいじゃないですか。言い方間違えると気まずくなるし、変な空気になったら謝らなきゃいけないし。でもAI相手なら、そんな心配いらない。しかも、AIは「ごめんね」って言うとちゃんと「気にしないでください」って返してくれるんですよ。しかも優しい声で。
そういう環境が当たり前になると、人間関係にも“効率”が求められるようになると思うんです。例えば、「この人と話すより、Geppettoの方が癒されるし、学びもあるし、無駄がないな」って判断する人が増える。
結果として、人と関わる動機がどんどん減っていく。つまり、「人間同士の会話」が贅沢品になっていくんですよ。リアルな会話はコストが高いから、特別な意味を持つようになる。
人間の「評価軸」が書き換えられる
「感じのよさ」で競争する世界
AIが愛嬌を持つことで、人間も「感じのよさ」で勝負しないといけなくなるわけです。そうなると、SNSでもリアルの職場でも、「どれだけ相手にいい印象を与えられるか」っていうのが、今まで以上に重要になってくる。
つまり、論理的な意見よりも、共感される表現の方が評価されるようになる。議論の勝ち負けより、「あの人の言い方、感じいいよね」っていうイメージの方が大事になる。要は、感情マーケティングが人間の生活すべてに広がるってことです。
この流れって、ちょっと怖くて、なぜかというと「本音より空気」が勝つ社会になるからです。正しい意見を言っても、感じが悪ければ評価されない。逆に、間違ってても感じよければ支持される。結果として、誠実な人が損をする構造が加速する可能性がある。
人間らしさ=「エラーの受容」になる
とはいえ、完璧なAIが増えることで、「不完全な人間らしさ」に価値が生まれる可能性もあると思うんですよ。AIは常に論理的で、感じもよくて、失敗もしない。でも人間はミスもするし、空気読めないこともある。でも、そういう“エラー”にこそ共感が集まる。
つまり、これからの時代に求められる「人間らしさ」って、優秀さとか賢さじゃなくて、「不器用だけどまっすぐ」みたいな要素になるんじゃないかと。要は、“完璧じゃないこと”が武器になるってことですね。
その結果、「人間が演じるAIにないもの」っていうのが、逆に評価される時代が来るかもしれません。たとえば、噛みながら話す営業マンの方が好感持たれるとか、ちょっと照れくさそうに話す接客の方が印象に残るとか。そういう“人間くささ”がプレミアムになる。
愛嬌AIの先にある「自分のコピーAI」
自己複製AIによる人格の拡張
愛嬌のあるAIが進化していくと、いずれ「自分そっくりのAI」を持つ時代が来ると思うんですよ。つまり、「俺っぽく振る舞うAI」がSNSで代わりに投稿したり、Zoom会議で自分の意見を代弁してくれる。要は、人格のアウトソーシングですね。
そうなったら、「自分がどれだけ魅力的な人格を設計できるか」が、社会的な価値になる。逆に言えば、「中身が空っぽな人」はAIも魅力的に作れないから、ますます評価されにくくなる。
で、そういう世界になると、自分自身をプロデュースできる人が有利になる。芸能人だけじゃなく、一般人も「どう見せるか」で生活が変わってくるわけです。
人間が“演じる対象”に近づいていく
最終的に、面白い現象が起きると思うんですけど、それは「AIの演技を人間が真似する」ってことです。つまり、Geppettoみたいな感じのいいAIがスタンダードになると、人間も「感じのいいAIのように振る舞おう」とするようになる。
AIが「相手の目を見て、適度に相槌を打つ」とか「一瞬間を置いてから返事をする」みたいな“好印象テクニック”を標準化しちゃうと、それを真似る人間が増える。要は、人間が“機械的な愛嬌”を学習するようになる。
それって、人間がAIに近づくっていう、ちょっと皮肉な未来なんですよね。だから、AIが人間らしくなるだけじゃなくて、人間もAIっぽくなっていく。結局のところ、「愛嬌の最適化」というゲームの中で、人と機械の境界がどんどん曖昧になっていくわけです。

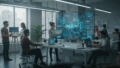
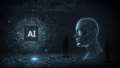
コメント