生成AI時代のSSD革命がもたらす未来
データ処理が速くなると、何が起こるのか
要は、今まではデータが膨大になりすぎて処理が追いつかないっていう問題があったわけですよね。でも、大容量SSDの登場によって、そのボトルネックが解消される可能性が高いんですよ。つまり、AIの処理速度が上がるだけじゃなく、AIが使えるデータの量も一気に増えるわけです。 例えば、これまで画像生成AIが一枚の画像を作るのに10秒かかってたとしましょう。それが1秒で済むようになると、試行錯誤の回数が増えて、より高品質な画像を短時間で大量に作れるようになるんですよね。これ、単純に便利ってだけじゃなくて、クリエイティブな仕事の進め方が根本から変わる可能性があるんですよ。
AIの成長スピードがさらに加速する
AIが学習するためには大量のデータが必要なんですけど、従来のストレージ技術だと読み書きの速度に制限があったわけです。で、大容量SSDが進化すると、この制限がかなり緩和されるんですよね。 要は、今までAIが1年かけて学習していたデータ量を、数カ月で処理できるようになる可能性があるってことです。そうなると、AIの成長スピードがこれまで以上に速くなって、「半年後には全然違うAIが登場している」みたいな世界になっていくんじゃないですかね。 この影響って、単にAIの精度が上がるって話じゃなくて、AIを使ったサービスやビジネスの回転速度も爆速になるってことなんですよ。例えば、企業が新しいAIを開発して、数カ月で市場に出して、すぐに次のバージョンを投入する、みたいな流れが普通になってくるわけです。
一般人の生活はどう変わるのか
結局、技術が進歩するときに一番影響を受けるのは一般人なんですよね。例えば、スマホのカメラがAIで超高性能になったら、もう「プロのカメラマンしか撮れない写真」っていう概念がなくなるわけです。要するに、誰でも簡単に高品質な写真や動画が作れるようになる。 で、それがもっと進むと、「仕事でプロのスキルが必要なくなる」って現象がどんどん増えてくるんですよね。例えば、動画編集でもAIが自動でいい感じに仕上げてくれるようになると、編集スキルがなくてもYouTubeで収益化できる人が増えるとか。 つまり、専門的なスキルを持たなくても、それなりにクオリティの高いアウトプットができるようになるってことなんです。これ、便利ではあるんですけど、逆に「専門職の価値が下がる」って問題も出てくるんじゃないですかね。
仕事のあり方が根本的に変わる
結局のところ、大容量SSDの登場によって、AIの進化が加速するって話なんですけど、それが仕事の世界に与える影響ってかなり大きいと思うんですよ。 例えば、今までは「時間をかけてスキルを磨いて、一流の仕事をする」みたいな価値観があったわけです。でも、AIが一瞬でやっちゃうようになると、その価値観自体が崩壊する可能性があるんですよね。 特に、デザインとか動画編集とか、クリエイティブな分野は影響を受けやすいですよね。今までは「経験を積んだ職人だけができる仕事」だったのに、AIと高性能なストレージが組み合わさることで「誰でもできる仕事」になっていく。 そうすると、逆に「人間にしかできない仕事って何?」って話になってきますよね。AIがすべての作業を高速化する中で、人間が求められるのは「AIが持っていないものを作れるかどうか」ってことになってくるわけです。 結局、AIに仕事を奪われるか、それともAIをうまく活用して新しい価値を生み出せるか、ここが重要になってくるんじゃないですかね。
AIと人間の役割の変化
AIが人間の思考までサポートする未来
結局のところ、AIとストレージの進化によって、人間の思考プロセスすらサポートされる未来になっていくと思うんですよね。 例えば、今までは「アイデアを考える」のは人間の仕事だったわけです。でも、AIが過去のデータを元に「こういうアイデアはどうですか?」って提案してくるようになると、人間はそれを選ぶだけでよくなる。つまり、「思考の効率化」が進むんですよね。 で、これが進んでいくと「考えることすら不要になる」って現象が起こる可能性があるんですよ。要するに、アイデアを生み出すのも、整理するのも、実行するのも、全部AIがやってくれると。「じゃあ人間って何するの?」って話になるんですよね。 結局、人間がやるべきことは「AIが出した答えをどう判断するか」っていう部分になってくると思うんですよ。要は、AIが提示した選択肢の中から、何を採用するのかを決める能力が重要になってくるわけです。
労働時間の概念が変わる
AIがどんどん進化して、人間の仕事を効率化していくと、労働時間の概念も変わると思うんですよね。 例えば、今までは「1日8時間働くのが普通」って考え方だったわけです。でも、AIが仕事をサポートしてくれることで、1日3時間働けば十分な成果が出せるようになる可能性があるんですよ。 そうなると、「長時間労働=頑張ってる」みたいな価値観がなくなって、「短時間で最大の成果を出すことが重要」って考え方にシフトしていくんじゃないですかね。 で、これが広まると、「そもそもフルタイムで働く必要ある?」って話になってくるわけですよ。企業側も、「AIが仕事をやってくれるなら、人間の労働時間を減らした方がコスト削減になる」って考えるようになる可能性があるんですよね。 結局、「仕事は長時間やるもの」っていう固定観念が崩れて、「いかに短時間で効率よく成果を出せるか」って方向にシフトしていくんじゃないですかね。
人間が求められる新しいスキル
で、そういう世界になると、人間が求められるスキルも変わってくるんですよ。 例えば、今までは「経験」とか「技術」が重要だったわけです。でも、AIがそれを補ってくれるようになると、経験とか技術そのものの価値が下がるんですよね。 じゃあ、何が大事になるかっていうと、「AIとどう付き合うか」っていうスキルが求められるようになると思うんですよ。 要は、「AIをうまく使いこなせる人」と「AIに振り回される人」に分かれてくるわけです。で、AIをうまく活用できる人は、短時間で大きな成果を出せるし、逆にAIに依存しすぎる人は、判断力を失ってしまう可能性があるんですよね。 結局、「AIをツールとして使いこなせる人」が、これからの時代の勝ち組になっていくんじゃないですかね。
社会全体の価値観が変わる
で、こういう流れが進むと、社会全体の価値観も変わってくるんですよ。 例えば、今までは「努力してスキルを身につけるのが大事」って考え方が主流だったわけです。でも、AIがスキルを代わりに持ってくれるようになると、「努力の方向性」が変わってくるんですよね。 要するに、「どんなスキルを磨くか」よりも、「どうAIを使うか」の方が重要になってくるってことです。 で、これって教育のあり方にも影響してくると思うんですよ。今の教育って、「知識を身につけること」が目的になってるじゃないですか。でも、AIが知識を持ってる時代になると、「知識を持っていること」自体には価値がなくなって、「どう活用するか」が重要になってくるわけです。 そうなると、今の教育システムも大きく変わる必要が出てくるんじゃないですかね。 結局、AIの進化って、「今まで当たり前だった価値観を壊していく」って話なんですよ。で、それをどう受け入れて、新しい時代に適応するかが、これからの社会の課題になってくるんじゃないですかね。
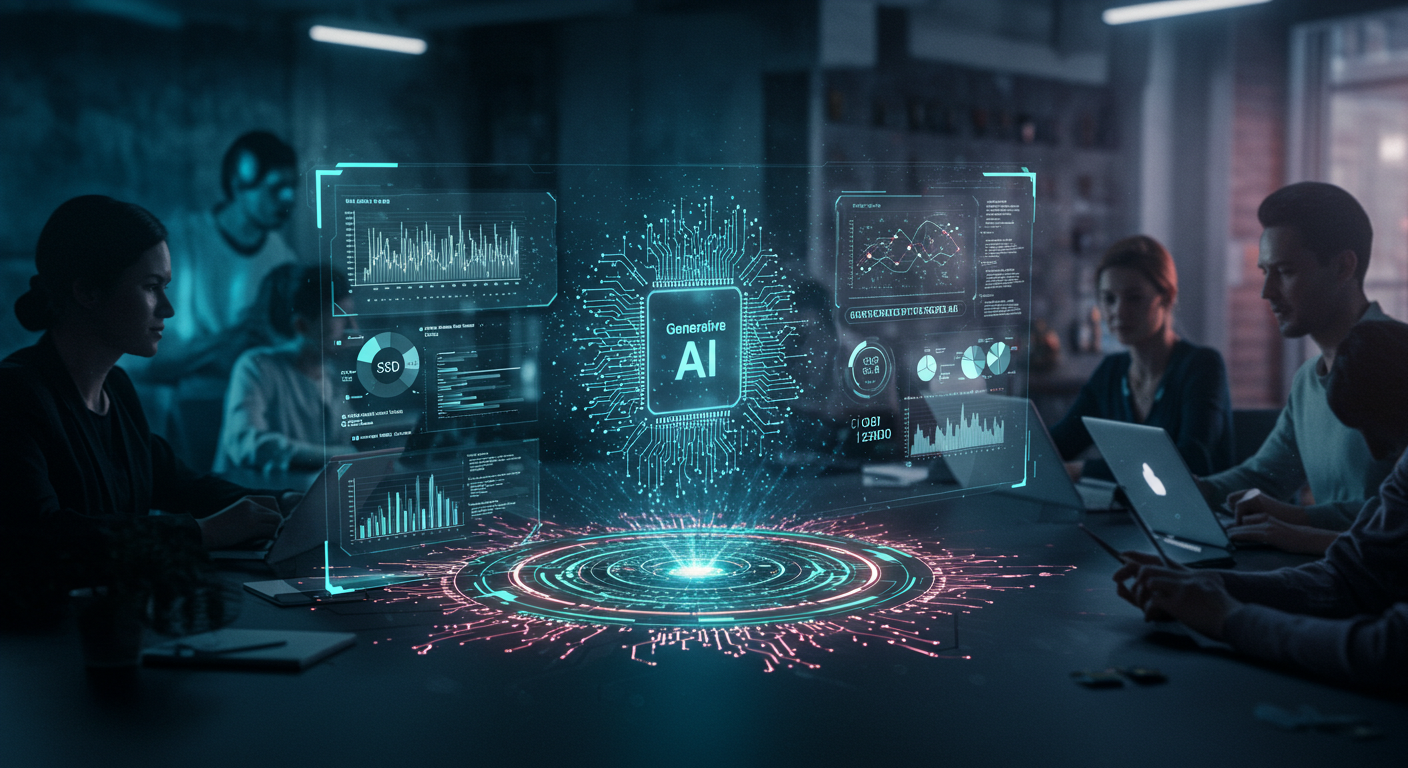


コメント