NTTの生成AIサービスがもたらす未来とは
要は、役所仕事がAIで最適化されるって話
NTT東日本が生成AIサービスを始めたんですけど、これって結局、今まで人間がやってた無駄な仕事をAIに丸投げできるって話なんですよね。たとえば、役所で住民からの問い合わせに対応するために何十人も人を配置してたのが、AIにやらせれば一発で済むと。これ、めちゃくちゃコスト削減になるんですよ。
今まで「それって人間が対応しなきゃダメだよね」って思われてた領域まで、AIが普通に対応する未来が来ると。しかも、ミスもしないし、休まないし、クレームも感情的に受けないから、トータルで見たら人間より優秀なんですよね。
結局、官公庁の雇用は減るんじゃないですか?
結局、役所とか公的機関って、いろんな業務を人手でやる前提で組織ができてるんですけど、それ自体が時代遅れになっていくんですよね。要は、問い合わせ対応だけじゃなく、申請書類の確認とか、データベースの照合とか、AIが得意な作業ってめちゃくちゃあるんですよ。
だから将来的には、役所の窓口って、ほぼ無人になると思うんですよね。AI端末に向かって話しかければ全部済む。しかも24時間対応。人間はシフトも組まなくていいし、残業代もかからない。コスト的にも市民サービス的にも、AI化が進んだほうがみんな幸せになるって話です。
その結果、官公庁で働く人の数は減るし、役所っていう存在自体が「何かあったらネットで完結する場所」になるんじゃないかなと。要は、窓口業務って職種自体が絶滅危惧種になる未来が見えるんですよ。
社会全体に広がる影響
要は、ホワイトカラーのリストラが本格化する
役所だけじゃなくて、民間企業にもこれ絶対波及するんですよ。たとえば、カスタマーサポートとか、営業資料作成とか、社内向けマニュアル作成とか、そういうルーチンワークは全部AIで代替可能になる。
だから、ホワイトカラーの仕事がどんどん減っていく未来が来ると。これ、ブルーカラーの自動化よりもインパクトでかいんですよね。工場のロボット導入はずっと前から進んでたけど、知的労働がAIに置き換わるって、もっと根本的な社会変化なんですよ。
要は、頭使ってるフリしてた人たちが一番危ないってことなんですよね。「うちの仕事はクリエイティブだからAIにできない」とか言ってた人たちも、実際には8割くらいルーチンだったことがバレる未来が来る。しかも、クオリティもAIのほうが高いってなると、人間の価値って一気に下がるんですよ。
結局、使う側に回るしかないって話
じゃあどうするの?って話になるんですけど、要は、AIに使われる側じゃなくて、AIを使いこなす側に回るしかないんですよね。つまり、AIをどう設計して、どうチューニングして、どうビジネスに組み込むかを考える人間が必要になる。
でも、それって今のホワイトカラーの半分以上はできないと思うんですよね。だって、自分で考えて仕事作ってたわけじゃなくて、与えられたルールに従って作業してただけだから。自分で考える能力がない人たちは、どんどん淘汰されていく未来が待ってると思います。
結果として、社会の格差はますます広がる。AIを使いこなせるごく一部の人たちがめちゃくちゃ稼ぐ一方で、大多数は「AIに仕事を奪われた人たち」として低賃金労働に追いやられる。要は、資本主義の勝ち組と負け組がもっとハッキリ分かれる世界になるんですよね。
人間に求められるスキルの変化
つまり、創造力と適応力が必須になる
AIにできないことって、結局、ゼロから新しいものを生み出す力と、環境が変わったときに柔軟に対応する力なんですよ。だから、これから求められるのは「指示待ち人間」じゃなくて、「自分で課題を見つけて、自分で解決方法を考えられる人」だけ。
たとえば、今までだったら「上司の指示を正確に実行する」ことが評価されてたけど、これからは「上司も気づいてない問題を見つけて勝手に解決する」人だけが生き残る世界になる。つまり、会社に言われたことをやるだけの人は、AIの下位互換として淘汰されるってことです。
要は、「考えない人間は要らない」という時代が、本格的に始まるんですよね。
結局、学び続けるしかない未来
あと、変化がめちゃくちゃ速くなるんですよ。5年前の常識が今では全然通用しないみたいなことが、さらに加速する。だから、大学出たらゴールとか、会社に就職したら一生安泰とか、そんな甘い考え持ってる人は普通に詰みます。
常に新しいスキルを学び続けて、変化に適応し続けないと、あっという間に時代遅れになる。で、変化に乗り遅れた人は、社会の底辺に落ちるしかない。別にそれが悪いってわけじゃないけど、要は「自分で努力しない人は勝手に落ちていく社会になる」ってだけなんですよね。
うん。まあ、自己責任ですよね。
AIによる社会の再設計
つまり、行政サービスの再構築が始まる
NTT東日本の生成AI導入って、単に業務効率化とかそういう小さな話じゃなくて、社会全体のインフラの作り直しに繋がると思うんですよね。今まで行政サービスって、基本的に「人間が人間のために」やることが前提だったけど、そこを根本から変える。
たとえば、住民票とか、税金の申告とか、福祉の申請とか、全部AIとチャットで完結する未来が来るわけです。で、人間が必要になるのは「AIでは判断できない例外対応」とか「新しい制度設計」とかだけ。
結局、ほとんどの住民対応は標準化できるし、AIのほうが圧倒的に正確で早い。これ、普通に考えて、税金の無駄遣いが減るって話なんですよ。だから、日本みたいに財政が厳しい国にとっては、めちゃくちゃありがたい流れだと思うんですよね。
要は、信頼されるAIが鍵になる
ただ、結局のところ、「本当にAIを信用していいのか?」って話にはなると思うんですよ。たとえば、間違った情報を出すリスクとか、バイアスの問題とか、いろいろあるんですよね。
だから、AIの品質管理とか、データの透明性とか、そういう信頼性の確保がめちゃくちゃ重要になってくる。要は、「人間よりミスが少ないAI」を作るだけじゃダメで、「なぜその答えになったのかを説明できるAI」が必要になる。
この辺をきちんと作り込めるかどうかで、国や企業の競争力が決まる未来になるんじゃないかなと。つまり、AIの精度と説明責任、この2つが次の時代のインフラ基盤になるわけです。
個人の生き方が根本から変わる
つまり、組織に依存するリスクが高まる
これからの社会って、会社とか自治体とか、組織に依存するリスクがどんどん高まるんですよ。要は、組織そのものが変化に適応できなかったら、あっという間に沈没する時代になる。
たとえば、大企業に就職して安泰とか、公務員だから安心とか、そういう考え方が完全に終わる。AIを導入できなかった役所は、市民から「遅すぎる」「不便すぎる」って批判されて、予算削減されるし、下手したら民間に業務委託されて職員ごとリストラされる。
つまり、個人が生き残るためには、「自分自身で食っていける力」を持つしかない。スキルセットのアップデートとか、副業とか、起業とか、そういう選択肢を持ってないと、めちゃくちゃリスキーな時代が来るんですよね。
結局、自分で選べる人だけが自由を手に入れる
未来の社会って、「どこに所属してるか」より「自分に何ができるか」が圧倒的に重要になる。つまり、肩書きとか年功序列とか、そんなものにしがみついてる人はどんどん苦しくなる。
逆に、自分のスキルで自由に働ける人は、めちゃくちゃ楽になると思うんですよね。働く場所も時間も自由に選べるし、収入源も複数持てるから、リスク分散もできる。要は、「自分の人生を自分でデザインできる人」だけが、これからの社会で楽しく生きられる。
この流れって、たぶんもう止められないんですよ。AI技術が進化すればするほど、人間に求められるのは「自己決定能力」と「行動力」だけになる。誰かに指示されて動く時代は、本当に終わりに近づいてるんですよね。
未来は悲観よりも期待すべき理由
つまり、面倒な仕事から解放されるチャンス
ここまで聞くと「未来怖い」と思うかもしれないんですけど、実はめちゃくちゃポジティブな面もあるんですよね。要は、AIにできる仕事は全部AIに任せて、人間はもっとクリエイティブなことに集中できる。
たとえば、ルーティンワークから解放されたら、アートやエンタメや研究開発とか、今まで時間が取れなかった分野にもっと力を注げるようになる。で、そういう分野って、人間が本当に楽しめることだったりするんですよ。
つまり、AI時代って、人間が「やりたくないけど仕方なくやってた仕事」から解放されるチャンスでもある。めんどくさい手続きとか、書類作成とか、全部AIに任せて、人間はもっと自由に生きられる未来が来るわけです。
結局、未来は自分次第って話
最後にまとめると、要は「未来がどうなるか」は、AIの進化そのものじゃなくて、「人間がどう使うか」で決まるって話なんですよね。変化にビビって何もしない人は、淘汰されていく。でも、変化を受け入れて、自分の武器にできる人は、めちゃくちゃチャンスを掴める。
だから、未来を悲観するんじゃなくて、「どうやってこの流れを利用するか」を考えたほうが建設的なんですよ。別に全員がプログラミングできる必要はないけど、AIに何をさせるかを考える力くらいは、最低限持っておいたほうがいい。
結局、未来は勝手にやってくるんじゃなくて、自分で作るものなんですよね。うん。そう考えたほうが、人生楽しくなると思いますよ。
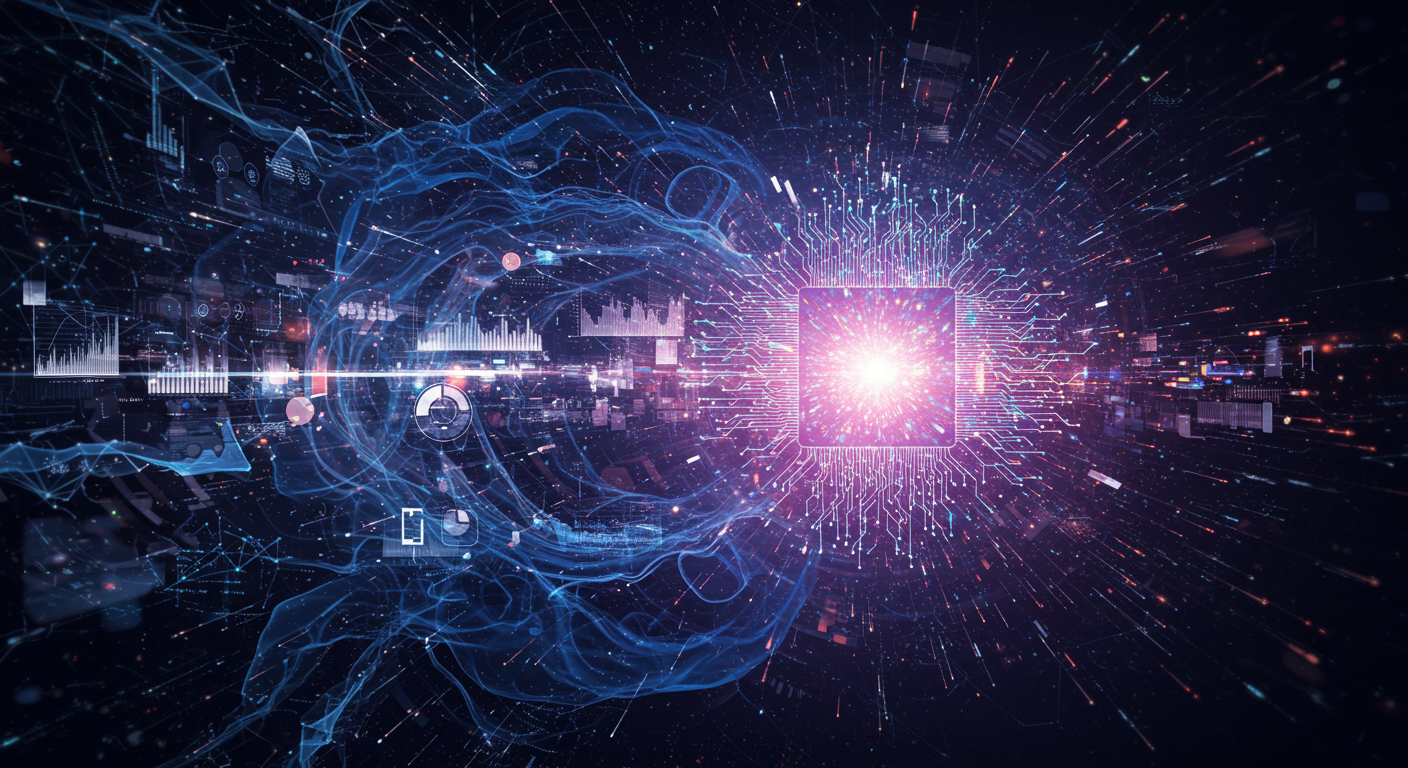


コメント